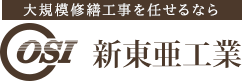ウレタン防水 通気緩衝工法は何? 修繕-神奈川
2021/03/20
ウレタン防水 通気緩衝工法とは?メリット・デメリット、施工方法まで徹底解説
建物の屋上やバルコニーの防水工事で広く採用されているウレタン防水。その中でも「通気緩衝工法」は、特定の条件下で優れた性能を発揮する重要な工法です。
しかし、「密着工法と何が違うの?」「どんな時に選ぶべき?」といった疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。
この記事では、ウレタン防水の通気緩衝工法について、その仕組みや特徴、メリット・デメリット、そして具体的な施工の流れまで、専門的な視点から分かりやすく解説します。
ウレタン防水 通気緩衝工法とは?仕組みと特徴を解説
ウレタン防水 通気緩衝工法は、液体状のウレタン樹脂を塗り重ねて防水層を形成するウレタン塗膜防水工事の一種です。
最大の特徴は、下地と防水層の間に意図的に「通気層」を設ける点にあります。これは、一般的な「密着工法」が下地に防水材を直接塗り付けるのとは対照的です。
通気緩衝工法では、まず下地に穴の開いた特殊なシート(通気緩衝シート)を貼り付け、その上からウレタン防水材を塗布します。
この工法の主な構成要素と仕組みは以下の通りです。
- 下地処理
施工面を高圧洗浄などで清掃し、必要に応じてひび割れ補修などを行います。良好な下地状態が、防水層の性能を左右します。
- プライマー塗布
下地と通気緩衝シートの密着性を高めるために、プライマー(接着剤)を塗布します。
- 通気緩衝シートの設置
下地の上に、通気性を持つ特殊なシートを敷設します。このシートは、下地からの湿気を防水層の下で拡散させ、外部へ逃がすための通路となります。シート自体は全面接着せず、部分的に固定されるか、自着層を持つタイプが用いられます。
- 脱気筒(だっきとう)の設置
シート下にこもった湿気や水蒸気を外部へ排出するための専用の筒状の装置(脱気筒)を、一定の間隔で設置します。これが湿気の逃げ道となり、防水層の「ふくれ」を防ぐ重要な役割を担います。
- ウレタン防水材の塗布
通気緩衝シートの上に、液体状のウレタン樹脂を複数回に分けて塗り重ね、規定の厚さの防水層を形成します。
- トップコート塗布
形成されたウレタン防水層を紫外線や摩耗から保護するため、最上層にトップコートを塗布して仕上げます。
この「通気層」と「脱気筒」の組み合わせにより、下地に含まれる水分が蒸発しても、その水蒸気が防水層を持ち上げてしまう「ふくれ」現象を効果的に抑制します。また、通気緩衝シートが下地の動き(ひび割れなど)をある程度吸収する緩衝材としての役割も果たします。
通気緩衝工法のメリット:なぜ選ばれるのか?
ウレタン防水 通気緩衝工法が多くの現場で選ばれる理由は、そのユニークな構造がもたらす複数の利点にあります。特に、改修工事においてそのメリットが最大限に活かされるケースが多いです。主なメリットを以下に挙げます。
防水層の「ふくれ」を抑制できる:
最大のメリットです。下地に含まれる水分が温度上昇によって水蒸気となっても、通気層と脱気筒を通じて外部に排出されるため、防水層が下から押し上げられる「ふくれ」の発生リスクを大幅に低減します。これにより、防水層の早期劣化を防ぎ、長期的な信頼性を確保します。
下地の水分影響を受けにくい:
密着工法では下地の乾燥状態が非常に重要ですが、通気緩衝工法はある程度の下地水分が存在しても施工が可能です。これは、湿気を逃がす仕組みがあるためで、工期の短縮や、梅雨時期など天候に左右されやすい時期の施工において有利になります。ただし、極端に湿潤な状態での施工は推奨されません。
下地の挙動(動き)に対する追従性が高い:
下地と防水層の間に緩衝材となるシートが存在するため、建物の振動や温度変化による下地の伸縮、軽微なひび割れなどの動きを吸収し、防水層の破断リスクを低減します。これにより、特に動きの大きい建物や、既存防水層の上に施工する場合に適しています。
既存防水層の状態に左右されにくい場合がある:
既存の防水層(例:アスファルト防水など)の状態によっては、撤去せずに上から施工できるケースがあります。これにより、撤去費用や工期の削減、廃材の削減につながる可能性があります。ただし、既存防水層の劣化状況や種類によっては適用できない場合もあるため、事前の診断が不可欠です。
これらのメリットにより、通気緩衝工法は特に防水改修工事において、信頼性が高く、適用範囲の広い工法として位置づけられています。
通気緩衝工法のデメリットと注意点
多くのメリットを持つウレタン防水 通気緩衝工法ですが、採用を検討する際には、いくつかのデメリットや注意点を理解しておく必要があります。これらを把握し、現場の状況や予算と照らし合わせて最適な工法を選択することが重要です。
密着工法と比較してコストが高い傾向にある:
通気緩衝シートや脱気筒といった専用部材が必要となり、工程も増えるため、材料費・施工費ともに密着工法よりも高くなるのが一般的です。初期費用を抑えたい場合には、他の工法との比較検討が必要になります。
施工に手間と時間がかかる:
シートの敷設、脱気筒の設置など、密着工法にはない工程が含まれるため、全体の工期が長くなる傾向があります。迅速な施工完了が求められる場合には、スケジュールの確認が重要です。
防水層の厚みが増す:
下地にシートを敷設する分、全体の厚みが密着工法よりも増します。サッシ廻りやドレン廻りなど、納まりに高さ制限がある箇所では、事前の寸法確認や調整が必要になる場合があります。
複雑な形状への施工が難しい場合がある:
シートをきれいに敷設する必要があるため、凹凸が多い、狭小部が多い、設備基礎などが多数存在するなど、非常に複雑な形状の部位への施工は、密着工法よりも難易度が上がり、手間がかかることがあります。
脱気筒の設置が不可欠:
通気緩衝工法の性能を十分に発揮させるためには、適切な位置と数量の脱気筒設置が必須です。この設置スペースが確保できない場合や、意匠的に設置を避けたい場合には、採用が難しくなります。
シート下の状態を確認しにくい:
一度シートを敷設してしまうと、その下の状態を目視で確認することは困難になります。そのため、施工前の下地処理や清掃がより重要となります。
これらの点を考慮し、建物の状態、要求される性能、予算、工期などを総合的に判断して、通気緩衝工法の採用を決定する必要があります。
通気緩衝工法が適した建物と施工の流れ
ウレタン防水 通気緩衝工法は、その特性から特定の条件下で特に推奨される工法です。どのような建物や状況に適しているのか、そして実際の施工がどのように進められるのかを解説します。
通気緩衝工法が適している主なケース:
- 既存防水層が水分を含んでいる可能性のある改修工事
特に、既存のアスファルト防水層やシート防水層の上に新たにウレタン防水を行う場合、内部に湿気が残っていることがあります。このような場合に密着工法を用いると「ふくれ」のリスクが高まるため、通気緩衝工法が適しています。
- コンクリート下地に微細なひび割れが多い、または動きが予想される建物
RC造(鉄筋コンクリート造)の建物でも、築年数が経過するとひび割れが発生しやすくなります。通気緩衝シートが緩衝材となり、下地の動きに追従しやすいため、防水層の破断を防ぐ効果が期待できます。
- 比較的広い面積の屋上
面積が広いほど、温度変化による下地の伸縮や水蒸気の発生量も多くなる傾向があります。通気緩衝工法は、こうした影響を緩和するのに効果的です。
- 工期に多少の余裕があり長期的な信頼性を重視する場合
コストや手間はかかりますが、「ふくれ」のリスクを低減し、防水層の耐久性を高める効果が期待できるため、長期的な視点でのメンテナンスコスト削減につながる可能性があります。
基本的な施工の流れ:
- 下地調査・清掃
既存防水層の状態、下地の種類、劣化状況などを確認します。その後、高圧洗浄などで施工面の汚れ、ゴミ、劣化した旧塗膜などを除去します。
- 下地調整
必要に応じて、ひび割れ補修、不陸調整(凹凸を平らにする)、脆弱部の除去・補修などを行います。
- プライマー塗布
下地と通気緩衝シートの密着性を確保するため、プライマーを均一に塗布します。
- 通気緩衝シート敷設
通気緩衝シートを下地に敷き込みます。シートの重ね部分や端末部分は、仕様に従って適切に処理します。
- 脱気筒の設置
設計された位置に、規定の方法で脱気筒を取り付けます。
- ウレタン防水材 1層目塗布
通気緩衝シートの上に、ウレタン防水材の1層目を均一な厚みで塗布します。
- ウレタン防水材 2層目塗布
1層目が硬化した後、2層目のウレタン防水材を塗り重ね、規定の防水層厚を確保します。
- トップコート塗布
ウレタン防水層が完全に硬化した後、紫外線などから保護するためのトップコートを塗布して完成です。
各工程での乾燥時間や施工条件(気温、湿度など)を守ることが、高品質な防水層を形成するために重要です。
まとめ:ウレタン防水 通気緩衝工法のポイント
ウレタン防水 通気緩衝工法は、建物の防水性能を長期的に維持するために有効な選択肢の一つです。最後に、この工法の重要なポイントをまとめます。
- 最大の特徴は「通気層」: 下地と防水層の間に通気緩衝シートを敷設し、下地からの湿気を脱気筒から外部へ逃がすことで、防水層の「ふくれ」を効果的に抑制します。
- 「ふくれ」抑制と下地追従性が主なメリット: 水分を含んだ下地や動きのある下地に対して高い適性を持ち、防水層の長期的な信頼性を向上させます。特に改修工事でその効果を発揮します。
- コストと工期は密着工法より増加: 専用部材の使用や工程の増加により、費用が高くなり、工期も長くなる傾向があります。
- 適材適所の選択が重要: 建物の状態(特に下地の水分状況や動き)、既存防水層の種類、予算、要求される性能などを総合的に考慮し、密着工法など他の工法と比較検討することが不可欠です。
- 施工品質が性能を左右する: シートの適切な敷設、脱気筒の確実な設置、規定の膜厚確保など、各工程を丁寧に行うことが、通気緩衝工法の性能を最大限に引き出す鍵となります。
ウレタン防水 通気緩衝工法は、適切な条件下で採用され、正しく施工されれば、建物の資産価値を守る上で非常に有効な防水工法です。防水工事を検討する際は、専門業者によく相談し、ご自身の建物に最適な方法を選択するようにしましょう。
修繕をご検討されてましたらお気軽にご相談ください!
☆☆工事担当者が現地にて詳しく調査させて頂きます。☆☆
現地調査、お見積りは無料にてさせて頂きます。
まずはメールにてお気軽にお問い合わせください。お待ちしております。