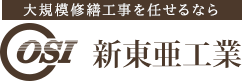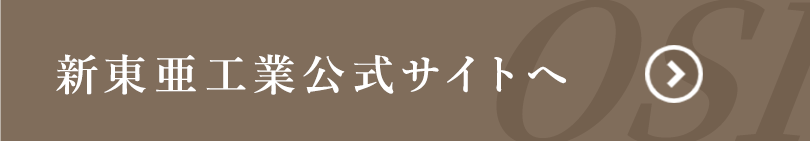木部塗装! 塗装-埼玉
2021/02/20
| ホコリや汚れなどは外壁と一緒に高圧洗浄で洗い流します。また、窓や格子など外壁塗装とは異なる塗装の部位箇所は、養生(ビニール、テープ)します。 |
| また、釘の出ているところは補修し、ペーパー目粗し・ケレンをしていき、塗面を平滑に仕上げます |
| もし、劣化してしまった既存塗膜の下地調整を行わないまま、上から新しく塗装をしても、下地からダメになってしまい、耐久性は期待できません。 |
| その後、下塗り塗装をしていきいます。古い塗膜は出来る限り除去し、同時に目粗しもします。仕上げが綺麗になるため、下塗りは厚めに塗り、しっかり吸い込ませます。 |
| 下塗り材には、上塗り塗料が密着しやすくなる「接着剤」としての効果があるので、塗装後、しっかり乾燥させて丈夫な下地を作っておくことが大切です。下塗りが十分に |
| 乾いたら上塗りを二回塗ります。上塗りは各メーカーごとに記載された稀釈率で塗装していきます。 |
| 下塗りとは違い、塗料を吸い込まないので艶も出て綺麗になります。基本的には外壁を塗った後の最後の仕上げ工程となります。このやり方で全て塗って仕上げていきます。 |
| 手遅れな木部に関しては補修が困難なので塗装以外の手段をお勧めします。そうならないよう塗装で済むように定期的なメンテナンスを心掛けてください。 |
修繕をご検討されてましたらお気軽にご相談ください!
☆☆工事担当者が現地にて詳しく調査させて頂きます。☆☆
現地調査、お見積りは無料にてさせて頂きます。
まずはメールにてお気軽にお問い合わせください。お待ちしております。