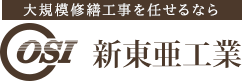シーリング材の種類とは!? 修繕-千葉
2021/10/08
【完全ガイド】シーリング材の種類を徹底解説!選び方から特徴・用途まで
シーリング材は、建物の気密性や防水性を高めるために欠かせない建築材料です。外壁の目地、サッシ周り、水回りなど、様々な箇所で使用されていますが、場所や目的に合わないシーリング材を選ぶと、早期の劣化や雨漏りの原因にもなりかねません。
この記事では、主要なシーリング材の種類とその特徴、適切な選び方、性能の違いについて、プロの視点から詳しく解説します。
主要なシーリング材の種類とその特徴
シーリング材には、主成分や特性によって様々な種類が存在します。現場の状況や求められる性能に応じて適切なタイプを選ぶためには、それぞれの特徴を正しく理解することが不可欠です。ここでは、建築現場でよく使用される代表的なシーリング材の種類と、その主な特徴について解説します。
シリコーン系シーリング材:
特徴
ケイ素樹脂を主成分とし、耐候性、耐水性、耐熱性、耐寒性に非常に優れています。紫外線や雨風に強く、長期間にわたって弾力性を維持します。多くの素材への密着性も良好ですが、塗装ができないタイプが多い点には注意が必要です。
主な用途:
ガラス周り、サッシ周り、キッチンや浴室などの水回り、ホーロー製品の目地など。特に耐候性や耐水性が求められる箇所に適しています。
メリット:
優れた耐候性・耐水性、幅広い温度範囲での使用が可能。
デメリット: ほとんどの種類で塗装ができない、一部のプラスチックを汚染する場合がある(オイルブリード)、埃が付着しやすい。
変成シリコーン系シーリング材:
特徴:
シリコーンの耐候性とポリウレタンの塗装性を併せ持つ、比較的新しいタイプのシーリング材です。幅広い下地への密着性に優れ、上から塗装を施すことが可能です。ノンブリードタイプ(可塑剤が移行しにくい)が多く、塗装面を汚染しにくいのも利点です。
主な用途:
一般建築物の内外装目地、サイディングの目地、ALCパネルの目地、サッシ周り、塗装が必要な箇所など。
メリット:
良好な耐候性、多くの種類で塗装が可能、幅広い下地への密着性、汚染が少ない(ノンブリードタイプ)。
デメリット: シリコーン系と比較すると耐候性がやや劣る場合がある、プライマーが必要な場合がある。
ポリウレタン系シーリング材:
特徴: 柔軟性と弾力性に富み、目地の動きへの追従性に優れています。硬化後はゴムのような弾力を持つため、動きの大きい目地に適しています。多くの種類で塗装が可能ですが、紫外線に弱いため、露出する箇所で使用する場合は上からの塗装が推奨されます。
主な用途:
ALCパネルやコンクリートの目地、サッシ周り(塗装仕上げ)、ひび割れの補修など。
- メリット: 優れた弾力性、目地への追従性、塗装が可能。
- デメリット: 紫外線に弱く、露出使用の場合は塗装が必要、シリコーン系や変成シリコーン系に比べて耐候性が劣る、プライマーが必要な場合が多い。
アクリル系シーリング材:
特徴: 湿った面にも施工が可能で、水性タイプが多く取り扱いが比較的容易です。硬化後は弾力性が少なく、硬くなる傾向があります。塗装は可能ですが、耐久性や耐候性は他のタイプに比べて劣ります。
主な用途: ALCパネルの目地(新築時)、内装の隙間充填、塗装下地処理など。動きの少ない箇所に適しています。
メリット:
湿潤面への施工が可能、水性タイプは扱いやすい、塗装が可能、比較的安価。
デメリット:
耐久性・耐候性が低い、硬化後の肉やせが大きい、動きの大きい目地には不向き。
これらのシーリング材は、使用箇所や目的に応じてさらに細分化された製品が存在します。例えば、防カビ剤入りのシリコーン系、低モジュラス(低弾性)タイプの変成シリコーン系など、特定の機能が付加されたものもあります。それぞれの特性を理解し、適切な種類を選定することが重要です。
シーリング材の選び方:用途と場所に応じた最適な選択
シーリング材を選ぶ際には、その基本的な性能を比較検討することが不可欠です。特に、耐候性、耐久性(弾力性・追従性)、塗装性、そして密着性は、シーリング材の寿命や仕上がりの品質に直結する重要な要素です。ここでは、主要なシーリング材の性能を比較し、選択の際の判断材料を提供します。
耐候性:
屋外で使用されるシーリング材にとって最も重要な性能の一つです。紫外線、温度変化、降雨などに対する耐久力を示します。
- シリコーン系:
非常に優れています。化学的に安定しており、紫外線やオゾンによる劣化が少なく、長期間にわたり性能を維持します。 - 変成シリコーン系:
シリコーン系にはやや劣るものの、屋外での使用に十分な耐候性を持ちます。 - ポリウレタン系:
劣ります。特に紫外線に弱く、暴露される環境では表面から劣化が進行するため、保護塗装が必要です。 - アクリル系:
低いです。耐候性は他のタイプに比べて劣るため、主に屋内や塗装で保護される箇所に使用されます。
耐久性(弾力性・目地追従性):
温度変化などによる部材の伸縮(ムーブメント)にどれだけ追従できるかを示す性能です。特に動きの大きい目地では重要になります。
- ポリウレタン系:ゴムのような強い弾力性を持ち、大きな動きにも追従できます。
- 変成シリコーン系: 低モジュラスタイプは特に動きへの追従性に優れています。
- シリコーン系: 種類によって弾力性の度合い(モジュラス)が異なります。適切なタイプを選ぶ必要があります。
- アクリル系: 硬化後は比較的硬くなり、大きな動きには追従しにくいため、ひび割れが発生しやすいです。
塗装性:
シーリング材の上から塗料を塗ることができるかどうかの性能です。外壁など、意匠性が求められる箇所で重要になります。
変成シリコーン系、ポリウレタン系、アクリル系: 良好です。ほとんどの種類で上から塗装が可能です。ただし、ポリウレタン系は塗装が推奨されます。
密着性:
様々な下地(被着体)にどれだけ強く接着するかを示す性能です。
- 変成シリコーン系: 非常に広範囲の素材に対して良好な密着性を示します。プライマーなしでも対応できる場合が多いです。
- シリコーン系: ガラスやタイル、ホーローなどには良好ですが、一部のプラスチックや塗膜には適さない場合があります。
- ポリウレタン系: コンクリートや金属には良好ですが、多くの場合プライマーが必要です。
- アクリル系: 多孔質な素材(モルタル、ALCなど)には比較的良好ですが、非多孔質素材への密着性は劣ります。
汚染性(ブリード):
シーリング材に含まれる可塑剤などが周辺の部材に移行し、汚染(黒ずみなど)を引き起こす現象です。
- 変成シリコーン系: ノンブリードタイプが多く、汚染性は低いです。
- シリコーン系: 種類によってはオイルブリードを起こすことがあります。
- ポリウレタン系: 種類によってはブリード汚染を起こす可能性があります。
- アクリル系: ブリードは少ないですが、硬化収縮による隙間が生じやすいです。
これらの性能を総合的に比較し、使用箇所、目的、要求される品質レベルに応じて、最適なシーリング材を選定することが重要です。
まとめ:最適なシーリング材を選んで建物の長寿命化を
シーリング材は、建物の目地や隙間を埋めることで、雨水の浸入を防ぎ、気密性を高め、建材を保護するという重要な役割を担っています。その種類は多岐にわたり、それぞれ主成分や特性が異なります。主な種類として、耐候性に優れる「シリコーン系」、塗装可能でバランスの取れた「変成シリコーン系」、弾力性が高い「ポリウレタン系」、扱いやすい「アクリル系」などが挙げられます。
最適なシーリング材を選ぶためには、まず使用する場所が屋内か屋外か、紫外線や雨水の影響をどれだけ受けるかといった「使用環境」を考慮する必要があります。次に、接着する相手となる「被着体の種類」を確認し、相性の良いシーリング材を選びます。さらに、温度変化などで部材がどれだけ動くか(ムーブメント)を考慮し、適切な「弾力性(目地追従性)」を持つタイプを選定します。シーリング箇所の上から「塗装」を行うかどうかも、選択を左右する重要なポイントです。水回りなどでは、「耐水性」や「防カビ性」も考慮に入れる必要があります。
選択のポイント:
- 使用場所(屋外/屋内)と耐候性の要件
- 接着する素材(被着体)との相性
- 目地の動きの大きさと必要な弾力性
- 塗装の有無
- 耐水性・防カビ性の必要性
これらの要素を総合的に判断し、各シーリング材のメリット・デメリットを理解した上で、最も適した製品を選択することが、シーリング箇所の性能を長期間維持し、ひいては建物全体の耐久性を高めることにつながります。適切なシーリング材を選び、正しい施工を行うことで、大切な建物を雨漏りや劣化から守り、快適な状態を長く保ちましょう。
新東亜工業は、総合工事店としてほぼ全ての工事を自社職人による一貫施工で対応していますので、施工費用に上乗せされる余分な下請け費を全てカットできます。規模が大きく、費用面での負担が大きい修繕工事だからこそ中間マージンゼロの効果は大きく、見積価格に大きな違いを生み出します。
自社施工のメリットは費用面だけではなく、施工スピードや品質面にも表れます。幾つもの施工会社が関わっている場合には、現場からの情報が管理者やそれぞれの会社の職長、職人を経てやり取りされるため、解決までに時間がかかるばかりか、正確に伝わらないということが起こり得ます。そのようなリスクを避けるために施工を全て内製化しており、職人同士のしっかりとした連携体制によって、新たに生じる問題や変更点、お客様からのご要望などがスムーズ且つ正確に伝達されます。
修繕をご検討されてましたらお気軽にご相談ください!
☆☆工事担当者が現地にて詳しく調査させて頂きます。☆☆
現地調査、お見積りは無料にてさせて頂きます。
まずはメールにてお気軽にお問い合わせください。お待ちしております。