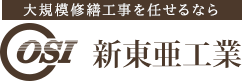アスファルトとは? 屋上-防水
2021/04/24
建物の寿命を左右する防水工事。中でも「アスファルト防水」は、耐久性と信頼性の高さから多くの建物で採用されています。本記事では、「アスファルト防水とは何か?」をテーマに、その種類やメリット、施工方法、メンテナンスまで詳しく解説します。初めての方でも理解しやすいよう、基礎から丁寧にご紹介します。
アスファルト防水の基本
アスファルト防水とは、アスファルトを主成分とした材料を使い、建物の屋上や屋根、地下部分などに防水層を形成する工法です。アスファルトは水を通さない性質があるため、長期間にわたって雨水や湿気から建物を守ることができます。
この防水工法は、特にビルやマンションなど大型建築物の屋上で多く使われており、厚い防水層を形成することで、高い耐久性と防水性能を実現しています。
アスファルト防水は、建物の耐久性を維持するために非常に重要な防水技術です。この工法には主に「トーチ工法(シート防水)」と「熱工法(熱アスファルト)」の2つがあり、それぞれ特徴があります。ここでは、より詳細にアスファルト防水の種類や特性、メリット・デメリットを解説していきます。
アスファルト防水の種類と特徴
アスファルト防水は、古くから使用されている信頼性の高い工法です。特に耐久性と防水性能に優れ、長期的なメンテナンスコストを削減できる利点があります。以下に、2つの主要な工法について詳しく説明します。
1. トーチ工法(シート防水)
この工法では、アスファルトを含んだ防水シートをバーナーで加熱し、施工面に密着させます。短時間で均一な防水層を形成できるため、多くの現場で採用されている工法です。
メリット:
施工のスピードが速い バーナーを使用して迅速にシートを密着させるため、作業時間が短縮されます。
品質が安定しやすい 事前に製造されたシートを使用するため、品質のばらつきが少なくなります。
デメリット:
バーナー使用による火災リスク 作業中に火を使うため、周囲への火災対策が不可欠です。
使用できる環境が限られる 風の強い屋外や、高温多湿の環境では施工が難しい場合があります。
2. 熱工法(熱アスファルト)
加熱したアスファルトを現場で流し込み、数層にわたって塗り広げる伝統的な防水工法です。屋上や建築基礎部分の防水に適しています。
メリット:
厚みのある防水層が形成できる 流し込み方式のため、防水層を重ねることでより高い耐久性を確保できます。
長寿命な防水性能 適切な施工が行われれば、20年以上の耐久性を持つ場合もあります。
デメリット:
施工に時間と手間がかかる シート防水に比べて工程が多いため、施工期間が長くなる傾向があります。
煙や臭いが発生しやすい アスファルトを加熱することで煙や特有の臭いが出るため、周囲への配慮が必要です。
アスファルト防水のメリットとデメリット
【メリット】
・高い耐久性
施工後の防水層は非常に強固であり、長期間にわたって建物を水の侵入から守ります。
適切なメンテナンスを行えば、10〜20年くらいの耐用年数を確保できます。
・優れた防水性能
厚い防水層が形成されるため、雨水や湿気から建物を効果的に保護できます。
特に屋上や地下構造物の防水に適しているため、多くの建築プロジェクトで採用されています。
・歴史ある信頼性
何十年にもわたる施工実績があり、安全性と効果が確立された防水技術です。
さまざまな建築現場で採用され続けており、信頼性が高い工法といえます。
【デメリット】
・施工に専門技術が必要
施工には経験豊富な技術者が必要であり、DIYには向いていません。
施工不良が発生すると、防水効果が十分に得られない可能性があります。
・火気使用による安全面の配慮
トーチ工法の場合、バーナーを使用するため安全対策が必須です。
作業環境によっては火災リスクを考慮する必要があります。
・重量がある
アスファルト防水は比較的重量があるため、軽量な屋根材との相性を事前に確認する必要があります。
建物の構造に適した防水工法を、選ぶことが重要です。
アスファルト防水は、耐久性と防水性能に優れた信頼性の高い工法ですが、施工には専門技術が必要であり、火気の使用に注意が必要です。目的や施工環境に応じて「トーチ工法」と「熱工法」のどちらを選ぶかを慎重に検討し、最適な防水対策を講じることが大切です。
アスファルト防水の施工方法
アスファルト防水の施工は、建物の防水性能を確保し、長期間にわたって雨水の侵入を防ぐために不可欠な工程です。適切な施工を行うことで、防水層の耐久性を最大限に引き出し、メンテナンスの手間を軽減できます。
ステップ1:
下地処理
まずは施工面を清掃し、凹凸をなくして防水層をしっかり密着させる準備をします。
ステップ2:
プライマー塗布
防水材をしっかり密着させるため、プライマー(接着剤)を塗布します。
ステップ3:
アスファルト塗布またはシート貼り
熱工法では溶かしたアスファルトを流し込み、トーチ工法では防水シートをバーナーで接着します。
ステップ4:
重ね張り(複層)
防水性能を高めるため、2〜3層にわたって重ねて施工します。
ステップ5:
トップコート仕上げ
紫外線から防水層を守るため、保護塗料を塗って仕上げます。
アスファルト防水のメンテナンスと寿命
アスファルト防水の寿命は一般的に10〜20年程度ですが、適切なメンテナンスを行うことで、さらに長持ちさせることが可能です。
上記のように、下地処理からトップコート仕上げまでの各ステップを確実に実施することで、高い防水性能と耐久性を確保できます。
メンテナンスポイント
アスファルト防水の性能を長く維持するためには、適切なメンテナンスが欠かせません。定期的な点検や軽度の補修を行うことで、大規模な修繕を避けることが可能となり、建物の防水性能を安定して確保できます。
1. 定期点検の実施
アスファルト防水は、高い耐久性を誇るものの、長期間にわたって外部環境の影響を受けるため、定期的な点検が不可欠です。推奨される点検頻度は年に1〜2回くらいであり、特に梅雨前や冬季の前後に実施すると、劣化を早期に発見しやすくなります。
【点検時の確認ポイント】
ひび割れの有無:
防水層に亀裂が入っている場合、水の浸入リスクが高まります。
膨れや剥がれ:
防水層が浮いてしまっている箇所や剥がれが見られる場合は、補修が必要です。
排水設備の状態:
屋上のドレンや排水口が詰まっていないか確認し、適切に掃除することで水の滞留を防ぎます。
外部からのダメージ:
施工部分に飛来物や過度な歩行による損傷がないかをチェックします。
2. ひび割れ・膨れ・剥がれの点検と対策
防水層の劣化が進むと、ひび割れや剥がれが発生することがあります。これらの症状は、放置すると雨水の浸入を引き起こし、防水性能の低下だけでなく建物の躯体にも悪影響を及ぼす可能性があります。
【劣化症状ごとの対処方法】
小さなひび割れ:
防水材の補修材を用いて部分的に修復可能。
膨れが見られる場合:
内部に湿気が溜まっている可能性があるため、施工業者に相談し適切な処理を実施。
剥がれが生じた場合:
防水層の一部張り替えを検討し、早めに補修を行う。
3. 補修のタイミングと方法
防水層の劣化が進行しすぎると、部分的な補修では対応しきれず、大掛かりな修繕が必要になることがあります。そのため、早めの補修を心掛けることが重要です。
【補修が必要になるケース】
・防水層の劣化が進み、防水性能が低下した場合
・排水の機能が悪くなり、水溜まりができる状態
・建物内部に漏水の兆候がある場合(天井や壁のシミなど)
【補修方法】
・小規模な劣化であれば、防水材を用いた部分補修
・劣化が進んでいる場合は、既存の防水層を撤去し、新たな防水シートを施工
・必要に応じてトップコートの再塗布を行い、防水層の保護を強化
4. トップコートの再塗布による長寿命化
アスファルト防水の劣化を遅らせるために、トップコートの再塗布が有効です。トップコートは防水層の表面を保護し、紫外線や雨風による劣化を抑える役割を果たします。
【トップコート再塗布のメリット】
防水層の劣化を抑制:
定期的に塗布することで、防水層の寿命を延ばす。
耐候性の向上:
紫外線や温度変化による影響を軽減し、防水層の持続性を確保。
メンテナンスコストの削減:軽度のメンテナンスを行うことで、大規模な修繕を避けることが可能。
【塗布時期の目安】
・施工後約5〜7年程で最初の再塗布を検討
・防水層の表面に色褪せや細かいひびが見られた場合は再塗布を推奨
アスファルト防水の性能を長持ちさせるには、定期点検・軽度の補修・トップコートの再塗布の3つを組み合わせたメンテナンスが重要です。特に、劣化の初期段階で適切な処置を行うことで、大規模な修繕を回避できるため、建物の維持管理コストを削減することができます。
まとめ
アスファルト防水の性能を長期間維持するためには、定期的な点検と適切なメンテナンスが欠かせません。特に定期的な点検を実施し、ひび割れや膨れ・剥がれを早期に発見することが重要です。これらの症状は防水性能の低下につながるため、小規模な補修を迅速に行うことで、大掛かりな修繕を回避できます。また、トップコートの再塗布によって、防水層の劣化を遅らせ、耐候性を向上させることが可能です。防水層の維持管理は、施工後5〜7年を目安にトップコートの再塗布を検討し、表面の変化に注意を払いながら適切な対策を講じることで、長期的な防水機能を確保できます。建物の保護とメンテナンスコストの削減を図るために、これらのポイントを実践することが大切です。
修繕をご検討されてましたらお気軽にご相談ください!
☆☆工事担当者が現地にて詳しく調査させて頂きます。☆☆
現地調査、お見積りは無料にてさせて頂きます。
まずはメールにてお気軽にお問い合わせください。お待ちしております。