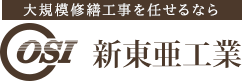下地補修”塗膜剥離” 東京
2021/04/06
建物の美観や耐久性を維持するためには、定期的な塗装メンテナンスが不可欠です。しかし、単に新しい塗料を塗り重ねるだけでは、本来の性能を発揮できないばかりか、早期の不具合を引き起こす可能性もあります。特に、既存の塗膜が劣化している場合には、「塗膜剥離」とそれに続く「下地補修」が極めて重要な工程となります。
この記事では、なぜ塗膜剥離が必要なのか、どのような方法があるのか、そして剥離後の下地補修がどのように行われるのかについて、その重要性と具体的な手順を解説します。
塗膜剥離が必要となる状況とその目的
建物の塗装改修において、既存の塗膜を剥がす「塗膜剥離」は、必ずしも全てのケースで必要となるわけではありません。しかし、特定の状況下では、新しい塗膜の性能を最大限に引き出し、長期的な保護機能を持続させるために不可欠な工程となります。塗膜剥離が必要となる主な状況と、その目的を理解することは、適切な改修計画を立てる上で非常に重要です。安易に塗り重ねるのではなく、下地の状態を見極めて判断することが求められます。
塗膜剥離が推奨される、あるいは必須となる具体的な状況は以下の通りです。
旧塗膜の著しい劣化:
塗膜に膨れ、ひび割れ、剥がれなどが広範囲に発生している場合。これらの上に新しい塗料を塗っても、旧塗膜ごと剥がれてしまうリスクが高くなります。
塗膜の過度の厚塗り:
過去の改修で何度も塗り重ねられ、塗膜が異常に厚くなっている場合。厚すぎる塗膜は、割れや剥がれのリスクを高めるだけでなく、建物の意匠性を損なうこともあります。
新旧塗料の相性問題:
既存の塗料と新しく塗る塗料の相性が悪い場合。例えば、特定の種類の旧塗膜の上に強溶剤系の塗料を塗ると、旧塗膜が侵されて縮みや溶解を引き起こすことがあります。
下地の状態確認と補修の必要性:
塗膜の下にあるコンクリートやモルタルなどの下地に、ひび割れや劣化が疑われる場合。塗膜を剥がして下地の状態を正確に把握し、適切な補修を行う必要があります。
特定の機能性塗料の塗布:
特殊な機能を持つ塗料(例:高耐久性フッ素樹脂塗料、断熱塗料など)を塗る場合、その性能を最大限に発揮させるために、清浄で健全な下地が要求されることが多く、旧塗膜の完全な除去が推奨されることがあります。
塗膜剥離を行う主な目的は、新しい塗膜の密着性を確保することにあります。劣化した旧塗膜や汚れ、異物などを除去し、健全で清浄な下地を作り出すことで、新しい塗料がしっかりと食いつき、本来の耐久性や保護性能を発揮できるようになります。
また、下地に隠れた問題を可視化し、適切な補修を施すことで、建物の構造的な安全性を高めるという目的もあります。
代表的な塗膜剥離の方法とそれぞれの特徴
塗膜剥離が必要と判断された場合、現場の状況や既存塗膜の種類、下地材の種類、作業環境、法規制など、様々な要因を考慮して最適な剥離方法を選択する必要があります。それぞれの手法にはメリット・デメリットがあり、特性を理解した上で選定することが重要です。
代表的な塗膜剥離の方法には、以下のようなものがあります。
物理的剥離工法:
- 工具によるケレン
スクレーパー、皮スキ、ワイヤーブラシなどの手工具や、ディスクサンダー、電動ケレン機などの電動工具を用いて物理的に塗膜を削り取る方法です。
比較的小規模な面積や、部分的な剥離に適しています。粉塵が発生しやすいため、集塵装置付きの工具を使用したり、湿式で行ったりするなどの対策が必要です。下地を傷つけないよう、慎重な作業が求められます。コストは比較的抑えられますが、労力がかかります。 - 高圧・超高圧水洗浄(ウォータージェット)
水の圧力だけで塗膜を除去する方法です。圧力を調整することで、塗膜の除去レベルを変えることができます。
粉塵の発生が少ない(湿式工法)のが大きな利点です。
ただし、強固に密着した塗膜の除去は難しい場合があり、大量の汚水が発生するため、適切な排水処理が必要です。騒音も比較的大きくなります。
ブラスト工法:
研磨材(砂、グリット、ドライアイスなど)を圧縮空気や水と共に高速で吹き付け、塗膜を除去する方法です。
強力な剥離能力を持ち、広範囲の塗膜除去や錆落としに非常に効果的です。下地に凹凸(アンカーパターン)を形成し、新しい塗膜の付着性を向上させる効果もあります。
一方で、大量の粉塵(ドライブラストの場合)や廃棄物が発生するため、大規模な養生や集塵設備、廃棄物処理が必要となり、コストが高くなる傾向があります。下地へのダメージも考慮が必要です。
化学的剥離工法:
塗膜を化学的に溶解または軟化させる剥離剤を塗布し、浮き上がった塗膜をスクレーパーなどで除去する方法です。
複雑な形状の部分や、物理的な方法では除去が難しい塗膜に有効です。粉塵の発生が少ないですが、使用する剥離剤によっては強い臭いや有害性を持つものがあるため、換気や保護具の着用など、安全管理が重要です。
また、剥離剤の種類によっては下地材に影響を与える可能性があり、廃液の適切な処理も必要です。
これらの工法以外にも、加熱して塗膜を軟化させて剥がす加熱剥離工法などもあります。最適な工法の選択は、塗膜の種類(水性、油性、合成樹脂系など)、膜厚、下地材の種類(コンクリート、金属、木材など)、作業環境(周辺への影響、騒音・粉塵規制)、予算、工期などを総合的に評価して決定されます。
塗膜剥離後の下地補修:その必要性と主な補修箇所
塗膜剥離は、あくまで健全な下地を作り出すための前処理であり、それ自体が目的ではありません。多くの場合、劣化した塗膜を剥がしてみると、その下に隠れていた様々な下地の不具合が露わになります。
これらの不具合を放置したまま新しい塗料を塗布しても、塗膜の性能が十分に発揮されず、早期の劣化や剥がれ、さらには建物の構造的な問題につながる可能性があります。
したがって、塗膜剥離後には、必ず下地の状態を詳細に点検し、必要な補修を行うことが極めて重要です。
下地補修が必要となる主な理由は以下の通りです。
新設塗膜の性能確保:
健全で平滑な下地は、新しい塗膜が均一に密着するための基盤となります。ひび割れや欠損、凹凸があると、塗膜の密着不良や早期の割れ、剥がれの原因となります。
建物の保護機能回復:
下地のひび割れや欠損は、雨水の浸入経路となり、内部の鉄筋腐食やコンクリートの中性化を促進します。これらを補修することで、建物の防水性や耐久性を回復・維持します。
美観の向上:
下地の凹凸や不陸は、仕上げの塗膜にも影響し、見た目の美しさを損ないます。平滑に補修することで、美しい仕上がりを実現します。
構造的な安定性の維持:
大きなひび割れやコンクリートの欠損などは、建物の構造的な強度に影響を与える可能性があります。適切な補修により、安全性を確保します。
塗膜剥離後に発見され、補修が必要となる主な下地の不具合箇所には、以下のようなものがあります。(主にコンクリート・モルタル下地の場合)
ひび割れ(クラック):
乾燥収縮、温度変化、構造的な動きなどが原因で発生します。幅や深さ、動きの有無によって適切な補修方法が異なります。微細なヘアークラックから構造的なひび割れまで様々です。
欠損・爆裂:
内部鉄筋の腐食・膨張によってコンクリートが押し出されて欠け落ちる現象(爆裂)や、物理的な衝撃による欠損です。鉄筋の防錆処理と断面修復が必要です。
浮き:
下地コンクリートと仕上げモルタル層の間などが剥離し、浮いている状態です。打診などで確認し、注入材による固定や、除去・再施工が必要です。
ジャンカ・豆板:
コンクリート打設時の施工不良により、骨材が分離してできた空隙の多い部分です。強度や水密性が低いため、除去してモルタルなどで充填します。
不陸・凹凸:
表面が平滑でなく、凹凸がある状態です。パテ材やモルタルで平滑に調整します。
これらの不具合を的確に診断し、それぞれの状態に適した補修を行うことが、塗装改修工事全体の品質を左右する重要な鍵となります。
下地補修の主な工法と適切な選択
塗膜剥離後に露わになった下地の不具合に対しては、その種類、程度、原因、そして要求される品質に応じて様々な補修工法が用いられます。適切な工法を選択し、確実に施工することが、下地の健全性を回復させ、最終的な塗装仕上げの品質と耐久性を保証するために不可欠です。
工法の選択を誤ると、補修箇所が再劣化したり、期待した効果が得られなかったりする可能性があります。
主な下地補修の工法と、その適用対象、特徴は以下の通りです。
ひび割れ補修工法:
- Uカットシール材充填工法
ひび割れに沿ってU字型またはV字型に溝(カット)を設け、清掃後、プライマーを塗布し、シーリング材や可とう性エポキシ樹脂などを充填する工法です。
比較的幅の広いひび割れ(0.3mm以上程度)や、動きのあるひび割れに適しています。水の浸入防止効果が高いですが、補修跡が目立ちやすい場合があります。 - 低圧注入工法(エポキシ樹脂注入など)
微細なひび割れ(0.1mm~1.0mm程度)に対して、専用の注入器具を用いて低圧でエポキシ樹脂などの注入材を注入し、ひび割れを閉塞・一体化させる工法です。
ひび割れ内部まで注入材が浸透し、強度回復や水密性の向上が期待できます。構造的な一体化を目的とする場合に有効です。補修跡は比較的目立ちにくいです。 - フィラーすり込み
ごく微細なひび割れ(ヘアークラックなど、幅0.2mm以下程度)に対して、セメント系やアクリル系のフィラー(微粒子充填材)を刷毛やヘラで擦り込むようにして埋める簡易的な工法です。
施工が比較的容易で、軽微なひび割れの閉塞や下地調整に適しています。構造的な強度回復は期待できません。
欠損部・断面修復工法:
- ポリマーセメントモルタル充填
鉄筋の防錆処理(ケレン、防錆材塗布)を行った後、接着性を高めるプライマーを塗布し、ポリマー(合成樹脂)を配合したセメントモルタルで欠損部を埋め戻す工法です。
コンクリートとの付着性、耐久性、防水性に優れており、一般的な欠損部補修に広く用いられます。左官コテで整形します。
- エポキシ樹脂モルタル充填
エポキシ樹脂を主成分としたモルタルで欠損部を充填する工法です。
高強度、高接着性、耐薬品性に優れています。特に高い強度が要求される箇所や、早期の強度発現が必要な場合に適しています。
浮き部補修工法:
エポキシ樹脂注入
浮いている箇所に注入孔を開け、低圧でエポキシ樹脂を注入して、浮き層を下地に固定する工法です。
既存の仕上げ層を撤去せずに補修できる場合がありますが、注入範囲や効果の確認が重要です。
これらの工法を選択する際には、劣化の状況(ひび割れの幅・深さ・動き、欠損の大きさ・深さ)、下地の種類、部位(壁、床、天井など)、環境条件(屋内、屋外、水掛かり)、そして仕上げ材の種類などを総合的に考慮する必要があります。
まとめ:塗膜剥離と下地補修を成功させるポイント
建物の美観と耐久性を長期にわたって維持するための塗装改修において、塗膜剥離とそれに続く下地補修は、最終的な仕上がり品質と建物保護性能を決定づける非常に重要な工程です。これらの工程を適切に行うことが、改修工事の成功の鍵となります。
単に古い塗膜を剥がして新しい塗料を塗るのではなく、一連のプロセスとして捉え、各ステップで注意深く作業を進める必要があります。成功のためには、
まず事前の綿密な調査・診断が不可欠です。既存塗膜や下地の状態を正確に把握した上で、現場の状況や要求品質に応じた適切な工法の選定を行います。この際、安全性や環境への配慮も忘れてはなりません。
次に、選択した工法で確実な塗膜剥離を実施し、劣化した層や付着阻害要因を徹底的に除去します。剥離後には、下地の状態を再度徹底的に確認し、塗膜に隠れていたひび割れや欠損などの不具合を見逃さないようにすることが重要です。発見された不具合に対しては、その種類と程度に応じた最適な材料と工法を用いて的確な下地補修を行い、補修材の性能が十分に発揮されるよう乾燥・硬化時間も遵守します。
さらに、丁寧な下地調整によって補修箇所と既存下地との段差をなくし、表面全体を平滑にし、塗装直前には清浄な塗装面を確保することで、新しい塗料の密着性を最大限に高めます。これらの剥離から補修、そして塗装に至る各工程がスムーズに進むよう、工程間の連携を意識した管理も成功には欠かせません。
これらのポイントを確実に実行することで、塗膜剥離と下地補修は、単なる前処理ではなく、建物の資産価値を高め、長期にわたってその機能を維持するための重要な投資となります。手間を惜しまず、基本に忠実な作業を行うことが、最終的な成功につながります。
修繕をご検討されてましたらお気軽にご相談ください!
☆☆工事担当者が現地にて詳しく調査させて頂きます。☆☆
現地調査、お見積りは無料にてさせて頂きます。
まずはメールにてお気軽にお問い合わせください。お待ちしております。