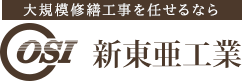下地補修”浮き部” 修繕工事-神奈川
2021/04/02
下地補修における『浮き部』とは?原因から補修方法まで徹底解説
建物の外壁や内壁、床などの塗装や仕上げ材の下地には、時として「浮き」と呼ばれる不具合が発生することがあります。この「浮き部」は、見た目の問題だけでなく、建物の耐久性にも影響を及ぼす可能性があるため、早期発見と適切な補修が重要です。
この記事では、下地補修における「浮き部」とは何か、その発生原因、放置するリスク、そして具体的な補修方法について、分かりやすく解説します。
下地に「浮き部」が発生する主な原因
下地補修が必要となる「浮き部」とは、塗装膜やモルタル、タイルなどの仕上げ材が、その下地コンクリートや旧塗膜などから剥離し、部分的に浮き上がっている状態を指します。
指で押すとペコペコしたり、打診検査で軽い音がしたりすることで発見できます。
この浮き部が発生する原因は一つではなく、複数の要因が絡み合っていることも少なくありません。主な原因を理解することで、予防策や適切な補修方法の選択に繋がります。
代表的な発生原因は以下の通りです。
経年劣化:
建物は常に紫外線、雨風、温度変化に晒されています。これらの外的要因により、下地材や仕上げ材が徐々に劣化し、付着力が低下することで浮きが発生します。特に、防水機能が低下すると、水の浸入を招き、浮きを助長します。
施工時の不備:
新築時や前回の補修時の施工に問題があった場合も、浮きの原因となります。
- 下地処理不足
下地の清掃が不十分でホコリや油分が残っていたり、適切な乾燥時間をおかずに次の工程に進んだりすると、仕上げ材がうまく密着しません。 - 材料の選定ミス・配合不良
下地と仕上げ材の相性が悪い材料を選んだり、モルタルなどの材料の配合比率を間違えたりすると、付着強度が不足し、浮きや剥離を引き起こします。
水分・湿気の影響:
壁内部への雨水の浸入や、結露などによって下地が水分を含むと、材料の膨張・収縮を引き起こしたり、接着力を弱めたりして浮きが発生します。特に、漏水箇所周辺や湿気の多い場所で発生しやすい傾向があります。
構造的な要因:
建物の振動や、地震などによる構造体の動きが、下地と仕上げ材との間にズレを生じさせ、浮きやひび割れの原因となることもあります。
これらの原因を特定することは、再発防止のためにも重要です。浮き部を発見したら、その範囲だけでなく、周辺の状況や建物の状態も合わせて確認することが求められます。
浮き部を放置するリスクと下地補修の重要性
下地の浮き部は、初期段階では小さな範囲であっても、放置することで様々な問題を引き起こす可能性があります。見た目の問題だけでなく、建物の安全性や資産価値にも関わるため、早期に発見し、適切な下地補修を行うことが極めて重要です。
浮き部を放置した場合に考えられる主なリスクは以下の通りです。
仕上げ材の剥落リスク:
浮いている状態は、仕上げ材が下地から剥がれかかっている状態です。放置すると、地震や強風、振動などをきっかけに、塗装膜やモルタル、タイルなどが突然剥落する危険性があります。特に外壁の場合、剥落した部材が通行人や下の階に落下し、重大な事故につながる恐れがあります。
雨漏りの発生・拡大:
浮き部やそれに伴うひび割れは、雨水の浸入口となります。壁内部に水が浸入すると、構造材である鉄筋の腐食や木材の腐朽を引き起こし、建物の耐久性を著しく低下させます。また、室内に雨漏りが発生し、内装材の汚損やカビの発生原因にもなります。
劣化範囲の拡大と補修費用の増大:
浮き部から浸入した水分は、周辺の下地にも影響を及ぼし、浮きや劣化の範囲を拡大させます。初期段階で補修すれば部分的な処置で済んだものが、放置することで広範囲の下地交換や大規模な補修が必要となり、結果的に補修費用が高額になるケースが多くあります。
建物の美観低下と資産価値の減少:
壁面に浮きや剥がれがあると、建物の見た目が悪くなります。美観の低下は、居住者の満足度を下げるだけでなく、賃貸物件の場合は入居率の低下、売買物件の場合は資産価値の減少に直結します。
これらのリスクを回避するためには、定期的な点検によって浮き部を早期に発見し、速やかに適切な下地補修を実施することが不可欠です。下地補修は、単に見た目を整えるだけでなく、建物の安全性、耐久性、資産価値を守るための重要なメンテナンス作業と言えます。
下地補修における浮き部の具体的な補修方法
下地補修における浮き部の補修方法は、浮きの範囲、下地の種類、仕上げ材の種類、そして劣化の程度によって異なります。
ここでは、一般的なモルタル外壁やコンクリート下地における浮き部の補修手順と、代表的な工法について解説します。適切な手順と工法を選択することが、確実な補修と再発防止に繋がります。
基本的な補修手順:
- 調査・マーキング
打診棒などを用いて、浮いている範囲を正確に特定します。浮いている箇所だけでなく、その周辺も念入りに調査し、補修範囲をマーキングします。
- 浮き部・脆弱部の除去
マーキングした範囲の浮いている仕上げ材(塗装膜、モルタルなど)や、付着力の弱い脆弱な部分を、ハンマー、ケレン棒、ディスクサンダーなどを使って丁寧に取り除きます。健全な下地面が露出するまで除去することが重要です。
- 清掃
除去作業で発生した粉塵や破片を、ワイヤーブラシや高圧洗浄機、ブロワーなどを使って徹底的に清掃します。下地に汚れが残っていると、補修材の付着不良の原因となります。
- 下地調整(吸水調整・プライマー塗布)
露出した下地面に、適切なプライマーやシーラーを塗布します。これにより、下地の吸い込みを調整し、次に施工する補修材との密着性を高めます。下地の種類や状態に応じたプライマー選定が重要です。
- 補修材の充填・成形
下地の欠損部や不陸(凹凸)を、ポリマーセメントモルタルやエポキシ樹脂モルタルなどの補修材で埋めます。一度に厚付けせず、必要に応じて複数回に分けて充填し、コテなどを使って平滑に成形します。
- 仕上げ
補修材が完全に硬化・乾燥した後、周辺の既存仕上げ材に合わせて、塗装や左官仕上げなどを行います。模様や色調を合わせることで、補修箇所が目立たないように仕上げます。
代表的な補修工法:
- エポキシ樹脂注入工法
比較的軽微な浮きや、仕上げ材を残したまま補修する場合に用いられます。浮き部に小さな穴を開け、そこから低粘度のエポキシ樹脂を注入し、下地と仕上げ材を再接着させる工法です。仕上げ材の撤去が不要なため、工期短縮や廃材削減に繋がります。 - ポリマーセメントモルタル充填工法
浮き部を除去した後の欠損部を埋める際に一般的に用いられます。セメントに合成樹脂(ポリマー)を混入した材料で、高い付着力と耐久性を持ちます。様々な厚みに対応可能です。
どの工法を選択するかは、専門業者による診断に基づいて決定することが望ましいです。
まとめ:下地補修で浮き部を見つけたら早めの対処を
この記事では、下地補修における「浮き部」について、その発生原因、放置した場合のリスク、そして具体的な補修方法を解説しました。下地の浮きは、単なる見た目の問題ではなく、建物の構造的な安全性や耐久性、さらには資産価値にも影響を及ぼす重要なサインです。
- 浮きの主な原因: 経年劣化、施工時の不備(下地処理不足、材料選定ミス)、水分・湿気の影響、構造的な要因などが挙げられます。
- 放置するリスク: 仕上げ材の剥落事故、雨漏りの発生・拡大、劣化範囲の拡大による補修費用の増大、建物の美観低下と資産価値の減少など、深刻な問題につながる可能性があります。
- 補修の重要性: 早期に適切な下地補修を行うことで、これらのリスクを回避し、建物の安全性と耐久性を維持することができます。
- 具体的な補修方法: 浮き部の調査・除去、清掃、下地調整、補修材の充填、仕上げといった手順で進められ、状況に応じてエポキシ樹脂注入工法などが選択されます。
建物の外壁や内壁、床などに浮きや剥がれ、ひび割れなどの異常を発見した場合は、決して軽視せず、早めに専門業者に相談することをおすすめします。専門家による正確な診断と適切な補修計画に基づき、必要な措置を講じることが、建物を長持ちさせるための鍵となります。定期的な点検とメンテナンスを心がけ、大切な建物を良好な状態に保ちましょう。
修繕をご検討されてましたらお気軽にご相談ください!
☆☆工事担当者が現地にて詳しく調査させて頂きます。☆☆
現地調査、お見積りは無料にてさせて頂きます。
まずはメールにてお気軽にお問い合わせください。お待ちしております。