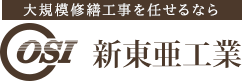シーリング工事とは!?
2020/12/17


シーリング工事とは?建物の寿命を延ばす防水・気密工事の基礎知識
建物の寿命を長く保ち、快適な室内環境を維持するために欠かせないのが「シーリング工事」です。普段あまり意識しないかもしれませんが、「一体どんな工事なの?」「なぜ大切なの?」と感じる方もいるかもしれません。
この記事では、シーリング工事の基本的な疑問から、その目的、種類、そして建物の維持においていかに重要な役割を果たしているのかまでを、プロの視点から分かりやすく解説します。
建物を守る縁の下の力持ち:シーリング工事の目的と役割
シーリング工事は、建物の様々な部材同士の隙間を埋めることで、雨水や空気の侵入を防ぐ重要な役割を担っています。建物は、外壁材やサッシ、屋根材など、多くの部材が組み合わさってできており、これらの部材の間にはわずかな隙間が生じます。この隙間をそのままにしておくと、雨水が浸入して建物の内部を腐食させたり、室内の空気が外部に漏れて冷暖房効率が悪くなったりする原因になります。
シーリング材と呼ばれる充填材を隙間に充填することで、これらの問題を未然に防ぐのがシーリング工事の主な目的です。具体的には、以下のような役割を果たしています。
防水性の向上:
雨水が建物の内部に浸入するのを防ぎ、構造体の腐食や雨漏りを防ぎます。特に、外壁材の継ぎ目やサッシ周りは雨水の浸入経路になりやすいため、シーリング工事は建物の防水性能を維持する上で不可欠です。
気密性の向上:
室内の空気や熱が外部に漏れるのを防ぎ、冷暖房効率を高めます。気密性が向上することで、エネルギー消費を抑え、快適な室内環境を維持することができます。
緩衝材としての役割:
地震や風圧などによる建物の揺れや部材の動きを吸収し、建物の損傷を防ぎます。シーリング材は、ある程度の伸縮性を持つため、部材同士の動きに追従し、負荷を軽減する効果があります。
美観の維持:
部材間の隙間を埋めることで、建物の外観を美しく保ちます。シーリング材の色や形状を適切に選択することで、建物全体のデザイン性を向上させることも可能です。
このように、シーリング工事は建物の耐久性、快適性、省エネルギー性、そして美観を維持するために、非常に重要な役割を果たしていると言えるでしょう。まさに、建物全体の品質を支える「縁の下の力持ち」のような存在です。
用途に合わせた材料選び:シーリング材の種類と特徴
シーリング工事に使用されるシーリング材には、様々な種類があり、それぞれに特徴や適した用途があります。建物の部位や求められる性能によって適切なシーリング材を選ぶことが、シーリング工事の品質を左右する重要な要素となります。
代表的なシーリング材の種類としては、以下のようなものが挙げられます。
シリコーン系:
耐候性、耐熱性、耐寒性に優れており、紫外線にも強いため、外装の目地やサッシ周りなど、屋外の幅広い用途で使用されます。比較的柔軟性も高く、動きの大きい箇所にも適しています。ただし、塗料が付着しにくい性質があるため、塗装を前提とする箇所には注意が必要です。
ポリウレタン系:
接着力が高く、塗料の密着性にも優れているため、塗装仕上げを前提とする箇所や、ALCパネルなどの目地によく使用されます。耐摩耗性にも優れていますが、耐候性はシリコーン系に劣る場合があります。
変成シリコーン系:
シリコーン系の耐候性と、ポリウレタン系の塗料密着性を兼ね備えたシーリング材です。幅広い用途に対応できるため、近年では主流となりつつあります。柔軟性や耐久性にも優れており、内外装の様々な箇所で使用されています。
アクリル系:
比較的安価で扱いやすいのが特徴です。主に内装の隙間や、動きの少ない箇所の補修などに使用されます。耐候性は他の種類に比べて劣るため、屋外での使用には適していません。
ブチルゴム系:
防水性が非常に高く、主に屋根材の接合部や、水密性が求められる箇所に使用されます。比較的柔軟性がありますが、耐候性はあまり高くありません。
これらのシーリング材は、それぞれ硬化後の特性(硬さ、柔軟性、収縮率など)や耐久性、耐候性、耐薬品性などが異なります。そのため、シーリング工事を行う際には、以下の点を考慮して適切なシーリング材を選択する必要があります。
施工箇所の材質:
外壁材、サッシの材質、屋根材など、施工する箇所の材質との相性を考慮します。
シーリングに求められる機能: 防水性、気密性、耐候性、耐薬品性など、その箇所に求められる機能を明確にします。
動きの有無:
地震や温度変化などによる部材の動きが大きい箇所には、柔軟性の高いシーリング材を選びます。
仕上げ:
塗装仕上げが必要な場合は、塗料の密着性の良いシーリング材を選びます。
適切なシーリング材の選択は、シーリング工事の品質と建物の長期的な維持に大きく影響します。専門業者に相談し、それぞれの箇所の状況に最適なシーリング材を選ぶようにしましょう。
シーリング材の種類と特徴
シーリング工事に使用されるシーリング材には、様々な種類があり、それぞれに特性と適した用途があります。代表的なシーリング材の種類と特徴を解説します。
「シリコン系シーリング材」は耐候性、耐熱性、耐寒性に優れており、紫外線にも強いため、外壁の目地やサッシ周りなど、屋外での使用に適しています。比較的安価で施工性も良いですが、塗料との相性が悪く、上から塗装できない場合がある点がデメリットです。また、油性であるため、ホコリなどが付着しやすいという性質もあります。
「ポリウレタン系シーリング材」は、弾力性、耐久性に優れており、動きの大きい箇所や振動を受ける箇所に適しています。塗料との相性も良く、上から塗装できるため、仕上げの自由度が高いのが特徴です。ただし、耐候性はシリコン系に比べてやや劣り、紫外線による劣化が見られる場合があります。また、湿気硬化型であるため、湿度が高い環境下での施工には注意が必要です。
「アクリル系シーリング材」は、水性で扱いやすく、塗装性にも優れています。比較的安価であるため、内装の補修や、あまり動きのない箇所での使用に適しています。ただし、耐水性や耐久性は他のシーリング材に比べて劣るため、屋外や水回りでの使用には不向きです。
「変成シリコン系シーリング材」は、シリコン系の耐候性とポリウレタン系の柔軟性、そして塗装性を兼ね備えた、比較的新しいシーリング材です。幅広い用途に対応でき、近年主流となりつつあります。価格はやや高めですが、その多機能性から多くの現場で採用されています。
その他にも、耐薬品性に優れた「フッ素系シーリング材」や、より高い耐久性を持つ「MS(変成シリコーンポリマー)系シーリング材」などがあります。どのシーリング材を選ぶかは、施工箇所の環境、建物の動き、仕上げの希望などを考慮して、専門業者と相談しながら決定することが重要です。それぞれの特性を理解することで、より適切なシーリング工事を行うことができるでしょう。
高品質な仕上がりのために:シーリング工事の施工手順と注意点
シーリング工事は、適切な材料選びだけでなく、正しい施工手順と丁寧な作業が不可欠です。手順を誤ったり、下処理が不十分だったりすると、シーリング材の早期劣化や剥離につながり、本来の目的を果たすことができなくなります。
一般的なシーリング工事の施工手順は以下の通りです。
既存シーリング材の撤去:
劣化した古いシーリング材をカッターなどで丁寧に除去します。この際、下地を傷つけないように注意が必要です。
清掃・下地処理:
シーリング材を充填する箇所の汚れや油分、水分などを丁寧に清掃します。また、必要に応じてプライマーと呼ばれる下地処理材を塗布します。プライマーは、シーリング材と下地の密着性を高める役割を果たします。
マスキング:
シーリング材を充填する箇所の両側に、仕上がり線を綺麗にするためのマスキングテープを貼ります。
シーリング材の充填:
シーリングガンなどを使用して、隙間にシーリング材を均一に充填します。空気が入らないように、奥までしっかりと充填することが重要です。
ならし:
ヘラなどを使用して、充填したシーリング材の表面を滑らかにならします。この作業により、防水性や気密性が向上し、美しい仕上がりになります。
マスキングテープの剥がし:
シーリング材が完全に硬化する前に、マスキングテープをゆっくりと剥がします。
養生:
シーリング材が完全に硬化するまで、雨水や直射日光などを避けて養生します。
高品質なシーリング工事を行うためには、以下の点に注意が必要です。
適切な工具の使用:
シーリングガンやヘラなど、作業に適した工具を使用することで、効率的かつ正確な施工が可能になります。
均一な充填:
シーリング材を隙間全体に均一に充填することで、防水性や気密性を確保します。
丁寧なならし:
表面を滑らかに仕上げることで、水の浸入を防ぎ、美観を向上させます。
天候への配慮:
雨の日や高温多湿な日の施工は避け、シーリング材の性能を十分に発揮できる環境で作業を行います。
安全管理:
高所作業などが必要な場合は、安全帯やヘルメットを着用し、安全に配慮して作業を行います。
シーリング工事は、専門的な知識と技術が求められる作業です。DIYで行うことも可能ですが、品質を確保するためには、信頼できる専門業者に依頼することをおすすめします。専門業者は、適切な材料の選定から丁寧な施工まで、一貫して行うことができます。
建物を長持ちさせるために:シーリング工事のメンテナンスと補修
シーリング材は、紫外線や雨風、温度変化などの影響を受け、経年劣化していきます。そのため、建物の寿命を長く保つためには、定期的なメンテナンスと適切な時期の補修が不可欠です。
シーリング材の劣化のサインとしては、以下のようなものが挙げられます。
ひび割れ:
シーリング材の表面に亀裂が入っている状態です。初期の劣化サインであり、放置すると雨水浸入の原因となります。
剥離:
シーリング材が下地から剥がれている状態です。防水性や気密性が大きく損なわれています。
肉やせ:
シーリング材のボリュームが減少し、凹んでいる状態です。隙間が広がり、雨水や空気の侵入を許す可能性があります。
硬化:
シーリング材が本来の柔軟性を失い、硬くなっている状態です。建物の動きに追従できなくなり、ひび割れやすくなります。
変色・汚染:
シーリング材の表面が変色したり、カビや藻が発生したりしている状態です。美観を損ねるだけでなく、劣化を促進する可能性もあります。
これらの劣化サインが見られた場合は、早めの補修が必要です。補修方法としては、部分的な打ち替えや、既存のシーリング材の上から新しいシーリング材を重ね打ちする方法などがあります。劣化の程度や範囲によって適切な補修方法を選択する必要があります。
定期的なメンテナンスとしては、以下の点に注意すると良いでしょう。
定期的な点検:
年に一度程度、専門業者に建物のシーリング部分を点検してもらい、劣化の状況を確認します。
早期の補修:
軽微な劣化が見られた場合は、早めに補修することで、大規模な改修を避けることができます。
清掃:
シーリング材の表面に付着した汚れを定期的に清掃することで、劣化の進行を遅らせることができます。
シーリング工事の耐用年数は、使用するシーリング材の種類や施工環境によって異なりますが、一般的には5年から10年程度と言われています。しかし、適切なメンテナンスを行うことで、より長く持たせることも可能です。
建物のシーリング部分は、普段あまり目に触れない場所ですが、建物の防水性や気密性を維持する上で非常に重要な役割を果たしています。定期的な点検と適切なメンテナンスを心がけ、建物を長持ちさせましょう。
まとめ
この記事では、シーリング工事の基本的な疑問から、その目的、種類、施工手順、そしてメンテナンスの重要性までを解説しました。
シーリング工事は、建物の部材間の隙間を埋めることで、雨水の浸入を防ぎ、室内の気密性を高める、建物を守るための重要な工事です。適切なシーリング材の選択と丁寧な施工、そして定期的なメンテナンスによって、建物の耐久性を向上させ、快適な室内環境を維持することができます。
もし、ご自身の建物のシーリング部分に気になる点がある場合は、放置せずに専門業者に相談することをおすすめします。適切な診断と処置を行うことで、建物の寿命を延ばし、資産価値を守ることにつながります。シーリング工事は、目立たないながらも、私たちの暮らしを支える上で非常に重要な役割を果たしています。
修繕をご検討されてましたらお気軽にご相談ください!
☆☆工事担当者が現地にて詳しく調査させて頂きます。☆☆
現地調査、お見積りは無料にてさせて頂きます。
まずはメールにてお気軽にお問い合わせください。お待ちしております。