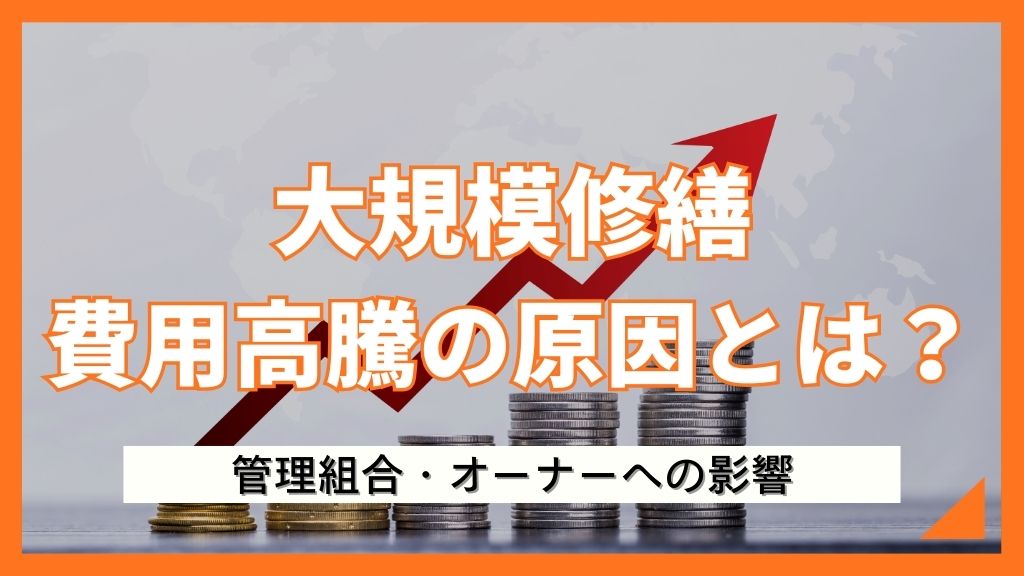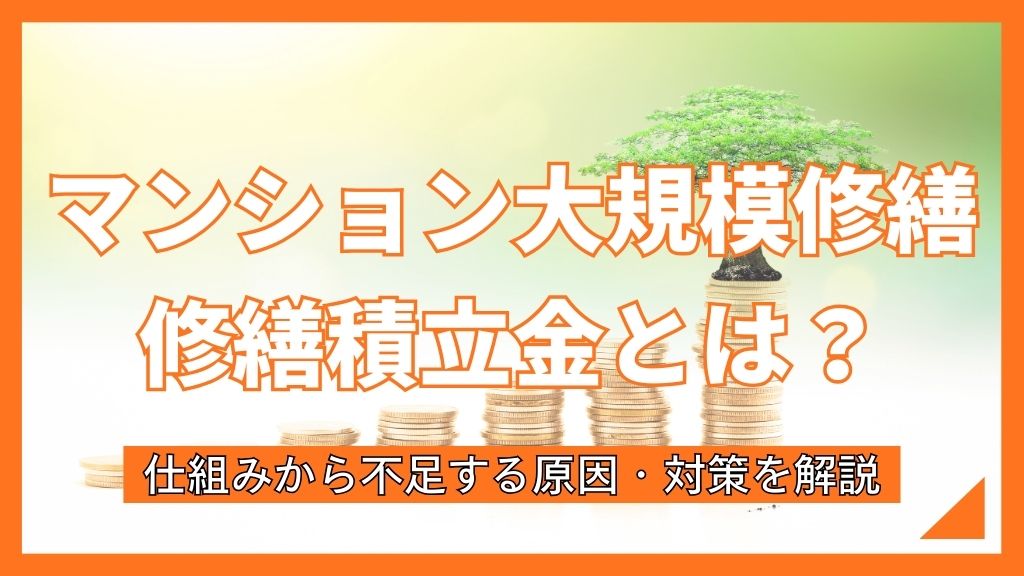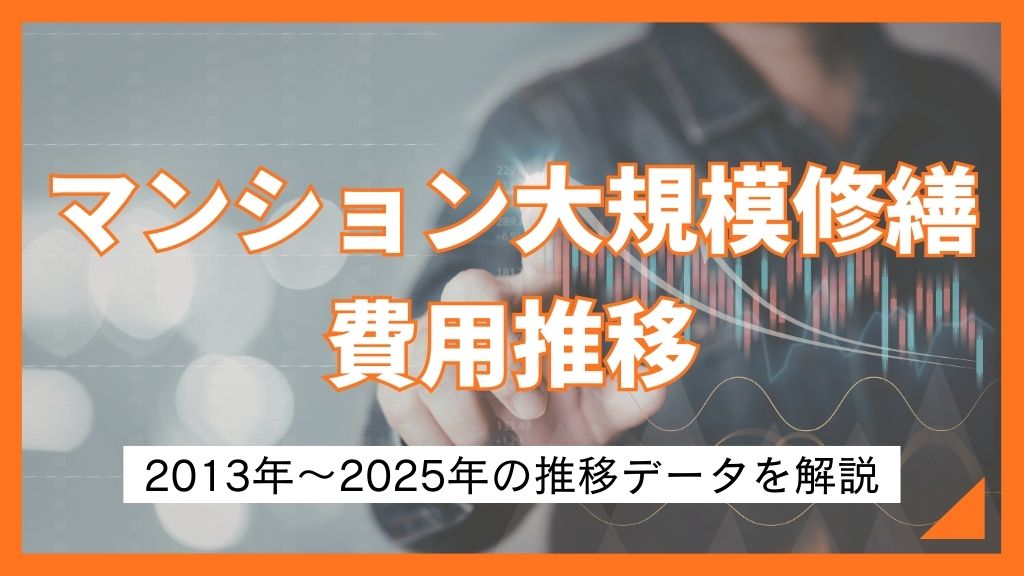マンション火災の保証内容とは?修繕工事中の火事は対象外?リスクから建物を守る方法を解説
2025/11/28
マンションの大規模修繕工事は、建物の資産価値を維持するために欠かせない重要な取り組みです。
しかし、工事期間中には思わぬ火災リスクが潜んでいることをご存じでしょうか。
2025年11月に香港で発生した高層マンション火災では、修繕工事中の不適切な防火対策が原因となり、多数の犠牲者が出る痛ましい事故となりました。
この記事では、マンション管理組合の理事や建物オーナーの皆様に向けて、修繕工事中の火災リスクと具体的な予防策、さらには万が一の際の対応方法まで、安全管理の実務を詳しく解説いたします。
日本の法規制に基づいた正しい知識を身につけ、大切な建物と住民の安全を守りましょう。
目次
香港高層マンション火災から学ぶ修繕工事の重要性
海外で発生した大規模火災の事例から、修繕工事における安全管理の重要性を再認識する必要があります。
日本のマンションでも同様のリスクが存在するため、他国の教訓を活かすことが求められます。
香港火災の概要と被害状況
2025年11月26日、香港の高層住宅群で大規模火災が発生し、発生から30時間以上にわたって消火活動が続けられました。
この火災による死者は94人に達し、200人以上が行方不明となる未曾有の災害となりました。
火災は複数の棟に延焼し、煙による被害も深刻でした。
修繕工事が火災の原因となった理由
香港警察の調査により、マンションで実施されていた修繕工事に重大な過失があったことが判明しました。
工事で使用されていた竹製の足場から出火し、防火基準を満たしていない可燃性のネットやシートを通じて急速に延焼したとみられています。
工事を請け負った会社の幹部3名が過失致死の容疑で逮捕され、汚職捜査機関も調査に乗り出す事態となりました。
日本のマンションでも起こり得るリスク
日本では竹製足場の使用は一般的ではなく、金属製の足場が主流です。
また、防炎性能を持つ資材の使用が法令で定められているため、香港と同様の火災が発生する可能性は低いとされています。
しかし、工事中の火気使用や資材管理に不備があれば、火災のリスクはゼロではありません。
日本の建築基準法や消防法に則った適切な安全管理が不可欠です。
マンション修繕工事中に潜む火災リスクとは
大規模修繕工事では、通常の居住状態とは異なる特有の火災リスクが存在します。
工事内容や使用する資材によって危険性が高まるため、具体的なリスク要因を理解しておくことが重要です。
足場や仮設材からの出火リスク
外壁塗装や防水工事で設置される足場には、飛散防止用のメッシュシートや養生シートが取り付けられます。
日本では労働安全衛生規則により、高さ10cm以上の幅木、メッシュシート、防網などの設置が義務付けられています。
これらの資材は防炎性能を持つものを使用する必要があり、消防法の防炎性能基準を満たした製品でなければなりません。
溶接・溶断など火気使用作業の危険性
鉄部の補修や設備工事では、溶接や溶断といった火気を使用する作業が発生します。
これらの作業では火花が飛散し、周囲の可燃物に引火する危険性があります。
作業場所の周辺に可燃物がないことを確認し、消火器を常備するなどの対策が必要です。
また、作業終了後も再燃火のリスクがあるため、十分な時間を置いて安全確認を行うことが求められます。
塗装作業での危険物取り扱いリスク
外壁塗装や防水工事で使用する塗料や溶剤の多くは、揮発性が高く引火しやすい危険物です。
保管場所の温度管理や換気、火気との距離を適切に保つ必要があります。
作業中は換気を十分に行い、静電気の発生にも注意を払うことが重要です。
これらの危険物を取り扱う際には、消防法に基づく適切な管理が義務付けられています。
作業員の喫煙や不注意による火災
建設現場での火災原因として見過ごせないのが、作業員の喫煙や不注意です。
指定された喫煙場所以外での喫煙や、吸い殻の不始末が火災につながるケースがあります。
工事現場では喫煙場所を明確に定め、作業員への教育を徹底することが必要です。
また、電気機器のコードやコンセント周りの管理不備も出火原因となるため、定期的な点検が欠かせません。
日本の法規制と修繕工事における防火基準
日本では建築基準法、消防法、労働安全衛生規則など、複数の法令によってマンション修繕工事の安全性が担保されています。
これらの法規制を正しく理解し、遵守することが管理組合と工事業者の責務です。
建築基準法による防火規制の概要
建築基準法では、建物自体の耐火性能や防火区画、内装制限などが定められています。
大規模修繕工事においても、防火扉や避難誘導灯などの消防設備が基準を満たしているかを確認する必要があります。
特に共用部分の配置変更や改修を伴う場合は、建築基準法に適合させることが求められます。
消防法で定める工事中の防火管理義務
消防法第8条では、一定規模以上の建物において防火管理者の選任が義務付けられています。
分譲マンションなどの共同住宅は「非特定用途の防火対象物」に該当し、収容人員が50人以上の場合に防火管理者の選任が必要です。
工事期間中は通常時と防火管理体制が異なるため、工事施工責任者が「工事中の消防計画」を作成し、管轄消防署に届け出る必要があります。
労働安全衛生規則に基づく安全対策
労働安全衛生規則第563条では、足場における作業床の要件が定められており、物体の落下による危険を防止するため、高さ10cm以上の幅木、メッシュシート、防網などの設置が義務付けられています。
これは作業員の安全だけでなく、下を通行する住民への危険防止にもつながる重要な規定です。
工事業者はこれらの規則を遵守し、定期的な安全パトロールを実施する必要があります。
防炎シート・メッシュシートの設置基準
足場に設置するメッシュシートや養生シートは、消防法令の防炎性能基準を満たす必要があります。
具体的には、日本工業規格JIS A 8952(建築工事用シート)に定める防炎性を有し、合成繊維製で難燃性または防炎加工を施したものでなければなりません。
また、仮設工業会の認定基準を満たした製品を使用することが推奨されています。
マンション修繕工事で実施すべき火災予防対策
法令遵守だけでなく、実務レベルでの具体的な火災予防対策を講じることが、安全な工事を実現する鍵となります。
工事前の準備から日々の管理まで、体系的な取り組みが求められます。
工事前の準備:消防計画の作成と届出
大規模修繕工事を開始する前に、工事施工責任者は「工事中の消防計画」を作成し、工事開始の7日前までに管轄消防署へ届け出る必要があります。
この計画には、火気使用場所の管理方法、危険物の保管方法、消火設備の配置、緊急時の連絡体制などを明記します。
既存建物で改修工事を行う場合も、通常の消防計画とは別に工事期間中の計画を作成することが求められます。
防火管理者の選任と役割
マンションの管理組合は、消防法に基づき防火管理者を選任する義務があります。
防火管理者は火災の発生を未然に防ぎ、万一火災が発生した場合には被害を最小限に抑えるための管理・指導を行います。
修繕工事期間中は、防火管理者と工事業者が密に連携し、日常的な安全確認を実施することが重要です。
足場・仮設材の安全基準と点検体制
足場の設置に際しては、安全計画を作成し、設置基準を満たしているかを確認します。
定期的な安全パトロールを実施し、足場の状態、メッシュシートの固定状況、幅木の設置などをチェックします。
強風や台風の前後には特に入念な点検が必要です。
労働基準監督署の立ち入り検査が実施されることもあるため、常に適法状態を維持することが求められます。
火気使用作業の管理と監視体制
溶接や溶断などの火気使用作業を行う際には、事前に防火管理者へ届け出て承認を受ける体制を整えます。
作業前後の点検を確実に実施し、消火器を作業場所に配置します。
作業中は監視員を配置し、火花の飛散状況や周囲の安全を常時確認します。
作業終了後も一定時間、再燃火がないかを監視することが重要です。
作業員への安全教育と危険予知活動
工事現場では、以下のような安全活動を日常的に実施することが効果的です。
- 新しく現場に入る作業員に対し、現場のルールや火災予防の注意事項を教育する
- その日の作業で発生しそうな危険について話し合う(危険予知活動)
- 作業内容、注意事項、天候による影響などを作業員全員で確認する
- 現場内に安全意識を高めるスローガンを掲示し、意識の向上を図る
これらの活動を継続することで、作業員一人ひとりの安全意識が高まり、火災をはじめとする事故の防止につながります。
消火設備の配置と緊急時の対応手順
工事現場には、適切な位置に消火器を配置し、すぐに使用できる状態にしておく必要があります。
火災発見時の初期対応として「通報・消火・避難」の3原則を徹底します。
まず119番通報を行い、初期消火が可能であれば消火器を使用しますが、火の勢いが強い場合は迷わず避難を優先します。
緊急連絡網を整備し、管理組合、工事業者、消防署への連絡体制を明確にしておくことが重要です。
管理組合が知っておくべき修繕工事業者の選定ポイント
大規模修繕工事を安全に進めるためには、確かな安全管理体制を持つ工事業者を選定することが最も重要です。
価格だけでなく、安全への取り組み姿勢を見極める必要があります。
安全管理体制が整った業者の見極め方
優良な工事業者は、社内で安全管理の専門部署を設けており、現場ごとに安全管理責任者を配置しています。
安全衛生管理計画を作成し、定期的な安全パトロールを実施する体制が整っているかを確認しましょう。
また、協力業者への安全教育や、年間無災害記録の表彰制度など、安全文化を醸成する取り組みがあるかも重要なポイントです。
過去の実績と安全記録の確認方法
工事業者を選定する際には、同規模のマンションでの施工実績を確認します。
特に過去5年間の労働災害発生状況や、消防法違反の有無を尋ねることが重要です。
実績のある業者は、過去の施工事例を写真や報告書で提示できます。
可能であれば、過去に施工したマンションの管理組合に問い合わせて、工事中の安全管理状況について評価を聞くことも有効です。
工事契約時に確認すべき安全対策項目
工事請負契約書には、安全管理に関する条項を明記することが重要です。
以下の項目を契約書に盛り込むことを推奨します。
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 安全管理責任者の配置 | 現場に常駐する安全管理責任者の氏名と資格 |
| 消防計画の届出 | 工事開始前の消防署への届出義務 |
| 安全設備の設置基準 | 防炎シート、消火器、安全通路などの具体的な設置基準 |
| 定期報告の実施 | 管理組合への安全パトロール結果の報告頻度 |
| 賠償責任保険の加入 | 工事中の事故に対する賠償責任保険の補償内容 |
これらの項目を契約段階で明確にすることで、工事業者の責任範囲が明らかになり、万が一の際にも適切な対応が可能となります。
工事期間中の安全パトロールと報告体制
工事が開始された後も、定期的な安全確認が欠かせません。
工事業者は週1回以上の安全パトロールを実施し、その結果を管理組合に報告する体制を整えるべきです。
管理組合側も、理事が月に1回程度現場を視察し、安全対策が適切に実施されているかを確認することが望ましいです。
不備が見つかった場合は、速やかに是正を求める姿勢が重要です。
火災保険の保証内容と修繕工事への適用
火災保険は、万が一の火災発生時に経済的な損失を補償する重要な備えです。
修繕工事との関係性を正しく理解し、適切な保険設計を行うことが管理組合の責務となります。
マンション共用部の火災保険とは
分譲マンションの共用部分については、管理組合が建物全体を対象とした火災保険に加入するのが一般的です。
この保険は、火災だけでなく落雷、風災、水災などの自然災害による損害もカバーします。
さらに、他の住戸で発生した水漏れによる損害や、突発的な事故による破損なども補償範囲に含まれる場合があります。
保険金額は建物の再調達価格を基準に設定します。
修繕工事中の火災は補償されるのか
マンションの火災保険は、工事中の火災についても基本的に補償対象となります。
ただし、工事業者の過失による火災の場合は、工事業者が加入している賠償責任保険から補償されるのが原則です。
したがって、管理組合の火災保険と工事業者の賠償責任保険の両方が関係することになります。
保険の適用関係を明確にするため、工事契約時に保険の取り扱いについて確認しておくことが重要です。
工事業者の賠償責任保険の重要性
工事業者は、工事中の事故により第三者に損害を与えた場合に備えて、請負業者賠償責任保険に加入しています。
この保険は、工事の過失により火災が発生し、建物や住民に損害が生じた場合の賠償金をカバーします。
管理組合は、工事業者が十分な補償額の賠償責任保険に加入しているかを契約前に確認すべきです。
補償額が不十分な場合は、増額を求めることも検討しましょう。
火災保険を活用した修繕工事のポイント
自然災害や突発的な事故により建物に損傷が生じた場合、火災保険を活用して修繕工事を行うことができます。
保険金を請求する際には、被害箇所を漏れなく調査し、写真などの証拠を十分に残すことが重要です。
保険会社への申請は、専門知識を持つ業者に依頼することで、適正な保険金を受け取れる可能性が高まります。
ただし、経年劣化による損傷は補償対象外となるため、保険適用の可否を事前に確認する必要があります。
万が一マンションで火災が発生した場合の対応
火災予防に万全を期しても、万が一の事態に備えた対応手順を整えておくことは管理組合の重要な責務です。
迅速かつ適切な初動対応が、被害の拡大を防ぎます。
初期対応の3原則:通報・消火・避難
火災を発見したら、まず119番通報を行うことが最優先です。
消防への通報と並行して、周囲に火災の発生を知らせ、初期消火に取り組みます。
消火器を使用する際は、火元から2~3メートルの距離を保ち、火の根元を狙って放射します。
ただし、天井まで火が回っている場合や、煙で視界が悪い場合は、初期消火を断念して速やかに避難することが重要です。
避難時は煙を吸わないよう、姿勢を低くして進みます。
煙による被害を最小限に抑える方法
建物火災における死因の約4割は、煙による一酸化炭素中毒や窒息です。
煙は階段を伝って驚くほど速く上階に広がるため、高層階の住民は特に注意が必要です。
避難時はエレベーターを使用せず、必ず階段を利用します。
濡れたタオルやハンカチで口と鼻を覆い、煙を吸い込まないよう注意しながら避難します。
自室にいる場合は、ドアの隙間から煙が入らないよう目張りをし、救助を待つことも選択肢となります。
鎮火後の復旧プロセスと専門業者の活用
火災が鎮火した後は、すすや火災臭の除去、損傷箇所の修繕など、専門的な復旧作業が必要となります。
火災復旧の専門業者は、特殊な技術とノウハウを用いて、すすの除去や臭いの脱臭処理を行います。
また、エレベーターなどの設備が損傷した場合は、設備業者による点検と修理が必要です。
管理会社を通じて、火災復旧の専門会社や各設備業者に速やかに連絡し、復旧計画を立てることが重要です。
マンション火災に関するよくある質問【FAQ】
マンションの修繕工事と火災に関して、管理組合や理事の方々からよくいただく質問をまとめました。疑問点の解消にお役立てください。
Q1. マンションの大規模修繕工事で火災が起きる確率は?
統計によると、全国で1日あたり最大10件弱の共同住宅火災が発生していますが、そのうち工事中の火災が占める割合は明確なデータがありません。
ただし、適切な安全管理を実施している工事現場では、火災発生のリスクは極めて低いと言えます。
重要なのは、工事業者が消防計画の届出や防炎資材の使用など、法令を遵守しているかを確認することです。
Q2. 修繕工事中に火災が発生した場合、責任は誰にありますか?
工事業者の過失により火災が発生した場合は、工事業者が損害賠償責任を負います。
一方、放火など工事と無関係な原因による火災の場合は、マンションの火災保険で対応することになります。
責任の所在を明確にするため、工事請負契約書に安全管理義務と賠償責任の範囲を明記しておくことが重要です。
また、工事業者が賠償責任保険に加入していることを必ず確認しましょう。
Q3. 工事中の消防計画の届出は必ず必要ですか?
消防法により、一定規模以上の建物で工事を行う場合は、工事中の消防計画を作成し、管轄消防署に届け出る義務があります。
具体的には、地階を除く階数が11以上で延べ面積が10,000㎡以上の建物や、延べ面積が50,000㎡以上の建物が対象となります。
該当する場合は、工事開始の7日前までに届出を完了する必要があります。
届出義務の有無については、管轄の消防署に事前に確認することをお勧めします。
Q4. 防火管理者がいないマンションでも修繕工事はできますか?
消防法では、収容人員が50人以上の共同住宅には防火管理者の選任が義務付けられています。
防火管理者が選任されていない状態は消防法違反となるため、修繕工事の前に必ず選任する必要があります。
近年は、防火管理者のなり手が少ないため、外部の専門コンサルタントに委託するケースも増えています。
管理組合で防火管理者が不在の場合は、早急に選任手続きを進めましょう。
Q5. 修繕工事中の火災で住民に被害が出た場合、補償はどうなりますか?
工事業者の過失による火災で住民に被害が生じた場合は、工事業者が加入している賠償責任保険から補償されます。
人的被害(けがや死亡)だけでなく、住戸内の家財の損害や、避難期間中の宿泊費用なども補償対象となる場合があります。
ただし、補償内容は保険契約の内容によって異なるため、工事契約時に工事業者の保険証券を確認し、補償額が十分かどうかを確認することが重要です。
まとめ:安全な修繕工事で資産価値を守る
マンションの大規模修繕工事は、建物の寿命を延ばし資産価値を維持するために不可欠な取り組みです。
しかし、香港の火災事例が示すように、工事中の安全管理を怠ると、取り返しのつかない被害につながる可能性があります。
防炎性能を持つ資材の使用、消防計画の届出、防火管理者の選任など、法令を遵守することが第一歩です。
以下のポイントを改めて確認しましょう。
- 工事業者の選定時には、価格だけでなく安全管理体制と過去の実績を重視する
- 工事契約書に安全対策の具体的な項目と責任範囲を明記する
- 工事前に消防計画を作成し、管轄消防署に届け出る
- 防火管理者と工事業者が連携し、日常的な安全確認を実施する
- 火災保険と工事業者の賠償責任保険の補償内容を確認する
- 万が一の火災発生時の初期対応手順を全住民に周知する
これらの対策を確実に実行することで、安全な修繕工事を実現し、大切なマンションと住民の生命・財産を守ることができます。
株式会社新東亜工業は、東京都内を中心にマンションの大規模修繕工事を手がける専門業者として、安全管理を最優先した施工を実施しております。
消防法に基づく適切な届出、防炎資材の使用、日々の安全パトロールなど、法令を遵守した確実な工事をお約束いたします。
マンションの修繕工事をご検討の際は、豊富な実績と確かな技術を持つ当社にぜひご相談ください。
大規模修繕工事でお悩みの管理組合の方
「ファシリテーション」で談合をなくそう!
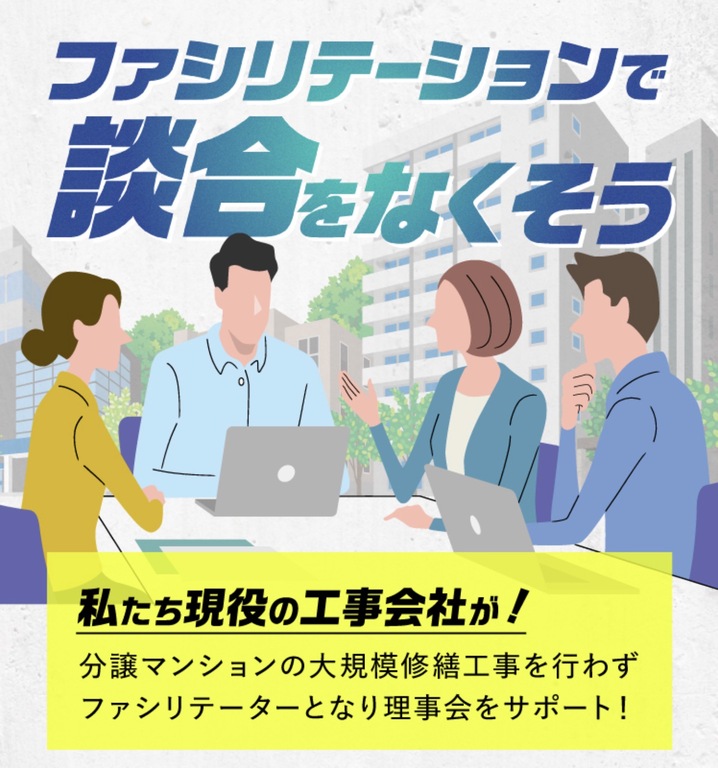
\お問い合わせや工事のお見積もり無料!/
豊富な実績と専門知識を持つスタッフが、
皆様の疑問や不安にお答えし、最適な解決策をご提案いたします。