マンションの大規模修繕における施工方式とは?発注形態の違いと選び方を解説
2025/07/24
マンションの大規模修繕は、建物の長寿命化や快適な住環境の維持、資産価値の保全といった目的で行われる重要な工事です。多くの区分所有者が関わるマンションでは、修繕計画の立案から実施までのすべての工程において、合意形成と正しい情報判断が求められます。その中でも、最初に決定すべき項目として重要なのが「施工方式(発注方式)」です。
施工方式とは、工事をどのような体制で発注し、誰が何を管理し、どのように進行させるのかという基本的な枠組みを決めるものです。方式の違いによって、工事の品質、コストの妥当性、進捗管理の明確さ、そして最終的な満足度までもが左右されます。
代表的な施工方式には「責任施工方式」「設計監理方式」「CM方式(コンストラクション・マネジメント方式)」の3つがあり、それぞれに一長一短があります。どれを選ぶべきかは、建物の構造や修繕の規模、管理組合の知識や体制、予算の規模など、さまざまな要因によって異なります。
本記事では、各施工方式の基本的な仕組みや特徴を丁寧に解説するとともに、比較表や向いているケース、管理組合が考慮すべき判断材料についても詳しく紹介していきます。これから大規模修繕に臨む管理組合や理事の方々が、適切な選択を行うための一助となる内容です。
大規模修繕・防水工事・外壁塗装のご依頼・メール・お電話でお受け致しております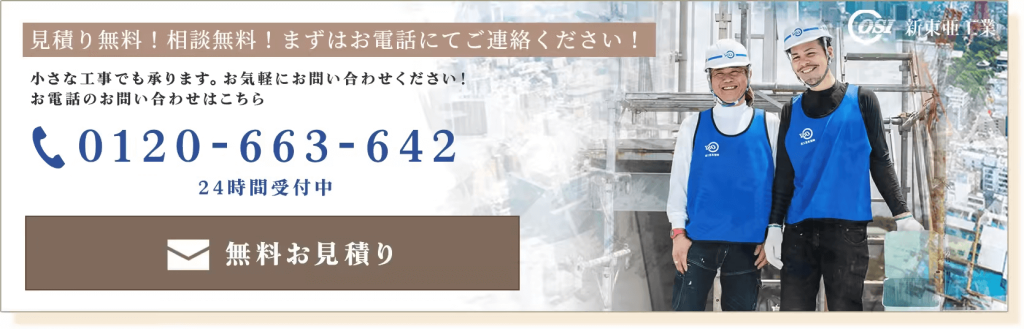
目次
施工方式とは?マンションの修繕工事における基本的な考え方
施工方式とは、マンションの大規模修繕を実施する際に、どのような組織体制と役割分担で進めていくかを決定する重要な枠組みです。管理組合が工事業者と直接やり取りするのか、それとも第三者に介入を依頼するのか、設計と施工を別の業者に分けるのか――その方式によって、工事の透明性や品質、費用、管理者の負担が大きく異なってきます。
施工方式は単なる「業者の選び方」ではなく、工事そのものの進め方に直結する要素です。管理組合としては、工事の計画段階から方式の選定を視野に入れ、理事会や修繕委員会と協力しながら慎重に進めることが求められます。
ここでは、マンションの大規模修繕において主に採用されている3つの施工方式について、それぞれの特徴を見ていきましょう。
責任施工方式
責任施工方式は、調査・設計から施工までの全工程を一括して施工会社に依頼する方式です。管理組合は設計者を別途雇うことなく、工事業者に直接依頼するため、工程がシンプルで手続きの手間が少ないという特徴があります。
- メリット:
- 業者を1社にまとめられるため、調整の手間が減りスピーディーに工事が進む。
- 設計・監理の費用がかからず、コストを抑えやすい。
- 小規模マンションや経験のある管理組合にとって負担が軽くなる。
- デメリット:
- 設計と施工が同じ業者になるため、チェック機能が働きづらく、品質管理が甘くなるリスクがある。
- 業者主導で進むため、住民の希望が反映されにくいことも。
- 向いているケース:
- 比較的小規模なマンション
- 修繕の経験が豊富な管理組合
- コストを優先したいケース
設計監理方式(設計・監理分離方式)
設計監理方式は、設計者(建築士や修繕コンサルタント)に調査・診断・設計を依頼し、その設計に基づいて施工会社を公募・選定する発注方式です。施工と監理を分離することで、工事の透明性と品質管理を強化できるという大きな利点があります。
- メリット:
- 設計者が発注者(管理組合)の立場で施工を監理してくれるため、品質とコストのバランスが取りやすい。
- 複数の施工会社から相見積もりを取得できるため、価格競争が働きやすい。
- 仕様書がしっかり作成されるため、契約内容が明確になる。
- デメリット:
- 設計・監理の費用が別途発生する。
- 設計者とのコミュニケーションが必要で、理事会や修繕委員の負担がやや増える。
- 向いているケース:
- 中〜大規模マンション
- 修繕工事の経験が少ない管理組合
- 品質や長期的な視点を重視する場合
CM方式(コンストラクション・マネジメント方式)
CM方式は、CM(コンストラクション・マネージャー)と呼ばれる第三者の専門業者を管理組合の代理人として選任し、設計者や施工業者と独立した立場で全体の工程をマネジメントする方式です。
- メリット:
- CM会社が全体を中立的に管理するため、利害の偏りがなく、公正な判断が可能。
- 工事全体の見積書や進捗を厳密にチェックし、コストと品質を最適化できる。
- 管理組合に専門知識がない場合でも安心して進められる。
- デメリット:
- CM会社への報酬が発生するため、全体のコストが高くなる可能性がある。
- 普及率がまだ低く、信頼できるCM会社を探すのに手間がかかる場合もある。
- 向いているケース:
- 大規模マンション
- 修繕計画が複雑で複数業者が関与する場合
- 管理組合に専門知識を持つ人材が少ない場合
施工方式別の比較ポイント【一覧で確認】
施工方式を選ぶ際には、それぞれのメリットやリスクを比較した上で、マンションの実情に合った方式を選定することが求められます。以下は、代表的な比較項目に基づく方式別の評価表です。
| 比較項目 | 責任施工方式 | 設計監理方式 | CM方式 |
|---|---|---|---|
| コスト透明性 | △ | ◎ | ◎ |
| 工事品質の担保 | △ | ◎ | ◎ |
| 柔軟な対応力 | ◎ | △ | △ |
| 発注者側の負担 | ◎ | △ | △ |
| 業者選定の自由度 | △ | ◎ | ◎ |
責任施工方式はコスト面と作業負担の軽さに強みがありますが、品質管理の観点ではやや弱いとされています。設計監理方式とCM方式は、管理組合の負担は多少増えますが、透明性と品質確保の面で優れており、近年多くのマンションで採用されています。
施工方式の選定は単なるコスト比較ではなく、「建物の将来にどれだけ責任を持てるか」「住民全体が納得できる体制を築けるか」という観点が重要です。次のパートでは、管理組合が施工方式を選ぶ際の判断基準や、トラブル回避のポイントについてさらに詳しく解説していきます。
管理組合が施工方式を選ぶ際の判断基準
マンションの大規模修繕において施工方式を選定することは、工事全体の方向性や成功可否を大きく左右する非常に重要な工程です。施工方式は、単に工事業者をどう選ぶかという視点にとどまらず、工事の品質、コスト、住民の満足度、そして将来の維持管理にも大きな影響を与える決定事項です。どの方式が最適かを見極めるためには、マンションの規模や築年数といった物理的要因だけでなく、管理組合の意思決定体制、修繕委員会の組成状況、住民の関心度や価値観までをも総合的に考慮する必要があります。
ここでは、施工方式を選ぶ際に特に注目すべき3つの判断視点について、より詳細に解説します。
管理組合の運営体制と専門性
最初に確認すべきポイントは、管理組合の体制とその中にある専門知識の有無です。理事会や修繕委員会に建築士や施工管理の経験者など、建物に関する知見を持つ人がいる場合と、そうでない場合とでは適切な施工方式は異なります。
たとえば、専門的な知識を持つメンバーがいない管理組合が責任施工方式を選んでしまうと、施工会社から提示された設計・見積内容の是非を判断できず、不必要な工事やコスト高のリスクが生じます。また、説明不足のまま合意が進むことで、住民間の不信やトラブルにもつながりかねません。
逆に、設計監理方式やCM方式を採用すれば、専門家が第三者的立場でプロジェクトを管理してくれるため、管理組合内に専門性がなくても一定の安心感をもって進めることが可能です。管理会社との連携体制や過去の修繕経験も加味し、管理組合の力量に応じた方式選びが求められます。
工事内容の規模と複雑さ
次に、修繕工事のボリュームや内容の複雑さを考慮しましょう。修繕対象が屋上防水や外壁塗装など単一工種で完結するものであれば、責任施工方式でもスムーズな進行が期待できます。しかし、配管の更新、エレベーター設備の改修、バルコニー防水、断熱性能の向上といった、複数業者が関わる多工程にわたる場合は、施工会社だけでの一括管理には限界が生じます。
設計監理方式であれば、設計者が図面をもとに各業種の連携を計画・監理でき、CM方式ならマネジメント会社がそれらを横断的に統括します。特に築30年以上経過し、過去の修繕履歴に曖昧な点が多いマンションでは、事前の建物診断と精緻な設計を経た上での発注体制が不可欠です。
さらに、将来的な長寿命化や省エネ対策、バリアフリー化などを見据えた改修を視野に入れる場合にも、複数の専門家が関与できる体制がある方式が望ましいと言えるでしょう。
予算とコスト管理の重視度
工事費用が管理組合にとって大きな関心事であることは言うまでもありません。施工方式によって初期費用や総工費のコントロールの仕方に違いが出てくるため、コストに対する価値観も方式選定における重要なファクターです。
責任施工方式は、設計費や監理費がかからないため、一見すると安価に見えるケースが多いです。ただし、その見積の中身が精査されていない場合や、設計・施工が一体で進められることによる情報の非対称性により、追加工事やグレードの変更といった名目で総費用が膨らむ可能性も否めません。
一方、設計監理方式やCM方式は、設計費・管理費が初期費用として必要ですが、詳細な設計・仕様書に基づいた複数社からの競争入札が可能となり、透明性の高い見積を取得できます。そのため、長期的にはコストの適正化と品質の担保が両立しやすく、総合的な費用対効果が高くなる傾向にあります。
工事に充てられる予算の額や、修繕積立金の蓄積状況、住民の経済的許容度などを整理し、どの方式が最も納得感の高い費用管理ができるかを判断材料としましょう。
トラブルを避けるために押さえておきたいポイント
施工方式の違いを理解せずに工事を進めてしまうと、工事完了後に後悔したり、思わぬトラブルに巻き込まれるリスクがあります。ここでは、どの方式を採用する場合でも共通して注意すべき3つのポイントを紹介します。
責任の所在を明確にしておく
特に責任施工方式では、設計と施工が一体となっていることから、施工後に瑕疵や不具合が発生した場合に、原因が設計ミスなのか施工不良なのかが不明確になり、責任の押し付け合いになることがあります。
このような事態を未然に防ぐためには、契約段階で設計内容、施工範囲、保証条件、アフター対応に至るまでを明確に文書化し、管理組合と業者の間で責任分界を明確にしておくことが大切です。できれば法律や建築に詳しい第三者のチェックを受けることも推奨されます。
設計監理方式やCM方式であれば、設計者やマネージャーが中立の立場で各業者の業務分担を監督してくれるため、問題が生じた際の対応もスムーズです。
住民への説明・合意形成
施工方式の違いによって、工事の内容や金額、スケジュールが大きく変動するため、住民の合意形成はどの方式でも不可欠な要素です。住民が施工方式について正しく理解していないまま合意を進めてしまうと、「聞いていなかった」「こんな費用がかかるとは思わなかった」といったトラブルに発展しかねません。
とくにCM方式のような馴染みの薄い方式を採用する際は、事前に説明会や資料配布を通じて住民に丁寧な情報提供を行い、全体の合意を得ることが重要です。説明の中では、それぞれの方式の違い、コスト構造、管理体制の違いなどを図や比較表を用いて視覚的に説明することで、理解を促しやすくなります。
住民の意見を無視したまま進めることは、工事途中での反発や組合内の対立を生む原因にもなります。工事の透明性と住民の納得感を高めるには、情報の共有と開かれたコミュニケーションが不可欠です。
見積もり・契約内容のチェック
施工方式に関わらず、最終的な工事費やリスクを左右するのが見積書と契約書の内容です。見積書には工事項目ごとの数量や単価、使用材料のグレードなどが明示されている必要があります。
以下のポイントは必ずチェックしておきましょう:
- 見積書の内訳が詳細かつ透明であるか
- 数量や仕様の根拠が示されているか
- 変更や追加工事の対応フローが明文化されているか
- 瑕疵保証や保険の適用範囲が記載されているか
また、契約書には万一のトラブル時の対応方法(解約条件、損害賠償、責任分担など)が明記されているかを確認し、不安がある場合は専門家に相談するのが賢明です。
特に責任施工方式では、施工業者が一括で見積を作成するため、他方式以上に内容の妥当性を見極める力が求められます。他方式では、設計者やCM会社が業者の見積をチェック・評価してくれるため、リスク分散がしやすくなります。
実録!新東亜工業の施工事例|7階建てマンションの大規模修繕工事
今回は、東京都墨田区にある7階建てマンションで実施された大規模修繕工事の実例をご紹介します。色選びの失敗を繰り返したくないというオーナー様のご相談から始まり、現地調査、丁寧な工程説明、施工後の満足の声まで、実際の会話を交えながら施工の流れをわかりやすくお届けします。
大規模修繕・防水工事・外壁塗装のご依頼やご相談は、メール・お電話からお受け致しております。

ご相談内容
お問い合わせ時点で、オーナー様は過去の色選びの失敗と屋上防水の要否にお悩みでした。
お客様:「前に外壁の修繕をやったとき、色で失敗してしまって…。今回はちゃんと満足できるものにしたいんです」
お客様:「屋上防水もやるべきか迷っていて…実は5年前に他業者でやってるんですが、そのまま使えますか?」
現地調査の結果、屋上防水の状態は良好と判断。防水あり/なしの2パターンで見積を提示し、「防水なしプラン」でのご契約となりました。
工事の概要|工事金額と施工期間


今回の工事では、外壁塗装、シーリング打ち替え、鉄部塗装、足場など複数の工事項目を含めて施工。屋上防水は状態良好につき除外となりました。
| 工事項目 | 内容 |
|---|---|
| 外壁塗装 | シリコン塗装仕上げ |
| シーリング | 全箇所撤去・打ち替え |
| 鉄部塗装 | 玄関扉・バルコニー手すりなど |
| 足場 | 全面架設 |
工事金額:約852万円(税込)
施工期間:約50日間
お客様:「複数パターンで見積を出してくれたので比較しやすかったですね。説明もわかりやすくて納得できました」
担当者:「屋上防水は前回の状態が良好でしたので、今回は必要ありませんでした。余計な費用がかからないよう判断させていただきました」
現地調査で判明した劣化症状
現地調査では、以下のような劣化症状が確認されました。
- シーリングの硬化・亀裂:経年劣化により弾性を失い、ひび割れ多数
- シーリングの「増し打ち」による施工不良:旧シールを撤去せず重ねていたことで剥離が発生
- 外壁塗装の色あせ・汚れ:前回塗装の退色が進行し、日陰部に黒ずみ
- バルコニー床のトップコート剥離:防水機能は残るものの、表面劣化あり
担当者:「古いものを撤去せず上から足してあるだけだったので、耐久性が落ちてました。今回はすべて撤去して打ち直します」
お客様:「やっぱり、見えないところもきちんと確認してもらえると安心できますね」
施工中のやり取りと配慮
工事中は毎回担当者が進捗を報告。外壁色や長尺シートの見本を見て決定しながら進められ、工程ごとに確認しやすい体制を整えました。
担当者:「今日は3階バルコニーのシーリングを打ち替えていきます。既存シールはすべて撤去済みです」
お客様:「毎回進捗を伝えてくれるので、こちらも安心して見守れます」
担当者:「色見本の実物板を5種類ほど持ってきましたが、どれがよさそうですか?」
お客様:「これがいいですね!」
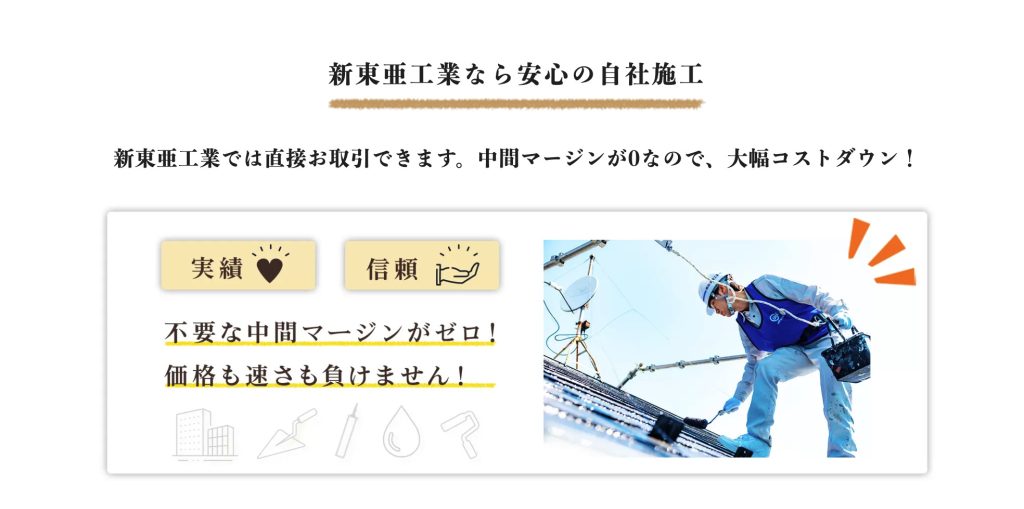
お問い合わせや工事のお見積もり無料!まずはメール・お電話からご相談ください!
引き渡し時のご感想
引渡し時には、オーナー様とお母様にも仕上がりをご確認いただき、ご満足の声をいただきました。
お客様:「本当イメージ通りの色でよかったです。ありがとうございます。母も喜びますわ!」
お客様:「領収書の件も丁寧に対応してくださって助かりました。最初から最後まで信頼できました」
施工方式選定のステップと専門家の活用法
施工方式の選定は、単に複数の選択肢を比較して選ぶだけではなく、段階を追って検討を重ねることで、より納得感のある意思決定へとつながります。特にマンションの大規模修繕は、長期的な資産維持に関わる重要なプロジェクトであるため、形式的な選定ではなく、実態に即した判断が必要です。以下では、管理組合が取るべき検討ステップと、活用可能な専門家の役割について詳しく解説します。
ステップ1:建物の現状把握と課題の整理
まず最初に行うべきは、対象となるマンションの建物状態を正確に把握することです。建物診断を行わずに施工方式を決めてしまうと、必要な修繕が漏れたり、逆に過剰な工事を実施することになりかねません。過去の修繕履歴を精査し、どの部分が劣化しており、どの程度の修繕が必要なのかを明確にすることで、工事のスコープを整理できます。
この段階では、専門の建築士や調査会社による建物劣化診断(建物診断報告書)を依頼することが推奨されます。外壁の浮き、鉄筋の腐食、屋上防水の劣化状況、設備機器の耐用年数など、客観的かつ詳細な情報を得ることで、施工方式の選定にも具体性が加わります。
ステップ2:理事会・修繕委員会内で方向性を協議
現状分析が完了したら、次は理事会や修繕委員会内で協議を行い、工事の目的と優先順位を整理します。「コストを抑えることが最優先なのか」「品質や耐久性を重視するのか」「工期の短縮を図りたいのか」といった観点から、それぞれの施工方式が持つメリット・デメリットを照らし合わせながら比較検討します。
この段階では、あえて方式を一つに絞る必要はありません。複数の選択肢を挙げ、それぞれの方式を採用した場合の想定課題や対応策を議論しておくことが、住民説明会や総会での理解促進にも役立ちます。また、検討過程で出た懸念事項を整理しておくことで、後の専門家相談や見積取得時にも明確な質問ができます。
ステップ3:専門家の助言を受けて方式を決定
施工方式の選定に迷いがある場合や、専門的な判断を要する場合は、第三者の専門家から助言を受けることが極めて有効です。管理組合の立場から中立的にアドバイスしてくれる専門家の存在は、複雑な施工方式の違いをわかりやすく整理し、住民への説明の助けにもなります。
活用できる専門家の例:
- 修繕コンサルタント:建物診断から設計、施工監理まで包括的に対応できる業者。技術的知見と発注者側の視点を併せ持ち、方式選定の初期段階から相談可能です。
- 一級建築士・設計事務所:設計監理方式を採用する場合に設計・図面作成・現場監理まで対応。仕様書の精度や見積比較の公平性確保に有効です。
- CM会社(コンストラクション・マネジメント会社):中立的な立場で工事全体のマネジメントを行い、工程管理や予算監理、業者調整などを担います。
- 弁護士・マンション管理士:契約書や法的な権利関係に関するチェック、住民トラブルの予防、説明資料の法的妥当性の確認などをサポート。
施工方式の決定後は、必要に応じて設計者の選定、公募や見積取得、住民説明会の段取りへと進行していきます。方式に応じたプロセスの違いにも留意が必要です。
よくある質問(FAQ)
Q1:責任施工方式でもトラブルなく進められる?
A:責任施工方式は手間がかからず、スピーディーに進行できる利点がありますが、その一方で施工会社主導になりやすく、監理の目が入りにくいという課題があります。管理組合に建築知識や監督力がある場合には有効ですが、知識がない場合は設計内容や工事の妥当性を判断できず、後に不具合が発覚することも。チェック体制を補う工夫が必要です。
Q2:小規模マンションでもCM方式は使える?
A:CM方式はもともと大規模建築物で採用されることが多かったですが、最近では小規模マンション向けのコンパクトなマネジメントサービスも登場しています。住民の高齢化や理事会人材不足により「第三者にすべて任せたい」というニーズが高まる中、柔軟な対応が可能なCM会社であれば、小規模物件にも対応できます。ただし費用と業務範囲の確認は必須です。
Q3:住民に施工方式をどう説明すればよい?
A:住民にとって施工方式は専門的すぎて理解が難しい分野です。そのため、比較表や図解を活用して「何が違うのか」「どこが自分たちに関係するのか」を視覚的に伝えることが効果的です。また、住民説明会では一度で理解してもらうのではなく、数回に分けて説明を行い、質問や意見を吸い上げることで納得感が得られやすくなります。専門家による説明を加えることも有効です。
Q4:施工方式は途中で変更できる?
A:施工方式は初期段階での方向性の一部として検討されるものであり、原則として設計・業者選定前であれば変更が可能です。しかし、一度設計契約を結んだ後や、施工業者との工事契約を締結した後の変更は非常に困難となるため、慎重な判断が求められます。方式に関する合意はできる限り早い段階で固めましょう。
Q5:どの方式が一番コストが安いの?
A:短期的な工事費だけで見れば、責任施工方式が一番安く見えることが多いです。しかし、設計・監理機能が不足することで発生する追加工事や不具合、メンテナンスのやり直しなどによって、長期的にはコスト増になることも少なくありません。設計監理方式やCM方式は初期費用こそ高くなりますが、トータルでのコストパフォーマンスや安心感は高いとされています。
まとめ:自分たちに合った施工方式で納得の修繕を
マンションの大規模修繕は、10〜15年に一度の重要な共同事業であり、その成否を左右するのが「施工方式の選定」です。責任施工方式、設計監理方式、CM方式のいずれも一長一短があり、管理組合の体制、住民の意識、工事の規模や内容によって最適な方式は異なります。
大切なのは、それぞれの方式がもたらす「責任の所在」「品質の担保」「コスト管理」「住民対応」などの違いを正しく理解し、住民全体が納得の上で方式を選ぶことです。専門家の助言を受けることで、知識の補完と意思決定の透明性を確保でき、トラブルの少ない修繕が可能となります。
さらに、方式決定後の準備や業者選定、説明会運営なども方式により大きく異なるため、事前準備の充実が成功の鍵を握ります。住民間の信頼と協力を土台に、建物と暮らしを守る大規模修繕を、最適な施工方式で実現しましょう。
