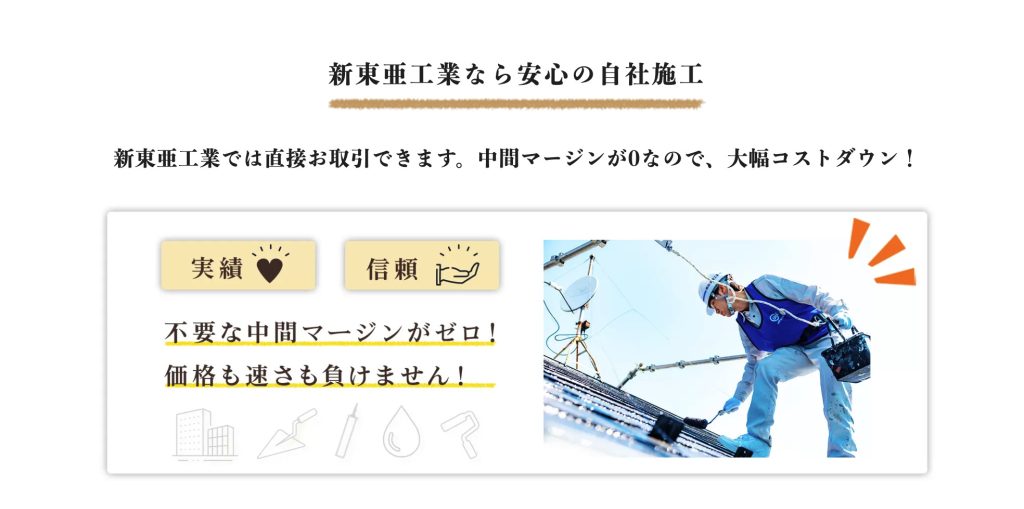マンション改修工事とは? 費用・時期・目的までプロが徹底解説
2025/07/24
マンションの改修工事は、単なる修繕ではなく、快適性や安全性の向上、さらには資産価値の維持・向上を目的とした重要な施策です。
近年では築20年以上のマンションが急増し、住環境や設備の老朽化に悩む管理組合や住民が増えています。
そうした背景から、改修工事の必要性と正しい知識への関心が高まっています。
この記事では、改修工事の基礎知識から費用相場・タイミング・具体的な工事内容・住民対応まで、実際に工事を検討する際に役立つ情報を解説します。
大規模修繕との違いや資金計画の立て方、トラブル回避のポイントについても丁寧に紹介していますので、管理組合の方や所有者にとっての実用的なガイドとしてお役立てください。
大規模修繕・防水工事・外壁塗装のご依頼・メール・お電話でお受け致しております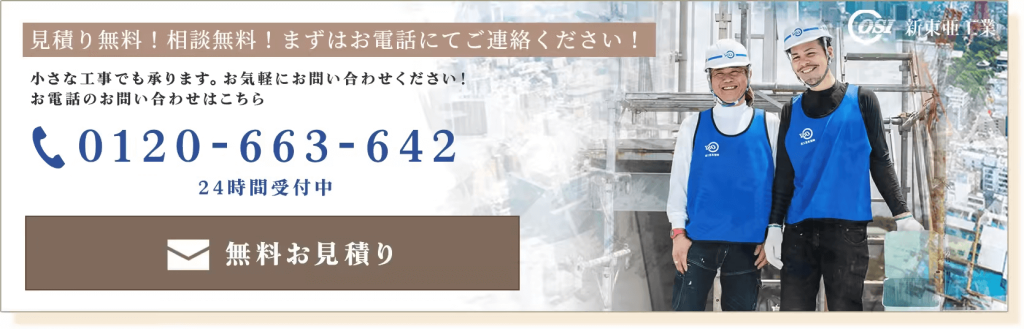
目次
マンションの修繕工事と改修工事の違いとは?
改修工事を正しく理解するには、まず「修繕」との違いを押さえる必要があります。
ここでは、両者の目的・対象・成果の違いを明確にし、改修工事の本質を捉えていきましょう。
修繕工事は「原状回復」が目的
修繕工事は、劣化や破損した部分を元の状態に戻すことを目的としています。
たとえば外壁のひび割れ補修や配管の漏水修理、防水層の再施工などが該当します。
建物の寿命を維持するうえで重要な工事であり、長期修繕計画にも組み込まれる基本的な作業です。
ただし、設備の機能向上や住み心地の改善を目的とするわけではなく、あくまで現状維持にとどまります。
改修工事は「性能や機能の向上」を目的とする
一方で改修工事は、老朽化した設備や構造を改善・刷新し、建物全体の価値を高めることを目的とします。
たとえば、旧式のエレベーターを最新型に入れ替えたり、バリアフリー化のためにスロープや手すりを設置したり、共用部に宅配ボックスを新設する工事などが含まれます。
住環境の快適性や安全性を高め、マンションの資産価値を維持・向上させるために重要な工事です。
マンション改修工事を行うべきタイミングとは?
マンション改修工事を実施する適切なタイミングを逃すと、かえって費用が膨らんだり、住民の満足度が低下する原因になります。
ここでは、改修工事を行うべき時期や判断基準について解説します。
築15~20年を目安に検討するのが理想
一般的に、改修工事の実施は「2回目以降の大規模修繕」と同時期、つまり築15〜20年程度が目安とされています。
これは建物や設備の老朽化が進み、単なる補修では対応しきれない問題が顕在化し始めるタイミングでもあります。
この時期に設備の更新や機能向上を図ることで、住民の満足度を維持しつつ、建物の寿命をさらに延ばすことが可能になります。
建物診断で客観的な判断を下す
改修の必要性は、建物の状態や使用状況によって異なります。
そこで重要になるのが「建物診断」です。
専門業者による外壁・屋上・設備の劣化調査を通じて、現状の性能を把握し、改善すべきポイントを明確にします。
診断結果に基づく計画的な改修は、無駄な工事や過剰な出費を防ぎ、長期的な視点での資産価値維持にもつながります。
マンション改修工事で得られる主なメリット
改修工事は見た目を良くするだけでなく、住民にとっての快適性や安全性、そして建物の価値向上にも大きく貢献します。ここでは、改修工事によって得られる具体的なメリットについて詳しく見ていきましょう。
マンション改修工事で得られるメリット:住み心地の向上と住民満足度のアップ
宅配ボックスの設置やエントランスの自動ドア化・照明のLED化など、日常生活をより便利に快適にするための設備更新は、住民の満足度を大きく高めます。
これにより、空室率の低下や入居希望者の増加といった効果も期待できます。
さらに、共用廊下の滑り止め加工や階段の視認性を高める手すり設置、雨天時の転倒防止策など、日々の安全・快適さに配慮した改修は、居住者の不満解消にもつながります。
また、遮音性や断熱性の向上を図る工事(共用部の窓ガラスの高性能化など)を通じて、日常生活の質を底上げすることも可能です。
こうした細やかな快適性の追求は、マンション全体の居住価値を大きく左右します。
マンション改修工事で得られるメリット:防犯性や防災性の強化による安心感
監視カメラの設置、オートロックの導入、耐震補強や火災報知器の最新化など、安全性を高める工事も重要です。
とくにファミリー層や高齢者の多いマンションでは、これらの施策が資産価値維持とともに安心感を与える要因となります。
たとえば、火災時の初期対応を強化するためのスプリンクラーや非常放送設備の導入、災害時に共用電源を確保できる非常用発電機の設置なども検討対象となります。
また防犯面では、エントランスや駐輪場・ゴミ置き場など、死角になりやすい箇所にセンサーライトやカメラを設けることで、犯罪抑止効果が高まります。
これらの取り組みは、住民の心理的な安心につながるだけでなく、マンションのブランドイメージ向上にも貢献します。
マンション改修工事で得られるメリット:コミュニティの活性化と居住者同士のつながり
もう一つの大きなメリットが、改修をきっかけとした住民同士の交流促進です。
たとえば集会室やキッズスペースの整備、共用ラウンジのリニューアルなどは、住民が自然に集まる場をつくり出します。
これにより、防災意識の共有や防犯の目が行き届く環境づくりにもつながり、管理組合活動の円滑化や長期的な居住志向の醸成にも寄与します。
改修工事は物理的な改善にとどまらず、マンションの「暮らしの質」を根底から高める機会ともいえるのです。
新東亜工業の施工事例|13階建てマンションの大規模修繕工事
東京都内にある13階建てワンオーナーマンションにて、新東亜工業が実施した大規模修繕工事の事例をご紹介します。外壁タイルやシーリング、屋上防水など複数の劣化箇所を総合的に改修し、建物の資産価値を回復しました。
工事概要【工事金額・期間】

工事金額:6,098万円/工期:約5か月間(足場設置〜引き渡しまで)
屋上防水・外壁タイル補修・シーリング打ち替えを中心に、建物全体をバランスよく修繕。
建物全体にわたる一貫した施工により、見た目と性能の両立を実現しました。
建物の劣化とオーナー様のご相談内容
長年手を入れていなかったマンションの修繕を検討し始めたオーナー様から、初回のご相談をいただいたのがスタートでした。
相談のきっかけ
築20年以上が経過し、目視でも劣化が感じられるように。最初は「少し気になる」という段階でしたが、調査を通じて複数の問題が明らかになっていきます。
オーナー様「タイルの剥がれや屋上の汚れが気になっていて…」
担当者「まずは図面を拝見して、現地調査で状態を見ていきましょう」
調査で明らかになった劣化状況
現地での打診調査や目視検査によって、建物の各所に進行した劣化が確認されました。オーナー様も驚かれるほどの症状が浮き彫りに。
屋上防水の劣化
既存の通気緩衝工法によるウレタン防水は、広範囲に劣化や膨れが生じていました。
オーナー様「花火の時期には屋上に上るんです。きれいになると嬉しいな」
現地調査員「眺望も大事ですね。美観にも配慮して施工いたします」
外壁タイルの浮き・剥離
浮きタイルが多数見つかり、剥離の危険性も。劣化の進行度に応じて、張替えと樹脂注入を使い分けました。
担当者「打診調査で見えない内部の浮きも確認しました。対応が必要です」
シーリングの硬化不良
シーリング材は硬化しきって弾性を失い、手作業での撤去が必要なほどでした。
現場職人「カッターが入らないくらい硬くなってます。全部打ち替えですね」
オーナー様「そこまで傷んでたとは…早めにお願いしてよかったです」
工事の流れと透明な対応
調査結果をもとに明確な見積書と診断書を作成。オーナー様に工程を丁寧に説明し、工事中も報告を徹底しました。
診断報告と見積提示
写真付きの診断報告書と、内訳を明記した見積書を提出。工事内容をわかりやすく共有しました。
オーナー様「写真があると素人でもわかりやすいですね」
担当者「透明性を重視していますので、何でもご質問ください」
工事の実施(足場~防水まで)
工程は足場設置から高圧洗浄、下地補修、シーリング、塗装、屋上防水まで。報告写真とともに進捗共有を行いました。
担当者「毎週の報告で進捗をご確認いただけます」
オーナー様「離れてても工事の様子がわかって安心できました」
工事完了後のオーナー様の声
見た目だけでなく機能性も向上した建物に、オーナー様からは満足の声が寄せられました。
オーナー様「すっかりきれいになりましたね。やってよかったです」
担当者「大切な資産を守るお手伝いができて光栄です」
お問い合わせや工事のお見積もり無料!まずはメール・お電話からご相談ください!
マンション改修工事の主な内容と工事項目
改修工事といっても、その範囲や内容はマンションの状況によって大きく異なります。
ここでは、多くのマンションで実施される代表的な改修内容について解説します。
バリアフリー化や共用部の改善
高齢化社会の進行に伴い、エントランスの段差解消や手すり設置、エレベーターの大型化・低床化など、バリアフリー対応のニーズが高まっています。
共用廊下や階段のノンスリップ化や、車椅子対応のスロープ設置などもよく見られる改修工事の一つです。
これらの施策は、高齢者だけでなく、子育て世帯にも安心を提供します。
セキュリティ設備の強化
居住者の防犯意識の高まりに応じて、監視カメラの増設、オートロックやインターホンのリニューアルといったセキュリティ関連の改修も重要です。
これにより、不審者の侵入抑止や居住者の安心感が向上し、マンション全体の価値向上にもつながります。
また、エントランスや共用廊下の照明を明るくするだけでも、防犯効果を高められます。
設備機器の更新や省エネ化
老朽化した給排水管やガス配管、電気設備の更新も改修工事の一環です。
これらの更新により、漏水や火災リスクを軽減し、安全性が向上します。
さらに、LED照明や高効率の給湯器・エアコンなど省エネ設備への更新により、光熱費の削減も実現可能です。
エコ志向の入居者にとっても、これらは魅力ある設備改善となります。
マンション改修工事にかかる費用と資金計画
改修工事を計画するうえで、多くの管理組合や所有者が気にするのが「費用」の問題です。
ここでは、改修工事にかかる費用の目安や、スムーズな資金計画の立て方について解説します。
費用の目安と内訳を把握する
マンションの規模や改修の範囲によって費用は異なりますが、一般的に改修工事は1戸あたり数十万〜百万円単位の費用がかかるケースが多くなります。
たとえば、共用部の設備更新やエントランスの改修であれば、全体で500万〜1,000万円程度が相場です。
費用の主な内訳は以下の通りです。
- 設備費(配管・電気・空調など)
- 建築費(改修に伴う建築作業)
- 設計・監理費(設計会社やコンサルタントへの報酬)
- 仮設工事費(足場・仮設トイレなど)
- 共通仮設費(安全管理・交通整理など)
設備費とは、老朽化した給排水管や電気配線・空調機器などの更新にかかる費用で、安全性の向上やトラブル予防に直結します。
建築費は、共用部の改装やバリアフリー化といった建物構造の改修に伴う施工費です。
設計・監理費は、工事計画の立案や現場監督を行う設計士・コンサルタントに支払う報酬で、施工品質の確保に欠かせません。
仮設工事費は、工事中に必要となる足場の設置や仮設トイレ・シートの準備などの費用を指し、安全で効率的な作業環境を整えるために必要です。
共通仮設費は、現場全体の安全管理や交通整理など、工事の進行を支える基盤的な費用です。
これらの内訳を把握しておくことで、見積もりの妥当性や必要性を適切に判断できます。
資金調達方法と長期修繕計画の連携
資金の多くは修繕積立金から捻出されますが、改修工事は予算を超過するケースも少なくありません。
その場合、一時金徴収や銀行からの借入れ、自治体の補助金活用なども視野に入れる必要があります。
また、長期修繕計画と一体化した形で改修計画を立てることで、費用の平準化や将来的な負担軽減にもつながります。
さらに、改修工事の実施を見据えた積立金の見直しや、住民との合意形成も非常に重要です。
計画初期段階から透明性の高い説明と信頼できるパートナーの選定が、資金計画成功のカギを握ります。
信頼できるマンション改修工事の業者選びのチェックポイント
改修工事の成功は、業者選びにかかっているといっても過言ではありません。
ここでは、業者を選定する際に見るべきポイントや、失敗しないためのチェック項目を紹介します。
建設業許可や実績の確認
まず確認したいのが、業者が「建設業許可」を有しているかどうかです。
特に500万円以上の工事では許可が必要であり、無許可業者による施工はリスクが伴います。
また、マンション改修工事の実績が豊富な業者であるか、同規模・同地域の事例があるかも選定の重要な指標です。
施工事例の写真や内容、住民とのやりとりを丁寧に開示してくれる業者は信頼できます。
複数社からの見積り取得と比較
業者選びでは、必ず3社以上から相見積もりを取ることが重要です。
金額だけでなく、工事項目の明細、仕様の記載の丁寧さ、保証内容などを総合的に比較することで、費用対効果の高い選択が可能になります。
極端に安い見積もりには注意が必要で、後から追加費用が発生するリスクがあります。
説明力と対応力も選定基準に
工事に関する質問への回答が明確かつ丁寧であるか、住民説明会などのサポートがあるかも確認ポイントです。
施工技術だけでなく、住民とのコミュニケーション力が高い業者は、工事中のトラブル回避にも貢献します。
マンション改修工事の流れとスケジュール感
改修工事は、工事内容によっては数ヶ月にも及ぶ大掛かりなプロジェクトです。
スムーズに進行させるためにも、全体の流れとスケジュール感を事前に把握しておくことが大切です。
一般的な改修工事の流れ
- 建物診断・要望ヒアリング
- 改修プランの作成と概算費用提示
- 住民説明会の実施と合意形成
- 詳細設計・実施設計
- 業者選定・見積もり取得
- 工事請負契約の締結
- 着工前説明・仮設工事
- 本工事の実施
- 完了検査と引き渡し
一般的な改修工事には、3〜6ヶ月程度を要します。
住民の生活に影響を与える場合があるため、工期中は丁寧な配慮と情報共有が欠かせません。
マンション改修工事でよくある質問
【Q1】改修工事と大規模修繕工事の違いは?
A. 改修工事は機能や性能の向上を目的とし、大規模修繕は原状回復が主な目的です。設備更新やバリアフリー化などは改修工事に該当します。
【Q2】改修工事は必ず実施しなければいけませんか?
A. 法的な義務はありませんが、資産価値や安全性、住環境の維持のためには推奨されます。
【Q3】工事期間中の生活はどうなりますか?
A. 騒音や一時的な共用部の使用制限がありますが、事前の説明とスケジュール調整により最小限の影響で済むよう配慮されるのが一般的です。
【Q4】補助金の活用は可能ですか?
A. 一部の自治体では、省エネ改修やバリアフリー対応などを対象とした補助制度があります。地域の制度を調べて活用しましょう。
【Q5】積立金だけでは足りない場合は?
A. 一時金徴収や金融機関からの借入れで対応可能です。ただし、事前の計画と住民の合意が不可欠です。
【Q6】改修工事後の保証はありますか?
A. 多くの業者が施工箇所に応じた保証制度を設けています。契約時に必ず確認しましょう。
【まとめ】マンション改修工事で建物の未来を守ろう
マンションの改修工事は、単なる修繕にとどまらず、快適性や安全性、資産価値の向上を図る重要なプロジェクトです。
築15〜20年を目安に建物診断を実施し、適切なタイミングでの計画立案が、コストと住民満足度の両面で大きな成果をもたらします。
成功のカギは、「正しい知識」「信頼できる業者の選定」「透明性のある資金計画」にあります。
管理組合や所有者は、長期修繕計画と連動した改修戦略を立てることで、将来にわたる安心と資産価値の維持が可能となります。
この記事を通じて、改修工事の全体像を把握し、より良いマンション管理にお役立ていただければ幸いです。