
区分所有法から大規模修繕工事を紐解く!決議要件や費用分担などをわかりやすく紹介
2025/07/24
マンションの大規模修繕工事は、区分所有者全員の財産に直結する重要なテーマです。外壁や屋上といった共用部分は、年月の経過とともに必ず劣化し、修繕や更新を避けて通ることはできません。
しかし実際に工事を進めようとすると「区分所有法では大規模修繕は義務付けられているのか?」「どのような決議手続きが必要なのか?」「工事費用は誰がどのように負担するのか?」といった法律上の疑問に直面します。特に管理組合の役員や理事に就任した方にとって、こうしたルールを理解しておくことは、余計なトラブルを防ぎ、住民全体の合意形成をスムーズに進めるうえで不可欠です。
本記事では区分所有法に焦点を当て、大規模修繕工事に関連する主要条文や決議要件、費用分担の仕組みを徹底的に解説します。また、反対者がいる場合の法的対応や、標準管理規約との位置づけの違いなども整理し、マンション修繕に携わる方が実務で直面する疑問を解決できるようにまとめましたので、ご覧ください。
目次
区分所有法と大規模修繕工事の関係
マンションの大規模修繕における法律として、よく耳にするのが区分所有法ではないでしょうか。区分所有法は「建物の区分所有等に関する法律」の正式名称を持ち、共同住宅における所有権や管理権、費用負担の原則を定めた法律です。マンションの管理・修繕の基本的なルールは、基本的にこの法律に規定されています。
ここでは、区分所有法の目的や大規模修繕に関連する主要条文などから関係性についてみていきましょう。
区分所有法の目的
区分所有法は、1棟の建物を複数人で所有・利用する場合に、区分所有者の権利と義務を調整し、建物全体を安全かつ円滑に維持・管理することを目的としています。
マンションは一人ひとりが専有部分を所有する一方で、外壁や屋根、廊下やエレベーターといった共用部分を共同利用しています。こうした共用部分を適切に管理するためには、明確なルールがなければ、修繕の要否や費用負担を巡って混乱が生じるのは必至です。
そのため区分所有法は、共用部分の保存行為や変更行為に関して明確な決議要件を設けています。大規模修繕工事はまさにこの「共用部分の保存」に関わるため、法律に基づいて実施されるべき行為といえるのです。
大規模修繕に関連する主要条文
区分所有法にはさまざまな条文がありますが、第17条と第18条が大規模修繕に関する内容として知られています。
第17条:共用部分の変更
共用部分の形状や効用を著しく変更する場合には、区分所有者および議決権のそれぞれ4分の3以上という特別多数決議が必要。例えばエレベーターの増設や外観の大規模な変更はここに該当します。
第18条:共用部分の管理
共用部分の保存・維持・管理は区分所有者全員の責任と定められています。通常の修繕や補修は区分所有者および議決権の過半数による普通決議で決めることが可能です。外壁塗装や屋上防水など、日常的な維持行為はこの条文を根拠として実施されます。
共用部分と専有部分の違い|区分所有法に基づいた工事を進めるために
大規模修繕の対象となる範囲を理解するには、共用部分と専有部分を区別することが不可欠です。
| 区分 | 範囲 | 特徴 | 大規模修繕の対象 | 費用負担 |
|---|---|---|---|---|
| 共用部分 | 外壁、屋上、廊下、階段、エントランスホール、配管、エレベーターなど | 全区分所有者が共同で使用 | 対象となる | 区分所有者全員で持分割合に応じて分担 |
| 専有部分 | 各住戸の内部、玄関ドアの内側、窓ガラスの内側など | 各区分所有者が単独で使用 | 原則対象外(ただし工事の影響を受ける場合あり) | 各所有者が自己負担で管理 |
このように共用部分と専有部分を明確に区分することが、大規模修繕工事を法律に基づいて適切に進める第一歩となります。
参考元:e-Gov「建物の区分所有等に関する法律」
大規模修繕工事は法律で義務?
「マンションは一定年数ごとに必ず大規模修繕を行うことが法律で義務付けられている」と誤解している方は少なくありません。しかし区分所有法には「大規模修繕を○年ごとに行うこと」といった具体的な義務規定は存在していません。
ここでは、大規模修繕工事は法律で義務付けられているのかに着目しながら、大規模修繕工事を実行するタイミングに関する内容を紹介します。
法律上の義務は明記されていない
区分所有法には大規模修繕を直接義務付ける条文はなく、周期も明示されていません。そのため、単に年数が経過しただけで工事を強制されることはありません。
第18条の「保存行為」としての修繕
しかし第18条は「共用部分の保存行為は区分所有者全員の責任」と規定しています。雨漏りの修繕や外壁の補修、屋上防水など建物の安全性を確保するための行為は、保存行為に該当します。
大規模修繕工事はこれら保存行為の延長線上にあり、区分所有法上、管理組合が責任を持って取り組むべき行為と解釈されています。つまり直接の義務規定はなくても、実質的には「行わざるを得ない工事」であるといえます。
実務上の必要性とガイドライン
国土交通省が公表している「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」では、12~15年を目安に大規模修繕を実施することを推奨しています。これは法律の強制規定ではありませんが、建物の劣化状況や資産価値の維持を考慮した現実的な基準とされています。
実際、長期間修繕を行わずに放置すると、雨漏りやタイル剥落など重大な不具合が生じ、修繕費用がかえって膨らむリスクがあるため、ガイドラインに従った周期的な修繕は社会的に必要不可欠とされています。
参考元:e-Gov「建物の区分所有等に関する法律」
参考元:国土交通省「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」
大規模修繕工事の決議要件|区分所有法第17条・第30条
大規模修繕工事を進めるには、管理組合の総会で決議を行う必要があります。区分所有法は工事の性質に応じて決議の種類と要件を定めています。この決議要件を理解していないと、総会での手続きが無効となり、後に工事の正当性が争われる可能性があるため注意が必要です。
ここでは、大規模修繕工事の決議要件として区分所有法第17条・第30条に関する内容を紹介します。
通常決議(過半数)と特別決議(4分の3以上)
大規模修繕工事の決議要件については、区分所有法第17条・第30条で以下のように記載されています。
通常決議(第30条)
出席者の議決権および区分所有者数の両方で過半数の賛成を得ることで成立します。外壁塗装や屋上防水など保存行為はこの通常決議で決定できます。
特別決議(第17条)
建物の形状や用途に著しい変更を加える場合には、区分所有者および議決権のそれぞれ4分の3以上の賛成が必要です。耐震補強やエレベーター増設などが該当します。
通常決議と特別決議のまとめ
| 決議の種類 | 条文 | 必要な賛成割合 | 主な対象工事 |
|---|---|---|---|
| 通常決議 | 第30条 | 区分所有者数・議決権の過半数 | 外壁塗装、防水工事、タイル補修など保存行為 |
| 特別決議 | 第17条 | 区分所有者数・議決権の4分の3以上 | 耐震補強、エレベーター増設、用途変更を伴う工事 |
大規模修繕はどちらに当たるか?
- 通常決議で足りる場合:外壁塗装、防水工事、タイル補修など。
- 特別決議が必要な場合:外観デザインを大幅に変える改修、用途変更を伴う工事。
議決権割合の重要性
決議要件は単なる人数の多数決ではなく、議決権割合も重要な基準となります。議決権は原則として専有部分の床面積割合に基づいて割り当てられるため、広い住戸を所有する人ほど議決権が大きくなります。
このため、少数の大口区分所有者が総会決議に大きな影響を与える可能性があります。実務では「人数」と「議決権割合」の両方で多数を得る必要があるため、合意形成の難易度が高まる点に注意が必要です。
参考元:e-Gov「建物の区分所有等に関する法律」
修繕費用の分担ルール|区分所有法第19条
大規模修繕工事において最も重要かつ関心を集めるテーマのひとつが「費用をどのように分担するのか」という問題です。金額が大きくなる大規模修繕では、費用の取り扱いに納得感を得られないと住民間のトラブルに発展しやすいため、区分所有法に基づいた正しい知識が必要不可欠です。
区分所有法はこの点について明確なルールを定めており、その理解が工事成功の鍵を握ります。
費用は区分所有者全員で負担
区分所有法第19条は「共用部分の管理に要する費用は区分所有者がその持分に応じて負担する」と定めています。大規模修繕工事は共用部分の保存・管理に直結するため、すべての区分所有者が費用を負担する義務を負います。
例えば、外壁塗装や屋上防水の修繕費は、特定の階や住戸のみに限定されるものではなく、建物全体に関わるため全員での負担が求められます。これは「利用するか否か」ではなく「所有者であるか否か」に基づく考え方であり、マンションという共同住宅の基本原理を反映した仕組みです。
持分割合と負担割合の例
| 区分所有者 | 専有面積 | 持分割合 | 負担額(仮定:工事費1,000万円) |
|---|---|---|---|
| Aさん | 80㎡ | 8% | 80万円 |
| Bさん | 60㎡ | 6% | 60万円 |
| Cさん | 40㎡ | 4% | 40万円 |
持分割合と負担割合
持分割合は、原則として各専有部分の床面積割合に基づき算出されます。広い住戸を所有する人はその分持分が大きく、負担額も高くなります。
一方、狭い住戸の所有者は負担額が少なくなります。この仕組みは公平性を担保するものですが、しばしば「使用していない設備にまで支払うのは不公平ではないか」といった誤解を招きます。しかし区分所有法の趣旨は、建物全体を適切に維持し続けるための共同責任であり、部分的な利用の有無ではなく所有権に基づく責務である点を理解することが大切です。
修繕積立金不足時の対応
修繕積立金が不足した場合、管理組合は一時金を徴収する決議を行う必要があります。通常決議で決定するのが一般的ですが、区分所有者にとっては負担が重くのしかかるため、反発が起こることも少なくありません。そのため日頃から計画的に修繕積立金を積み立て、国交省のガイドラインに基づいた長期修繕計画を策定しておくことが望まれます。
また、金融機関からの借入れや補助金制度の活用といった選択肢を検討するケースもあり、資金調達の多様化が実務上の課題となっています。
参考元:e-Gov「建物の区分所有等に関する法律」
大規模修繕工事でお悩みの管理組合の方
「ファシリテーション」で談合をなくそう!
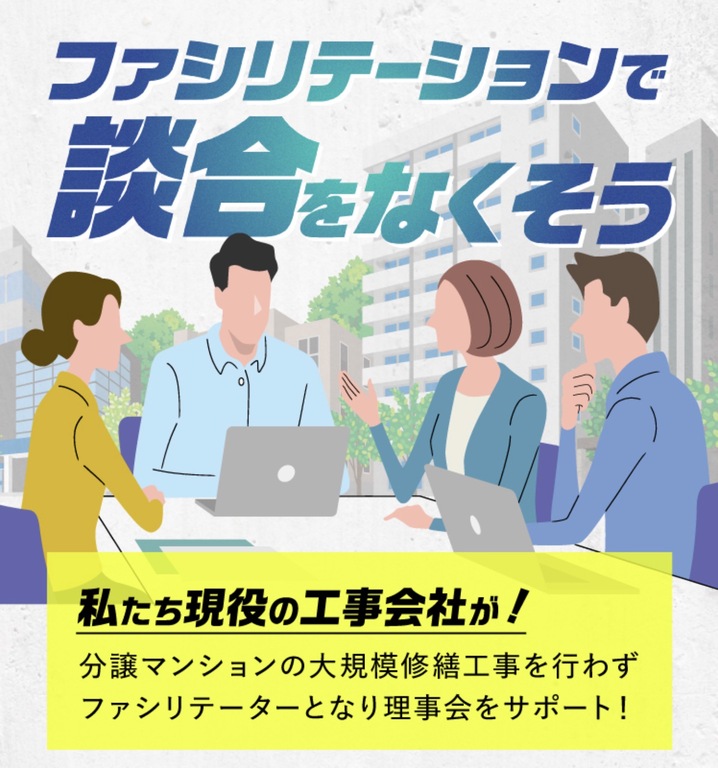
\お問い合わせや工事のお見積もり無料!/
豊富な実績と専門知識を持つスタッフが、
皆様の疑問や不安にお答えし、最適な解決策をご提案いたします。
工事反対者の法的取り扱い|区分所有法第47条
大規模修繕工事は金額も影響範囲も大きいため、すべての区分所有者が必ずしも賛成するわけではありません。中には「工事の必要性を感じない」「費用が高すぎる」といった理由で反対する住民も存在します。
こうした場合にどのように対応するかは、区分所有法の重要な論点のひとつです。
少数反対者と多数決原理
区分所有法の基本は多数決原理であり、総会で適法に成立した決議は、反対者を含む全区分所有者を拘束します。つまり一部の反対があったとしても、決議要件を満たせば工事は実施可能です。
この仕組みによってマンションの維持管理が停滞するのを防ぎ、建物全体の利益を守ることが可能となります。
区分所有法第47条の規定
第47条は「区分所有者が共同の利益に反する行為をした場合、管理組合はその行為の差止めや、場合によっては専有部分の使用禁止を請求できる」と規定しています。
大規模修繕に合理的な理由なく反対し続け、工事の妨害や妨害行為を行うようなケースでは、この規定を根拠に法的措置を講じることが可能です。共同利益を害する行為として、裁判所が介入する余地があるのです。
判例から見る反対者対応
過去の判例では「建物の安全性確保や資産価値維持に必要な修繕を拒否することは、共同利益に反する」として、裁判所が工事実施を認めた事例もあります。つまり、合理的な理由を欠いた反対は法的に受け入れられにくいのが実情です。
ただし、費用の算定根拠や業者選定に問題がある場合など、正当な理由がある反対意見については無視できません。そのため管理組合は、反対者への説明責任を果たし、透明性を確保することで不要な紛争を避けることが重要です。
参考元:e-Gov「建物の区分所有等に関する法律」
標準管理規約と区分所有法の違い
マンション管理の現場では「標準管理規約」という用語が頻繁に登場します。国土交通省が策定したこのモデル規約は、多くのマンションで採用されていますが、区分所有法とは性質が異なるため両者を混同しないことが大切です。
ここでは標準管理規約と区分所有法の違いとして、標準管理規約の位置づけや区分所有法が優先される原則・実務での活用などを紹介します。
標準管理規約の位置づけ
標準管理規約は、あくまで参考となる「モデルケース」です。法的拘束力はなく、各マンションが自らの事情に合わせて管理規約を定める際の指針として機能します。
そのため、標準管理規約の内容がそのまま適用されるわけではなく、マンションごとに修正や追加が行われるのが一般的です。
区分所有法が優先される原則
区分所有法は国の法律であり、標準管理規約よりも優先されます。もし管理規約が区分所有法に抵触する内容であった場合は、法律の規定が優先され無効となります。
したがって、実務上は管理規約の内容を精査する際に「区分所有法と矛盾していないか」を確認することが重要です。管理規約はあくまで区分所有法を補完する存在であり、法律を超える権限を持つものではありません。
実務での活用
標準管理規約は、法律では詳細に定められていない部分を補う役割を果たします。たとえば、修繕積立金の積立方式、総会の議事運営方法、役員の任期や選任方法などです。これにより、実際の管理運営がスムーズになり、住民間の認識の統一が図られます。
ただし、標準管理規約をそのまま採用するのではなく、各マンションの実情に合わせて適切に修正・適用することが望まれます。標準管理規約と区分所有法を両輪として理解し、現場での適用をバランスよく行うことが円滑なマンション管理につながります。
参考元:国土交通省「マンション標準管理規約(単棟型)」
区分所有法を踏まえた大規模修繕の手続き
区分所有法を正しく理解することで、大規模修繕工事を円滑に進めることができます。特に法律に基づいた手続きを踏むことは、工事の正当性を確保し、住民間のトラブルや後々の訴訟リスクを避けるために欠かせません。
ここでは、区分所有法に沿った修繕工事の一般的な手続きと実務で注意すべきポイントを整理します。
長期修繕計画の策定
法律上、長期修繕計画の作成が義務付けられているわけではありません。しかし、区分所有法第18条に基づく「保存行為」の責任を果たすためには、あらかじめ計画を策定しておくことが極めて重要です。長期修繕計画を整備することで、工事の必要時期や資金計画を明確にでき、住民全体の合意形成を促進することができます。
さらに、計画をもとに修繕積立金の額を調整することも可能になり、突発的な一時金徴収のリスクを軽減できます。国交省の指針でも、長期修繕計画を定期的に見直すことが推奨されており、法的義務がなくとも事実上不可欠な準備といえるでしょう。
総会での議決
大規模修繕を実施する際には、必ず管理組合の総会で決議を行う必要があります。工事の内容が保存行為にあたる場合は通常決議(過半数)で足りますが、建物の用途や形状を変更する場合は特別決議(4分の3以上)が求められます。
議事録は必ず作成し、適法な手続を経たことを記録に残しておくことが大切です。議事録の不備は、後に決議の有効性を争う際に問題となる可能性があるため、慎重に対応する必要があります。
業者選定と契約
区分所有法そのものには業者選定方法の規定はありませんが、透明性のある手続きを行うことが、区分所有者からの信頼を得るために重要です。複数の業者から相見積もりを取り、内容や価格、保証条件などを比較検討したうえで総会に諮るのが望ましいでしょう。
また、契約時には契約条件を明確にし、工期や費用、保証内容を文書で残しておくことが後のトラブル防止につながります。弁護士や建築士といった専門家に契約書を確認してもらうことも有効です。
工事実施と監理
工事が始まると、管理組合が区分所有者全員の代表として責任を負います。施工中の安全確保や騒音・振動への配慮、工期や品質の監理は、区分所有法の「保存行為」に基づく責務の一部です。監理者を置いて第三者的な視点から工事の品質をチェックすることも推奨されます。
工事後には竣工検査を実施し、不具合があれば速やかに是正を求めることが、住民の利益を守るうえで欠かせません。
参考元:e-Gov「建物の区分所有等に関する法律」
よくある法律上の質問(FAQ)
大規模修繕工事を進めるうえで、区分所有法をある程度把握しておくことは重要です。
ここでは理解を深めるのに役立つ情報として、区分所有法に関するよくある質問を紹介します。
Q1. 区分所有法で大規模修繕は義務ですか?
A. 法律には「○年ごとに大規模修繕を実施しなければならない」といった直接的な規定は存在しません。
しかし第18条により、共用部分の保存行為は全区分所有者の責任とされているため、実質的には大規模修繕を怠ることは許されません。放置すれば建物の安全性が損なわれ、管理組合が責任を問われる可能性もあります。
Q2. 通常決議と特別決議の境目はどこですか?
A. 保存行為にとどまる修繕(外壁塗装や防水工事など)は通常決議で足ります。一方で、建物の効用や外観を大きく変えるような工事(耐震補強や増築など)は特別決議が必要です。
この線引きはトラブルになりやすいため、事前に弁護士や専門家に相談するのが安全です。
Q3. 修繕積立金が足りないときはどうすればいいですか?
A. 一時金の徴収、金融機関からの借入れ、補助金制度の活用といった方法が検討できます。
いずれの場合も総会決議が必要であり、特に一時金徴収は区分所有者への影響が大きいため丁寧な説明が欠かせません。補助金や助成金は自治体によって内容が異なるため、事前の情報収集も大切です。
Q4. 工事に反対する所有者がいたら工事はできませんか?
A. 総会で必要な決議要件を満たせば、反対者がいても工事は実施できます。合理的な理由のない反対は「共同の利益に反する行為」とされることもあります。
ただし、反対者の意見を無視するのではなく、十分な説明を尽くすことが望ましいです。合意形成の過程そのものが、工事後のトラブルを避けるために重要となります。
Q5. 管理規約と区分所有法が矛盾した場合はどちらが優先されますか?
A. 区分所有法が優先されます。管理規約は区分所有法を補完する役割に過ぎず、法律に反する規定は無効です。
したがって管理規約を策定する際には、必ず法律との整合性を確認する必要があります。
区分所有法に沿った大規模修繕で工事を成功に導く|まとめ
マンションの大規模修繕工事は、単なる建物の修繕にとどまらず、区分所有法という法的枠組みに基づいて進められる共同事業です。
区分所有法には「保存行為としての修繕」「通常決議と特別決議の区別」「持分割合に応じた費用負担」「反対者への対応」など、大規模修繕の実務に直結する規定が数多く存在します。これらを正しく理解し、適用することで管理組合は法的に有効な決議を行い、住民全体の合意を得たうえで工事を進めることが可能になります。
大切なのは、法律に従った正しい手続きと、住民全体の納得を得られる合意形成です。透明性を確保し、説明責任を果たしながら、長期修繕計画をベースに資金面・工期面を調整していくことで、建物の安全性と資産価値を長期にわたり守ることができます。区分所有法を理解し、積極的に活用することこそが、大規模修繕工事を成功に導く最大のポイントだといえるでしょう。








