
パラペット防水工事とは?費用・工法・業者選びまで徹底解説
2025/07/24
パラペットの防水工事を検討する際、まず知っておきたいのが各工法の特徴です。ひと口に防水といっても、施工方法や使用する材料によって仕上がりや耐久性、費用に大きな差があります。工法ごとに得意・不得意があるため、建物の状態や形状、既存防水層の種類、そして将来的なメンテナンスのしやすさまで含めて慎重に選定する必要があります。
この記事では、代表的なパラペット防水工法を取り上げ、それぞれのメリット・デメリットを詳しく解説します。どの工法が自分の建物に合っているのかを見極める判断材料として、ぜひ参考にしてください。
目次
- 1 パラペットとは?基本知識や役割を解説
- 2 パラペットが雨漏り原因になる4つの理由|防水工事で対処しよう!
- 3 パラペット防水における主な工事内容|工法別の比較一覧表
- 4 パラペット防水の各工法のメリット・デメリットと選び方
- 5 パラペット防水工事の費用相場|㎡単価と工法別に解説
- 6 実録!新東亜工業の施工事例|2階建て戸建の屋上防水工事
- 7 パラペットの防水工事などメンテナンス方法と最適なタイミング
- 8 パラペット防水工事の施工手順と工期の目安
- 9 防水保証と施工後のアフターサービスとは?
- 10 パラペット防水工事で業者選びで失敗しないためのチェックリスト
- 11 戸建て・マンション・ビルで異なるパラペット防水の注意点
- 12 パラペット防水工事でよくある質問(FAQ)
- 13 パラペット防水工事で建物の寿命を守ろう|まとめ
パラペットとは?基本知識や役割を解説
パラペットとは、屋上やバルコニーなどの外周部に設けられた立ち上がり部分の壁を指します。一般的にはコンクリートやモルタル、金属などで構成されており、建物の縁に沿って水平に設置されています。パラペットの最大の役割は、安全性の確保と防水性能の補強です。人が屋上で作業を行う際や、強風・落下物などから屋根を保護するためのバリアとして機能し、また雨水の侵入を防ぐための重要な構造部分でもあります。
さらに、建築デザインの一部として意匠性を高める役割も果たし、外観の印象を大きく左右します。ただし、常に外気にさらされていることから、劣化や破損が起きやすく、定期的なメンテナンスや防水対策が必要とされる箇所でもあります。特に防水層との取り合い部分は雨漏りリスクが高いため、専門的な診断と適切な施工が欠かせません。
パラペットの主な役割
- 転落防止(安全性の確保)
- 雨水・風雨の侵入を抑える
- 建物の外観にアクセントを加える
ただし、このパラペット部分の防水が不十分、もしくは経年劣化により破損したまま放置すると、そこから雨水が侵入し、内壁や構造材を腐食させてしまう恐れがあります。
パラペットが雨漏り原因になる4つの理由|防水工事で対処しよう!
パラペットは外気に常にさらされており、風雨や紫外線の影響を直接受けます。以下のような原因で雨漏りを引き起こすことがよくあります。
パラペットが雨漏りの原因となる理由1.シーリング材の劣化
パラペットと外壁との取り合い部や笠木の継ぎ目には、シーリング材(コーキング)が使われています。これが劣化すると隙間が生じ、水の侵入経路となってしまいます。
パラペットが雨漏りの原因となる理由2.笠木の浮き・外れ
パラペットの上部には「笠木(かさぎ)」と呼ばれる仕上げ材が設置されています。これが浮いたり外れたりすると、そこから雨水が侵入する恐れがあります。
パラペットが雨漏りの原因となる理由3.排水不良や水たまりの発生
パラペット周辺の勾配設計が不十分な場合、水が排水されず溜まりやすくなり、防水層の膨れや破断の原因になります。
パラペットが雨漏りの原因となる理由4.施工不良
新築時やリフォーム時の施工が不適切であると、目地処理や防水シートの貼り付けが甘く、経年劣化を待たずに雨漏りが発生してしまうこともあります。
パラペット防水における主な工事内容|工法別の比較一覧表
パラペットの防水工事には、部位や症状に応じてさまざまな工法が選ばれます。下記は代表的な防水方法とその特徴をまとめた比較表です。
| 工法名 | 特徴 | 耐用年数 |
|---|---|---|
| シーリング再施工 | コーキング材を打ち替え | 5〜10年 |
| 笠木の交換 | 金属やアルミ笠木の交換 | 10〜15年 |
| ウレタン塗膜防水 | 液体状の樹脂を塗る | 10〜12年 |
| シート防水(塩ビ系) | シートを貼り防水層を形成 | 12〜15年 |
工法選定は、パラペットの劣化具合、既存の下地、防水層の種類などによって異なります。適切な診断を受けたうえで、最適な工法を選びましょう。
パラペット防水の各工法のメリット・デメリットと選び方
パラペット防水には複数の工法があり、それぞれに異なる特徴や適性があります。ここでは、代表的な防水工法について、メリットとデメリットを整理し、どのような状況にどの工法が適しているのかを分かりやすく解説します。
建物の形状や劣化状況、予算や施工後のメンテナンス性を踏まえて、最適な選択を行う参考にしてください。
パラペット防水|工法シーリング再施工
既存のシーリング材が劣化している場合に行うのがシーリング再施工です。ひび割れや隙間が生じた箇所に新たにコーキング材を打ち直すことで、防水性を回復させます。比較的安価で短期間の施工が可能なため、軽微な劣化への対処に向いています。ただし、劣化が進んでいる場合には根本的な解決にはならず、あくまで応急処置的な対応となる点には注意が必要です。
- メリット:比較的安価で対応可能
- デメリット:劣化が進行している場合は応急処置にとどまる
パラペット防水|笠木交換
パラペットの最上部に取り付けられる「笠木」は、雨水の浸入を防ぐ最前線です。笠木自体の劣化や浮きが雨漏りの直接原因になることも多く、交換は根本的な対策となります。アルミやガルバリウムなどの金属製笠木に交換することで、耐久性を高めることが可能です。ただし、高所作業となるため足場の設置が必要になるケースが多く、工事費用が高額になる傾向があります。外観も刷新されるため、建物のリフレッシュを兼ねたリフォームにも適しています。
- メリット:雨水侵入の根本対策になる
- デメリット:足場が必要なケースもあり費用が高くなる傾向
パラペット防水|ウレタン塗膜防水
ウレタン塗膜防水は、液体状のウレタン樹脂を塗布して防水層を形成する工法で、特に複雑な形状のパラペットに適しています。継ぎ目のない一体成形が可能なため、美観に優れ、仕上がりも滑らかです。また重ね塗りによる補修も容易な点が特徴です。一方で、施工の際に防水層の厚みを均一に仕上げるには職人の技術が求められます。施工者の技量によって品質が左右されやすく、信頼できる業者選びが重要となります。
- メリット:複雑な形状にも施工可能/継ぎ目がなく美観が良い
- デメリット:厚み管理が難しく、施工品質に依存する
パラペット防水|シート防水(塩ビ系)
塩ビシート防水は、防水性の高い塩化ビニルシートをパラペットの表面に貼り付けて施工する方法です。耐久性・耐候性に優れており、安定した品質が期待できます。施工スピードが速く、工期を短縮したい現場にも適しています。ただし、シート自体は平滑な面への施工を前提としているため、凹凸の多い箇所や複雑な構造には向きません。特に端部処理が甘いと漏水リスクがあるため、丁寧な納まりが求められます。
- メリット:施工期間が短い/耐候性に優れている
- デメリット:複雑な形状には不向き/端部処理に注意が必要
選定時には「パラペットの状態」と「予算」「建物の築年数」「施工後の維持管理」を総合的に判断することが大切です。
パラペット防水工事の費用相場|㎡単価と工法別に解説
パラペットの防水工事にかかる費用は、工法や建物の状況、足場の有無などによって大きく変動します。ここでは、代表的な防水方法ごとの費用目安を表にまとめ、相場感を把握しやすくしています。
| 防水工法 | ㎡単価(税別) | 特徴 |
|---|---|---|
| シーリング再施工 | 約1,000〜2,500円 | 築浅物件や部分補修向き |
| 笠木の交換 | 約5,000〜10,000円 | 劣化が激しい場合に有効 |
| ウレタン塗膜防水 | 約5,000〜8,000円 | 一体成型で美観に優れる |
| 塩ビシート防水 | 約6,000〜9,000円 | 耐久性に優れメンテ性も高い |
パラペット防水工事の費用相場の目安としては、シーリング再施工で1,000〜2,500円/㎡、笠木交換は5,000〜10,000円/m、ウレタン塗膜防水が5,000〜8,000円/㎡、塩ビシート防水は6,000〜9,000円/㎡程度です。
建物の状況や劣化の程度によっては追加工事が必要になることもあるため、実際の工事金額を把握するには現地調査と見積もりの取得が不可欠です。
パラペット防水の費用に影響する主な要因
- 施工範囲の広さ:面積が大きいほど単価は下がる傾向があります
- 足場の必要性:高所作業では足場費用が5万〜30万円前後発生
- 劣化の程度:既存防水層の撤去・下地処理の有無によって変動
- 施工環境:狭小地や接道条件により搬入・作業費が増加
正確な費用を知るためには、現地調査に基づく見積もり取得が不可欠です。複数社からの相見積もりを取ることで、適正価格かどうかを判断しやすくなります。
実録!新東亜工業の施工事例|2階建て戸建の屋上防水工事
夏になると屋上階が非常に暑くなる――。そんなお悩みから始まった今回のご相談。前回のウレタン防水から約5年が経過しており、再施工の必要性を見極めたいというお問い合わせをいただきました。現地調査の結果、防水性能には大きな問題が見られなかったものの、「夏の暑さをなんとかしたい」というご要望を受けて、遮熱機能付きの塗料を用いたウレタン防水をご提案。適切な施工時期の判断と、目的に合ったご提案によって、満足度の高い工事となりました。
ご相談内容
屋上の防水機能に不安を感じていたお客様から、メールでのお問い合わせをいただいたことがきっかけでした。前回の工事から5年が経過し、表面の劣化が気になるとのこと。また、夏場の屋上階の暑さに悩まされており、遮熱対策についてもご相談がありました。
担当者:現地調査をしたところ、まだ防水層は機能しています。ただ、トップコートの劣化があり、遮熱機能のあるトップコートへの塗り替えを検討されるのは良い判断です。
お客様:無理に工事を勧められるのかと思ってましたが、正直に見ていただけて安心しました。暑さ対策になるならやりたいです。
工事の概要|工事金額と期間
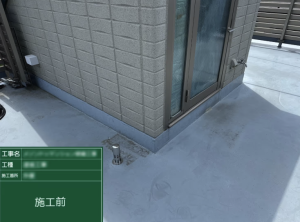
屋上防水工事 施工前

屋上防水工事 施工後
工事の内容が以下のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 建物種別 | 2階建て戸建住宅 |
| 所在地 | 東京都(詳細非公開) |
| 工事内容 | 屋上防水工事・遮熱塗装 |
| 工法 | ウレタン塗膜防水(通気緩衝工法)+遮熱塗装 |
| その他特記事項 | 遮熱効果を考慮し屋根塗装も実施、日曜作業許可取得、近隣対応あり |
工事金額:74万円/施工期間:9日間
現地調査で判明した劣化症状
5年前に施工された防水層は機能を保っていましたが、トップコートの色あせやディスク部のひび割れが確認されました。ただし、雨漏りや重大な損傷は見られず、急を要する状況ではありませんでした。
担当者:正直、今すぐやる必要はありません。ただ、暑さ対策をしたいというご要望には応えられます。
お客様:工事しないという選択肢も提示してもらえるなんて思わなかったです。本当に暑いので、やっぱりお願いします。
施工中のやり取りと配慮
施工に先立ち、色の選定や工程説明、資材置き場・電気・水道使用について丁寧に打ち合わせを行いました。工事中は毎日の進捗報告や中間検査も実施され、終始スムーズに進行しました。お客様から職人への労いの言葉があったことも印象的でした。
お客様:暑い中での作業、本当にありがとうございます。
担当者:ありがとうございます。できるだけ音の出ない作業で日曜も進めさせていただきますね。
引き渡し時のご感想
施工後の屋上や屋根の表面を実際に触っていただいたところ、「前と全然違う!」とその遮熱効果を実感していただきました。また、見積外だったシーリング部の劣化箇所もサービス対応し、ご満足いただけました。
お客様:触ってみたら本当に前より熱くないですね。こんなに変わるんですね!
担当者:必要以上の施工はおすすめしません。ご満足いただけて嬉しいです。
今回の工事は「防水層の更新」が目的ではなく、「夏の暑さを和らげるための遮熱対策」が主眼でした。必要な提案だけを行い、お客様の予算やご希望に応じた最適な施工を提供する――それが新東亜工業の強みです。信頼関係を築けたからこそ、サービス施工や柔軟な対応も可能となり、高い満足度につながりました。
パラペットの防水工事などメンテナンス方法と最適なタイミング
パラペットは、風雨や紫外線にさらされやすく劣化が進行しやすい部位です。早期に劣化を発見し、定期的にメンテナンスを行うことで、雨漏りや大規模修繕のリスクを軽減できます。
パラペットの防水工事のメンテナンスポイント
- 3〜5年に1度の目視点検(ひび割れ・膨れ・汚れ)
- シーリング部の弾力性チェック(押して戻らない・ひびあり)
- 笠木の浮き・ズレ確認
- 排水経路の清掃(詰まりやコケの発生を防止)
メンテナンスの種類
| 種別 | 内容 | 実施目安 |
|---|---|---|
| 簡易補修 | シーリングの打ち直し、防水塗料の塗布など | 3〜5年ごと |
| 部分改修 | 笠木の交換、防水層の再施工 | 7〜10年ごと |
| 全面改修 | 下地からやり直す大規模工事 | 15〜20年ごと |
劣化を放置してしまうと、補修範囲が広がり結果的に費用がかさむため、早期対応が何よりのコスト削減策となります。
パラペット防水工事の施工手順と工期の目安
防水工事はどのような流れで進むのか、工期はどれくらいかかるのかを事前に把握しておくと安心です。ここでは一般的なパラペット防水工事の流れと、工法ごとの工期目安について解説します。
パラペット防水工事の一般的な施工の流れ
- 現地調査・劣化診断:建物の状態を確認し、工法を選定
- 見積もり提出・契約:工事内容・金額・スケジュールを明示
- 足場設置(必要な場合):安全な作業環境を確保
- 既存防水層やシーリングの撤去:劣化部材を除去
- 下地処理・清掃:密着性を高めるための作業
- 防水材の施工:工法に応じて塗布または貼付
- 乾燥・硬化期間:材質により数日から1週間程度
- 完了検査・片付け:仕上がりと漏水チェック
詳しく解説していきます。
現地調査・劣化診断
施工の第一歩は、現地調査と劣化診断です。建物の立地や構造、パラペットの形状や既存防水層の状態を細かく確認します。この段階で劣化の原因や施工範囲が明確になり、最適な工法の選定が可能になります。専門的な診断を受けることで、不要な追加工事を避けられるというメリットもあります。
見積もり提出・契約
現地調査の結果をもとに、工事の範囲・工法・スケジュールを明記した見積書が提出されます。ここで施工内容や保証範囲、支払い条件をしっかり確認したうえで契約を結びます。不明点がある場合はこの時点で解消しておくことが大切です。
足場設置(必要な場合)
パラペットの防水工事は高所作業になるため、安全対策として足場の設置が求められるケースが多くあります。足場の有無は費用や工期にも影響を与えるため、事前に確認しておきましょう。設置には1日〜2日程度を要します。
既存防水層やシーリングの撤去
劣化が進行している場合、古い防水層や劣化したシーリング材を撤去する必要があります。この作業を怠ると、新たに施工する防水層の密着性が低下し、早期に不具合が発生するリスクが高まります。
下地処理・清掃
撤去後は、下地の清掃やプライマー処理などを行い、防水材との密着性を高める工程に入ります。ひび割れ補修や段差調整などもこの工程で行われ、仕上がりと耐久性に直結する非常に重要な作業です。
防水材の施工
下地処理が完了したら、選定した工法に応じて防水材の施工を行います。ウレタン塗膜防水であればローラーや刷毛による塗布、シート防水であれば接着剤と機械固定を用いた貼付施工など、工法ごとに施工手順が異なります。
乾燥・硬化期間
防水材の施工後は、材質に応じた乾燥・硬化の時間を確保します。ウレタン塗膜の場合は2〜3日、シーリングであれば1日程度が目安です。しっかり硬化するまでは歩行や加重を避ける必要があります。
完了検査・片付け
すべての施工が終わったら、目視と散水による漏水チェックを行い、工事の仕上がりを確認します。問題がなければ足場を撤去し、清掃とともに施工完了報告書や保証書を提出して作業終了となります。
工法別の工期目安
- シーリング再施工:1〜2日
- ウレタン塗膜防水:3〜5日
- シート防水(塩ビ):2〜4日
- 笠木交換工事:3〜5日
建物の規模や天候によって変動するため、余裕を持ったスケジュールを計画することが大切です。
防水保証と施工後のアフターサービスとは?
防水工事の施工後、どれくらいの保証が付くのかは重要な判断基準です。業者選びの際に確認すべき保証内容やアフターサポートのポイントを紹介します。
保証内容の目安
- 保証期間:一般的に5〜10年(工法や業者により異なる)
- 保証範囲:漏水・剥離などの施工不良に対する補償
- 保証対象外:天災・第三者の損傷・使用者の過失など
アフターサービスの例
- 定期点検サービス:工事後の1年・5年後などに無料点検
- 緊急時の対応可否:突然の雨漏りに対する即日対応
- 報告書の発行:施工中・完了後の写真付き報告書を提出
契約時に必ず保証書を確認し、書面で内容を取り交わすことが安心につながります。
パラペット防水工事で業者選びで失敗しないためのチェックリスト
パラペット防水は専門性が高く、業者の技術力や対応力が仕上がりを大きく左右します。信頼できる業者を見極めるために確認すべきポイントをチェックリスト形式でご紹介します。
業者選定のチェックポイント
- 施工実績の確認:パラペット防水の事例があるか
- 防水施工技能士など資格者が在籍:技術力の裏付け
- 見積もりの明細が明確:不明瞭な費用がないか
- 保証内容が明示されているか:施工後も安心
- 口コミ・評判の確認:GoogleレビューやSNSの評判
- 説明が丁寧で対応が早いか:信頼できる窓口対応
複数社から相見積もりを取ることで、価格だけでなく信頼性も比較できます。
戸建て・マンション・ビルで異なるパラペット防水の注意点
建物の種類によって、パラペットの形状や施工方法に違いがあります。戸建て・集合住宅・商業ビルそれぞれでの防水工事のポイントを解説します。
戸建て住宅の場合
戸建てでは比較的施工範囲が狭く、足場の有無で費用が大きく変動します。外観のデザイン性を損なわないよう、塗膜系のウレタン防水やカラー塗装を組み合わせた工法が好まれます。
マンション(集合住宅)の場合
共用部分となるため、管理組合の承認や住民対応が必要です。足場設置や工事期間中の安全対策、作業音への配慮などが求められます。保証付きの工法や施工記録の提出が重視される傾向があります。
商業ビル・事業用物件の場合
防水性能に加え、メンテナンス性・耐久性・工期の短縮が重視されます。シート防水や笠木交換など、耐用年数の長い工法が選ばれることが多く、施工中の営業活動への影響を最小限に抑える配慮も必要です。建物の種類によって、パラペットの形状や施工方法に違いがあります。戸建て・集合住宅・商業ビルそれぞれでの防水工事のポイントを解説します。
パラペット防水工事でよくある質問(FAQ)
ここでは、パラペットの防水工事でよくある質問についてまとめているので、ぜひ参考にしてみてください。
Q1. パラペットの防水は何年おきに行えばよい?
一般的には10年〜15年ごとに再防水を行うのが目安です。ただし、建物の立地条件や使用されている防水材の種類によっては、それより早く劣化が進行する場合もあります。3〜5年ごとの定期点検を行い、状態を見極めることが重要です。
Q2. パラペット防水工事は建物全体の足場が必要ですか?
建物の高さや構造によっては、安全面から足場の設置が求められます。特に3階建て以上の建物や傾斜の強い屋根がある場合には、足場費用も見積もりに含まれることが多くなります。
Q3. DIYでパラペット防水をすることは可能ですか?
一部のシーリング補修や簡易的な塗装であればDIYも不可能ではありませんが、専門的な技術が必要となるため、長期的な耐久性や安全性を考えると業者に依頼するのが安心です。
Q4. パラペット防水に保証はつきますか?
ほとんどの施工業者では、防水工事に対する施工保証(5〜10年)が付きます。保証内容は業者によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
パラペット防水工事で建物の寿命を守ろう|まとめ
パラペットは見落とされがちな部分ですが、実は建物全体の防水性や耐久性に直結する非常に重要な構造です。ひび割れや劣化を放置すれば、雨漏りや構造部材の腐食といった重大なトラブルに発展することもあります。
適切なタイミングで点検やメンテナンスを行い、必要に応じて信頼できる専門業者に防水工事を依頼することで、大切な建物を長く快適に維持することができます。
パラペットの状態が気になったら、まずは無料の現地診断を活用し、早めの対応を検討してみてください。










