
大規模修繕工事の戸当たり単価とは?相場の目安やコスト削減のポイントを解説
2025/07/24
大規模修繕工事の費用は数千万円単位に及ぶこともあり、住民にとっては大きな負担となる場合があります。その際に指標となるのが「戸当たり単価」です。これはマンション全体の工事費用を世帯数で割った金額を指し、住戸ごとの費用感を把握するのに役立ちます。
とはいえ「一戸あたりでいくらかかるのか分からない」「他のマンションと比べて高いのか安いのか判断できない」と悩む管理組合や所有者も少なくありません。さらに、工事内容によってもコストは変動するため、相場を正確に捉えるには複数の視点が必要です。
この記事では、大規模修繕工事の戸当たり単価に焦点をあて、相場の目安・計算方法・費用の内訳・コスト削減の工夫まで、管理組合や区分所有者に役立つ情報をわかりやすく解説していきます。
目次
大規模修繕工事の戸当たり単価平均と相場の目安
マンションの大規模修繕では、戸数や築年数・工事項目により単価に大きな差が出ます。適正なコストを把握するには、まず相場感を知ることが第一歩です。
ここでは、全国平均やマンション規模別の目安をもとに一般的な相場感を紹介します。
全国平均とマンション規模別の単価傾向
一般的に、大規模修繕工事の戸当たり単価は50万円〜120万円が相場とされています。ただし、この金額はマンションの築年数、規模、立地、施工内容、施工会社の選定条件などによって大きく変動します。
例えば、都市部では人件費や資材費が高騰しているため相場が上がりやすく、地方では比較的コストが抑えられる傾向にあります。また、高層マンションや特殊な構造を持つ建物は、仮設工事や施工の難易度が上がるため、単価が割高になることもあります。
規模が小さいマンションほど共用部や足場などの工事単価が割高になりがちで、戸当たりコストも高くなる傾向があります。一方で、50戸以上の大規模マンションでは工事全体のスケールメリットが働き、単価を抑えられるケースも多く見られます。このように、建物の条件によって大きな差が出るため、相場だけに頼らず、条件に見合った比較が必要です。
10戸・30戸・50戸以上の費用モデル
以下に、代表的な戸数別の費用モデルと戸当たり単価の目安をまとめます。戸数による影響は顕著であり、費用構造を理解するうえでも有用な比較になります。
| 規模 | 総工事費の目安 | 戸当たり単価 |
|---|---|---|
| 10戸規模の小型マンション | 1,200万〜1,500万円 | 約120万〜150万円 |
| 30戸程度の中規模マンション | 2,400万〜3,600万円 | 約80万〜120万円 |
| 50戸以上の大型マンション | 4,000万〜6,000万円 | 約60万〜90万円 |
たとえば10戸の小規模マンションでは、足場費用や仮設工事の比重が大きくなるため、一戸あたりの負担が大きくなります。一方、50戸以上の大規模物件では、費用を分散しやすく、設備更新や工事項目の拡張もしやすいといった利点もあります。
これらはあくまで目安であり、実際には建物の劣化状態や施工内容によって変動します。そのため、複数の見積もりを取得して比較検討することが大切です。可能であれば、同じ築年数・構造・立地の物件と比較することで、より現実的な相場感が得られるでしょう。
大規模修繕工事の戸当たり単価の計算方法と注意点
戸当たり単価は単純な割り算で算出できますが、実際には計算方法や対象範囲に注意が必要です。特に、どの費用を含めるか、またどの住戸がどの程度の負担をするのかという点は管理組合で明確にしておかなければなりません。
ここでは、基本的な計算式とよくある誤解と確認すべき点を解説します。
基本的な計算方法とは
戸当たり単価の基本的な計算式は「戸当たり単価=総工事費 ÷ 総戸数」です。たとえば、総工事費が3,000万円で30戸のマンションなら、戸当たり単価は100万円となります。
ただし、この計算はすべての住戸が同じ条件で費用を負担するという前提に基づいています。実際には、専有部の工事を含むかどうかや、階数・住戸の広さによる負担割合が異なる場合もあるため、注意が必要です。特に管理規約の内容によっては、階層別や専有面積による按分が必要となることがあります。
また、施工会社の選定費や設計監理費、コンサルタント費用などを総工事費に含めるか否かによっても、計算結果は異なります。これらの取り扱いについても、見積もり段階で明確にしておく必要があります。
共用部や専有部の負担割合に注意
工事項目によっては、共用部(廊下・エントランス・外壁・屋上など)だけでなく、専有部(バルコニーや玄関ドアなど)にまで工事が及ぶことがあります。共用部分の工事は全体で負担しますが、専有部に関する部分については各住戸ごとに費用負担を検討する必要があります。
その場合、専有部に関する費用をどこまで住民負担とするかは、規約や管理組合の方針によって異なります。事前に合意形成を行い、負担割合を明確にすることがトラブル回避の鍵となります。合意が不十分なまま進行すると、後々のトラブルや反対意見につながる可能性も高くなるため、説明責任をしっかり果たすことが重要です。
住戸によって異なる場合の計算例
最上階住戸では屋上防水工事の影響が大きく、バルコニーの仕様も異なるため、追加費用が発生することがあります。逆に、1階住戸では共用廊下の範囲が狭く、コストが少ないケースも考えられます。また、角部屋や専有面積の広い住戸では負担が大きくなる場合もあります。
このような場合は、按分方式を採用し、住戸ごとに異なる負担額を計算する方式が一般的です。按分方法としては、専有面積比、階層別、位置別などの複数の軸から検討することができます。管理会社や設計監理者のサポートを受けながら、透明性のある算出を行いましょう。
大規模修繕工事の戸当たり単価と主な費用内訳
戸当たり単価を理解するには、工事費全体の構成を知っておくことが不可欠です。単価を算出する前提として、どのような工事項目にいくらかかっているのかを把握しておくことで、相場の妥当性を判断しやすくなります。
ここでは、大規模修繕工事で発生する主な費目を解説します。
仮設工事
仮設工事は、大規模修繕において最初に行われる作業であり、全体の安全性と作業効率を左右します。主に足場の設置や養生ネット、防護幕の取り付けなどが該当し、全工事費の15〜20%程度を占めるのが一般的です。
特に高層階が多いマンションでは足場の高さが必要となるため、仮設費が増加します。また、敷地条件や周辺環境によっては足場の設置方法に制約が生じ、追加費用が発生するケースもあるため、事前の現地調査が重要です。
外壁補修・塗装工事
外壁は建物の外観を保つだけでなく、風雨や紫外線から構造体を守る重要な部分です。経年劣化によるひび割れやチョーキング現象、塗膜の剥がれが見られる場合、補修・再塗装が必要です。
この工事には、下地処理、クラック補修、高圧洗浄、塗装の3〜4工程が含まれます。工法や塗料の種類によって費用は変動しますが、一般的には工事費の30〜40%を占めることが多い項目です。美観だけでなく、防水性能や耐候性の向上にもつながるため、適切な材料と施工が求められます。
防水工事
屋上やバルコニー、共用廊下は雨水の影響を受けやすい場所であり、防水層の劣化は雨漏りの原因になります。防水工事には、シート防水、ウレタン塗膜防水、アスファルト防水などの種類があり、現場の状況に応じて選定されます。
防水工事は、施工の難易度や対象面積によって大きく費用が変動しますが、全体の15〜25%前後を占めることが多いです。漏水トラブルを未然に防ぐためにも、定期的な更新が不可欠です。
給排水・電気設備更新工事
建物のインフラ部分にあたる給排水管や電気設備も、一定年数を経ると老朽化してトラブルの原因になります。特に配管の腐食や漏水、絶縁劣化による電気トラブルは生活に直結するため、更新のタイミングは非常に重要です。
設備更新工事は他の工事と比べて専門性が高く、工事期間やコストもかかりやすい傾向にあります。費用比率としては10〜15%ほどですが、長期的に見れば修繕回数を減らす効果があるため、コストパフォーマンスの高い投資ともいえます。
新東亜工業の施工事例|13階建てマンションの大規模修繕工事
東京都内にある13階建てワンオーナーマンションにて、新東亜工業が実施した大規模修繕工事の事例をご紹介します。
外壁タイルやシーリング、屋上防水など複数の劣化箇所を総合的に改修し、建物の資産価値を回復しました。

工事概要【工事金額・期間】

工事金額:6,098万円/工期:約5か月間(足場設置〜引き渡しまで)
屋上防水・外壁タイル補修・シーリング打ち替えを中心に、建物全体をバランスよく修繕。
建物全体にわたる一貫した施工により、見た目と性能の両立を実現しました。
ご相談内容・お問い合わせ内容
長年手を入れていなかったマンションの修繕を検討し始めたオーナー様から、初回のご相談をいただいたのがスタートでした。
オーナー様「タイルの剥がれや屋上の汚れが気になっていて…」
担当者「まずは図面を拝見して、現地調査で状態を見ていきましょう」
築20年以上が経過し、目視でも劣化が感じられるように。
最初は「少し気になる」という段階でしたが、調査を通じて複数の問題が明らかになっていきます。
調査で明らかになった劣化状況
現地での打診調査や目視検査によって、建物の各所に進行した劣化が確認されました。
オーナー様も驚かれるほどの症状が浮き彫りに。
屋上防水の劣化
既存の通気緩衝工法によるウレタン防水は、広範囲に劣化や膨れが生じていました。
オーナー様「花火の時期には屋上に上るんです。きれいになると嬉しいな」
現地調査員「眺望も大事ですね。美観にも配慮して施工いたします」
外壁タイルの浮き・剥離
浮きタイルが多数見つかり、剥離の危険性も。
劣化の進行度に応じて、張替えと樹脂注入を使い分けました。
担当者「打診調査で見えない内部の浮きも確認しました。対応が必要です」
シーリングの硬化不良
シーリング材は硬化しきって弾性を失い、手作業での撤去が必要なほどでした。
現場職人「カッターが入らないくらい硬くなってます。全部打ち替えですね」
オーナー様「そこまで傷んでたとは…早めにお願いしてよかったです」
工事の流れと透明な対応
調査結果をもとに明確な見積書と診断書を作成。
オーナー様に工程を丁寧に説明し、工事中も報告を徹底しました。
診断報告と見積提示
写真付きの診断報告書と、内訳を明記した見積書を提出。
工事内容をわかりやすく共有しました。
オーナー様「写真があると素人でもわかりやすいですね」
担当者「透明性を重視していますので、何でもご質問ください」
工事の実施(足場~防水まで)
工程は足場設置から高圧洗浄、下地補修、シーリング、塗装、屋上防水まで。
報告写真とともに進捗共有を行いました。
担当者「毎週の報告で進捗をご確認いただけます」
オーナー様「離れてても工事の様子がわかって安心できました」
工事完了後のオーナー様の声
見た目だけでなく機能性も向上した建物に、オーナー様からは満足の声が寄せられました。
オーナー様「すっかりきれいになりましたね。やってよかったです」
担当者「大切な資産を守るお手伝いができて光栄です」
\お問い合わせや工事のお見積もり無料!/
大規模修繕工事の戸当たり単価を抑える3つの方法
適切な発注と事前の準備により、戸当たり単価を抑えることは可能です。
ここでは、コストダウンを実現するための現実的な方法を3つ紹介します。
複数業者からの相見積もりを取得する
最も基本でありながら非常に効果的なのが、複数の施工業者から相見積もりを取ることです。業者によって提案内容や施工方法、価格には差があるため、比較検討することで適正価格を見極めやすくなります。
また、相見積もりを取ることで業者側にも競争意識が生まれ、過度に高い見積もりを抑える効果も期待できます。ただし、単に価格が安い業者を選ぶのではなく、工事実績・対応力・保証内容など総合的に評価することが重要です。
工事時期と発注方式を工夫する
工事の実施時期によっても費用は変動します。たとえば、梅雨や台風の多い時期を避けることで天候による工期遅延リスクを減らし、効率的な進行が可能になります。また、年度末や繁忙期を避けることで施工会社の人員確保がしやすくなり、見積もり価格を抑えられる場合もあります。
発注方式についても、「責任施工方式」だけでなく「設計監理方式(第三者による監理)」を採用することで、見積もりの透明性が高まり、無駄な費用を防ぐことができます。管理組合側の監理体制を整えることが、無駄な支出を防ぐ第一歩です。
長期修繕計画との連動・調整を行う
長期修繕計画と今回の修繕工事を連動させることで、費用の最適化が図れます。本来別年度に行う予定だった工事項目を一括で実施することで、足場の設置費用を共有できるなど、コストダウンの余地が生まれます。
また、修繕積立金の運用状況や、将来的な支出予定とのバランスを確認することも重要です。中長期的な視点で修繕計画を見直すことで、急な支出を抑え、住民の合意形成もスムーズになります。
大規模修繕工事でお悩みの管理組合の方
「ファシリテーション」で談合をなくそう!
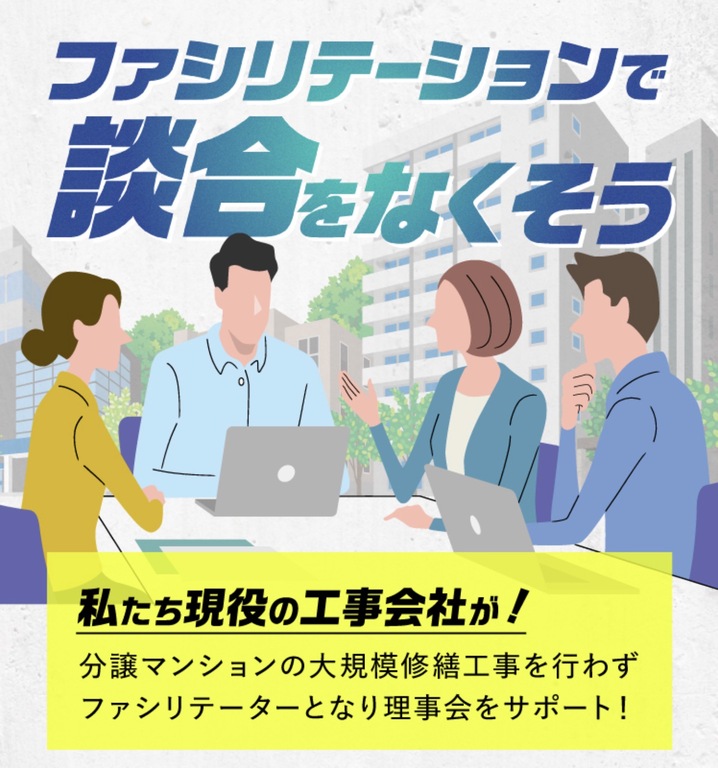
\お問い合わせや工事のお見積もり無料!/
豊富な実績と専門知識を持つスタッフが、
皆様の疑問や不安にお答えし、最適な解決策をご提案いたします。
大規模修繕工事の戸当たり単価を実際のマンションで比較
具体的な数値と事例は、コストの妥当性を判断するうえで非常に有効です。ここでは、マンションの規模別に実際の工事費・戸当たり単価を比較し、どのような特徴があるのかを紹介します。
マンション規模別・修繕費用と戸当たり単価の比較表
| 規模 | 総工事費 | 工事項目 | 戸当たり単価 |
|---|---|---|---|
| 小規模(10戸) | 1,400万円 | 足場・外壁補修・屋上防水 | 約140万円 |
| 中規模(30戸) | 3,300万円 | 外壁全面塗装・屋上防水・バルコニー床改修・設備更新 | 約110万円 |
| 大規模(50戸以上) | 4,500万円 | 全面改修・防水・配管更新・EVリニューアル等 | 約90万円 |
このように、戸数が増えるほどスケールメリットが働き、戸当たりの負担額が下がる傾向にあります。一方で、規模が小さい物件ではどうしても共通工事の比率が高くなり、単価が割高になるため注意が必要です。
大規模修繕工事の戸当たり単価に関するよくある質問(FAQ)
Q1. 戸当たり単価が相場より高いと感じたら?
A.まずは同規模・同築年数・同エリアの他マンションの事例と比較しましょう。それでも高い場合は、見積書の内訳を細かくチェックし、不明瞭な項目がないかを確認します。必要に応じてセカンドオピニオンを依頼するのも有効です。
Q2. 築年数が古いと単価も高くなる?
A.一般的にはその傾向があります。老朽化が進んでいると補修範囲や工事項目が増え、結果として工事費が高くなりやすくなります。ただし、事前の点検と長期修繕計画によって費用の平準化を図ることも可能です。
Q3. 住戸によって費用負担は変わる?
A.共用部中心の工事では基本的に均等割りですが、専有部に影響する工事や階層ごとの仕様差がある場合は按分されることがあります。管理規約や合意形成の方法によって異なるため、事前に確認が必要です。
大規模修繕工事の戸当たり単価はコスト管理の第一歩|まとめ
大規模修繕工事における戸当たり単価は、住民一人ひとりの費用負担を考えるうえで非常に重要な指標です。単価を正しく把握し、相場と比較することで、コストの妥当性を判断できるようになります。
この記事で紹介したように、単価はマンションの規模や工事項目、業者の選定、発注方式によって大きく左右されます。また、見積もりの取得方法や時期の選定、修繕計画との連動など、工夫次第でコストダウンも可能です。
まずは現状を正確に把握し、無理のない計画を立てることが大切です。そして、透明性の高い見積もりと合意形成によって、住民の納得感と満足度を高める修繕工事を実現していきましょう。








