
FRP防水とは?特徴・工法・費用・メリット・注意点を徹底解説
2025/07/24
住宅のベランダやバルコニー、屋上といった場所において、経年劣化や雨水侵入を防ぐために不可欠なのが「防水工事」です。その中でも、特に近年注目されているのが「FRP防水」です。防水工法のひとつでありながら、他の工法と比べて高い強度や耐久性、施工スピードの速さなど、多くのメリットを持っています。しかし、FRP防水にも適材適所があり、すべての建物や環境に最適というわけではありません。
本記事では、FRP防水の基礎知識から、施工方法、費用感、長所と短所、他の防水工法との違いまで、住宅のメンテナンスを考える上で知っておきたいポイントを丁寧に解説していきます。これから防水工事を検討している方や、FRP防水を検討中の方にとって、有益な情報源となることを目指しています。
FRP防水をはじめとした防水工事の種類については、こちらの記事で詳しく解説しています。
工事を検討している方は、ぜひ一読のうえ施工方法を検討ください。
目次
FRP防水とは?基本の仕組みと素材の特徴
FRP防水とは、「Fiber Reinforced Plastic(繊維強化プラスチック)」を素材とした防水工法で、ガラス繊維(ガラスマット)と硬化樹脂を組み合わせて強固な防水層を作り上げる方法です。この防水層は塗膜タイプに分類され、施工面に直接塗り広げることで継ぎ目のない一体化した仕上がりになります。
もともとFRPは、自動車の外装部品、バスタブや船舶などにも使われるほど強度と耐久性に優れた素材です。そのため、防水工法としてもその優れた物性が活かされており、特に強度が求められる場所や複雑な形状の面にも柔軟に対応できます。
建築分野では、住宅のベランダ・バルコニー、屋上といった比較的小規模で人の出入りがある場所において多用されており、軽量ながらも高い防水性能を発揮します。さらに、施工後の見た目が美しいという特徴もあり、景観性を重視する物件でも選ばれやすい工法です。
FRP防水の施工工程
FRP防水の施工は、いくつかの明確な工程を経て完了します。作業自体はスピーディーで、乾燥や硬化の時間も短く、天候に大きく左右されにくいため、現場での段取りがしやすいというメリットがあります。以下に代表的な施工工程を紹介します。
- 下地処理・清掃:コンクリートやモルタルなどの施工対象面をきれいに掃除し、表面のホコリ、油分、ゴミを取り除いて平滑に整えます。下地の状態が仕上がりに直結するため、最も重要な工程の一つです。
- プライマー塗布:下地と防水材の密着性を高めるために、専用のプライマー(接着剤)を塗布します。プライマーがしっかりと下地に吸着することで、後の防水層の剥離を防ぎます。
- ガラスマットと樹脂の積層:ガラスマットを敷き、その上からポリエステル樹脂を塗布していきます。樹脂はローラーや刷毛を用いて丁寧に塗り込み、ガラスマットにしっかりと含浸させます。この積層工程を1〜2回繰り返すことで、高強度の防水層が形成されます。
- 硬化・研磨作業:樹脂が完全に硬化するまで一定時間を置いた後、表面をサンダーなどで研磨し、凹凸をならして滑らかに整えます。これは仕上げの美しさとトップコートの密着性を高めるために欠かせません。
- トップコート塗布:最終仕上げとして、紫外線や摩耗から防水層を守るためにトップコート(保護塗料)を塗布します。トップコートには色付きのものも多く、美観の向上にも寄与します。
このようにFRP防水は、施工者の技術によって仕上がりに差が出る工法ではありますが、正しく施工されれば長期間にわたって優れた防水性能を維持することができます。
基本的な防水工事の流れについては、こちらの記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
FRP防水のメリットとデメリット
FRP防水は高性能な工法である一方で、適用範囲や注意点を理解しておくことが重要です。ここでは、FRP防水の代表的な長所と短所を詳しく見ていきましょう。
メリット
- 軽量で建物に負荷をかけにくい:防水層の厚みが1〜2mm程度と非常に薄く、全体が軽量に仕上がるため、建物への構造的な負担が少なくなります。
- 高強度・高耐久で摩耗にも強い:ガラス繊維の補強により、耐衝撃性や耐摩耗性に優れ、人が頻繁に歩く場所でも安心して使えます。
- 継ぎ目のない美しい仕上がり:液状の材料を用いた塗布工法であるため、シームレスで均一な防水層が形成され、ひび割れや雨水侵入のリスクが低減されます。
- 複雑な形状にも適応可能:段差や立ち上がり部分、排水口周辺など形状が複雑な箇所でも、柔軟に対応可能なため施工自由度が高いです。
- 短期間で施工が完了:乾燥・硬化時間が短く、1〜2日程度で工事が完了するため、居住者の負担も少なく済みます。
デメリット
- 紫外線に弱くトップコートの定期更新が必要:防水層自体は紫外線に弱いため、5年を目安にトップコートの再塗装が必要です。放置すると防水性能が劣化します。
- 下地の動きに弱い(特に木造住宅):FRP防水は伸縮性が少ないため、木造住宅など下地の動きが大きい建物では、ひび割れや剥がれが起こるリスクがあります。
- 施工時に臭いが強く、火気にも注意が必要:ポリエステル樹脂は溶剤を含むため、施工中は刺激臭が強く、周囲の換気や火気厳禁の対策が欠かせません。
これらの点を考慮すると、FRP防水はすべてのケースに適しているわけではありません。建物の構造や使用環境に応じて、他の防水工法との比較検討を行い、最適な方法を選ぶことが成功への第一歩となります。
FRP防水の施工が適した場所と不向きな場所
FRP防水は非常に高い防水性能と耐久性を誇る工法ですが、すべての場所に万能というわけではありません。施工場所の構造、気候、使用目的などによって向き不向きが分かれます。施工前にFRP防水が本当に適しているのかどうかを正しく判断することは、長期的な防水性能を確保する上でも非常に重要です。
適している場所
FRP防水がとくに適しているのは、歩行頻度が高く、人の往来があるような小規模なスペースです。また、形状が複雑な場所や、スピーディーな施工が求められるケースにも対応力を発揮します。
- 住宅のベランダ・バルコニー:雨風にさらされやすく、かつ人の歩行が日常的に行われるベランダやバルコニーでは、摩耗や劣化に強いFRP防水の性能が非常に有効です。住宅密集地などで施工期間を短くしたい場合にも適しています。
- 鉄筋コンクリート造(RC構造)の屋上:下地が安定しているため、FRP防水の硬質な仕上がりと相性が良く、長期的な耐久性も期待できます。
- ルーフバルコニー・庇・出窓・屋根の谷部など、細部形状の箇所:FRP防水は液状材料を塗布して形成するため、細かい段差や複雑な形状にも対応可能です。
- 外階段・開放廊下など、人の往来が激しく防水性が求められる場所:滑り止め仕様のFRP施工も可能で、安全性と機能性を兼ね備えています。
適していない場所
一方で、FRP防水は柔軟性が低いため、建物の動きが大きい場所や、大規模な面積に対してはリスクも伴います。以下のようなケースでは、他の防水工法を検討するほうが適している場合もあります。
- 大規模な屋上(特に木造建築):広範囲に施工すると、下地の動きに追従できずにひび割れを起こす可能性があります。木造は特に温度や湿度の影響で変形しやすく、FRP防水との相性が良くありません。
- 高層階や地震の多いエリアの屋上・バルコニー:構造的な揺れが頻繁に起こる場所では、硬化したFRP層が追随しにくく、亀裂や剥がれが生じやすくなります。
- 経年劣化が進んだ下地:下地が脆弱な場合、FRP防水の硬さが裏目に出て、割れや剥離の原因となることがあります。補強や下地補修を併用しないと、十分な性能を発揮できません。
施工前には、必ず専門業者による下地調査を行い、最適な防水工法を選定することが大切です。
FRP防水の費用相場とメンテナンス周期
防水工事を検討する際には、初期施工費用だけでなく、メンテナンスにかかるコストや周期も含めて総合的に判断することが重要です。FRP防水は高性能である一方、定期的なメンテナンスを前提とした設計が求められます。
費用相場(1㎡あたりの目安)
| 工事内容 | 費用相場(税別) |
|---|---|
| 新築でのFRP防水施工 | 約6,000〜8,000円/㎡ |
| 改修時の再施工 | 約7,000〜10,000円/㎡ |
| トップコート再塗装 | 約1,500〜2,500円/㎡ |
この費用は、施工範囲の広さや使用材料のグレード、職人の技術レベル、地域差などによって変動します。特に改修工事では、古い防水層の撤去、下地の修復作業などが加わるため、新設よりもやや高くなる傾向があります。
たとえば、10㎡のバルコニーを改修する場合、下地処理や古い防水層の撤去を含めて、総額で10〜13万円程度になることも想定されます。トップコートのみの塗り替えであれば、数万円で対応できるため、定期的な塗り替えは費用対効果が高い対策といえます。
メンテナンス周期と耐用年数
- トップコートの塗り替え:5〜7年ごとに行うのが理想です。日射や風雨による劣化を防ぎ、防水層本体を長持ちさせます。トップコートが粉を吹いたり、変色してきたら要注意のサインです。
- 防水層本体の耐用年数:標準的には10〜15年ですが、施工精度や使用条件により異なります。適切なメンテナンスを継続して行えば、20年以上持つケースも少なくありません。
定期的な点検により劣化の早期発見が可能になり、必要最低限の補修にとどめることで、トータルコストを抑えることにもつながります。
他の防水工法との違い(ウレタン・シート・アスファルトとの比較)
FRP防水が優れているとはいえ、すべての防水工事に万能というわけではありません。他の主要な防水工法との違いを比較し、建物の特性に合った選択をすることが求められます。
| 防水工法 | 特徴 | 適用部位 | 耐用年数 | 費用目安(㎡) |
|---|---|---|---|---|
| FRP防水 | 高強度・軽量・美観・施工が早い | ベランダ・バルコニー・屋上の一部 | 約10〜15年 | 約6,000〜10,000円 |
| ウレタン防水 | 柔軟性が高く、施工が簡易。下地追従性に優れる | 複雑形状の屋上、バルコニー | 約10〜12年 | 約4,000〜7,000円 |
| シート防水 | 規格品の防水シートを貼るため品質が安定しやすい | 広い屋上や大面積の倉庫・工場屋根 | 約10〜15年 | 約5,000〜8,000円 |
| アスファルト防水 | 厚みと重厚感があり、耐久性が非常に高い | 大型ビル、地下室、構造物の屋根 | 約15〜20年以上 | 約7,000〜10,000円 |
このように、FRP防水は小規模な部位に対して高い効果を発揮しますが、広範囲や柔軟性が求められる部位ではウレタンやシート防水、耐久性重視であればアスファルト防水などが適しています。
防水工事を成功させるためには、「建物の構造」「使用頻度」「求める耐久年数」「予算」などの複合的な要素をふまえて、最適な工法を選定することがカギになります。
実録!新東亜工業の施工事例|8階建てビルの防水工事【企業様】
芝生の敷設を目的とした屋上緑化に先立ち、防水工事を行いたい——そんな法人様のご相談から始まった今回の工事。東京都台東区にある8階建てビルにて、既存のウッドデッキと植栽の撤去を含む防水工事を実施しました。企業様ならではの稟議・スケジュール調整にも柔軟に対応し、確実な施工をお届けした実例です。
ご相談内容
屋上緑化のため、事前の防水施工をご希望された法人様からのお問い合わせ。既存のウッドデッキや植栽の撤去も含めた施工をご希望され、他業者との調整も視野に入れたご提案が求められました。
お客様:屋上に芝生を敷きたいんですが、防水をしっかりやってからにしたくて…ウッドデッキも撤去お願いできますか?
担当者:はい、もちろん可能です。芝生施工業者様との整合性も確認のうえ、工法をご提案いたします。
工事の概要|工事金額と期間

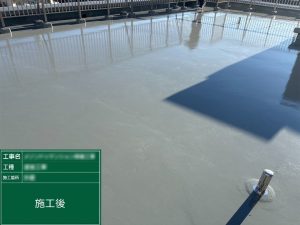
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 建物種別 | 8階建て企業ビル |
| 所在地 | 東京都台東区 |
| 工事内容 | 屋上防水工事(通気緩衝工法)・ウッドデッキ等撤去 |
| 工法 | ウレタン通気緩衝工法・改修用ドレン設置・脱気筒設置 |
| その他特記事項 | 芝生設置業者との事前確認・稟議対応 |
工事金額:364万円
工期:13日間
現地調査で判明した劣化症状
現地調査の結果、ウッドデッキや植栽の撤去後に下地調整が必要な箇所が複数見つかりました。将来的な芝生設置に耐えうる防水性能確保のため、通気緩衝工法を採用。
担当者:芝生施工業者さんとも確認取りましたが、防水には影響ありません。
お客様:ありがとうございます。では、ウレタン通気緩衝工法でお願いします。
施工中のやり取りと配慮
ウッドデッキ・植栽の解体撤去から始まり、洗浄、下地処理、ドレンや脱気筒の設置、防水層の形成までスムーズに進行。工程ごとの進捗共有と、社長様を含めた中間検査も実施しました。
担当者:予定通り木曜日には完了しそうです。一緒に最終確認もお願いします。
お客様:綺麗に片付いていて安心しました。ありがとうございます。
引き渡し時のご感想
最終確認では、社長様も立ち会い、美観や機能性にご満足いただきました。今後のメンテナンス方法についても丁寧にご説明し、報告書類一式を後日郵送でお渡し。
お客様:さすがプロですね。花火大会も楽しめそうです(笑)
担当者:排水口は半年に1度の清掃をお願いします。今後ともよろしくお願いいたします。
本工事は、企業ビルにおける屋上防水工事という特性上、通常より多くの配慮が求められました。緑化計画や他業者との連携、法人内稟議フロー、近隣への対応など、多岐にわたる調整を丁寧に実施。施工面ではウレタン通気緩衝工法により、今後の芝生設置にも耐えうる高い防水性能を確保しました。
法人様のご要望に的確に応えることで、安心と信頼を構築した施工事例となりました。
\お問い合わせや工事のお見積もり無料!/
まずはメール・お電話からご相談ください!
よくある質問(FAQ)
Q1. FRP防水はDIYで施工することはできますか?
A. 基本的にはおすすめできません。FRP防水の施工には専門的な知識と熟練した技術が不可欠であり、樹脂の硬化タイミング、適正な塗布量、温度・湿度の管理、換気対策、火気の扱いなど、現場環境ごとに細やかな配慮が求められます。これらを正確に実施しなければ、施工不良が発生しやすく、漏水やひび割れの原因となる可能性があります。また、失敗した場合の補修も簡単ではなく、場合によっては全面やり直しとなり、費用がかえって高額になるケースもあるため、DIYは現実的とは言えません。安全かつ確実に高い防水性能を実現するためには、経験豊富な防水業者に依頼するのが最良の選択です。
Q2. トップコートの再塗装を怠るとどうなりますか?
A. トップコートは、FRP防水層を紫外線や風雨、摩耗などの外的要因から守るために必要不可欠な仕上げ材です。これを定期的に再塗装せずに放置してしまうと、防水層の表面が徐々に劣化し、変色・チョーキング(白い粉が出る)・ひび割れなどの症状が現れます。さらに、トップコートの劣化が進行するとFRP樹脂そのものが紫外線や雨水に直接さらされることになり、性能の低下や構造部材への浸水リスクも高まります。最終的には大規模な補修や防水層の再施工が必要になることもあり、余計な費用がかかってしまう結果になります。定期的な点検と5〜7年ごとの再塗装を継続することが、FRP防水の長寿命化とランニングコストの最小化に直結します。
Q3. FRP防水は何回でも重ねて施工できますか?
A. FRP防水は一定回数までであれば、既存の防水層の上から再施工が可能です。ただし、回数を重ねることで防水層が過度に厚くなり、ひび割れや剥離のリスクが高まる可能性があります。特に古い防水層の状態が悪かったり、既に浮きやクラックがある場合は、重ね塗りではなく、古い層を一度撤去してから新たに施工し直す方が安全で長持ちするケースも多く見受けられます。また、既存層との密着性を確保するためには、表面の研磨や下地処理などの適切な前処理が必要不可欠です。再施工を検討している場合は、まず信頼できる専門業者による現地調査を受け、適切な施工方法を提案してもらうことが重要です。
まとめ
FRP防水は、軽量かつ高強度という物理的な特性を持ち、施工スピードにも優れた非常に有用な防水工法のひとつです。特に、住宅のベランダやバルコニー、複雑な形状のルーフバルコニー、小面積の屋上や外階段など、人の往来が多い場所ではその性能を存分に発揮します。施工後の見た目も継ぎ目がなく美しい仕上がりとなり、景観性と機能性を両立させたい物件に適しています。また、施工期間が短いため、日常生活や業務に支障をきたしにくい点も大きな魅力です。
一方で、FRP防水には注意すべきポイントもあります。とくに紫外線への耐性が低いため、トップコートの定期的な塗り替えを怠ると、防水性能の早期劣化を招く恐れがあります。また、FRP層は伸縮性に乏しいため、木造住宅のように構造の動きが大きい建物や、大面積で構造の揺れが発生しやすい屋上などでは、適用に慎重な判断が必要です。このような場所には、ウレタン防水やシート防水といった他の工法を併用することも検討すべきでしょう。
費用面についても、新設・改修・トップコート再塗装といった段階ごとのコストを事前に把握しておくことで、長期的な計画が立てやすくなります。さらに、10年後・15年後といった将来的な補修や再施工の可能性も見据えて、ライフサイクルコスト全体で判断することが、防水工事を成功させる鍵となります。
FRP防水の特徴や注意点をしっかりと理解したうえで、建物の構造や使用環境に合った最適な防水工法を選ぶことが、資産の保全と快適な居住環境の維持につながります。信頼できる専門業者と相談しながら、安心できる防水対策を実現していきましょう。










