
大規模修繕工事の補助金・助成金一覧!費用削減方法や申請の流れも解説【令和7年最新版】
2025/07/24
マンションの大規模修繕工事が近づいてくると、管理組合の皆さまは修繕積立金の残高を見ながら、「本当にこの費用で足りるのだろうか」と不安を感じることがあるのではないでしょうか。
建築資材や人件費の高騰により、修繕費用は年々増加傾向にあります。
そんな中、ぜひ知っておいていただきたいのが大規模修繕工事の補助金制度です。
国や地方自治体が実施するこれらの制度を活用することで、数百万円単位の費用負担を軽減できる可能性があります。
本記事では令和7年度最新の補助金情報をもとに、制度の種類・申請の流れ・注意点まで、分かりやすく解説いたします。
補助金は申請のタイミングや手続きが複雑ですが、正しく理解すれば、管理組合の大きな味方になります。ぜひ最後までご覧いただき、費用負担の軽減にお役立てください。
目次
大規模修繕工事の補助金とは?
大規模修繕工事における補助金は、建物の安全性向上や省エネルギー化、バリアフリー化など、社会的に意義のある工事に対して、国や地方自治体が費用の一部を支援する制度です。
すべての修繕工事が対象になるわけではなく、特定の目的や条件を満たした工事のみが補助の対象となります。
まずは、補助金の基本的な仕組みと、どのような工事が対象になるのかを理解しておきましょう。
補助金と助成金の違いを理解する
「補助金」と「助成金」という言葉はよく似ていますが、実は支給の仕組みに違いがあります。
マンションの大規模修繕で主に活用されるのは補助金ですが、両者の違いを知っておくと、制度選びの際に混乱を避けられます。
以下の表で、それぞれの特徴を比較してみましょう。
| 項目 | 補助金 | 助成金 |
|---|---|---|
| 支給条件 | ・審査制 ※必ず受け取れるとは限らない | ・条件を満たせば原則受給可能 |
| 予算枠 | ・限りがある ・予算に達すると募集終了 | ・比較的安定している |
| 対象分野 | ・建築改修 ・耐震 ・省エネ ・防水 ※公共性の高い工事 | ・雇用 ・研究開発 ・福祉 ※幅広い社会政策分野 |
| マンション修繕 | ・活用できる制度が多い | ・直接活用できるケースは少ない |
マンションの大規模修繕で費用負担を軽減したい場合は、補助金制度を中心に検討することになります。
ただし、審査を通過する必要があるため、制度の要件をしっかり確認し、計画的に申請を進めることが重要です。
大規模修繕工事で補助対象となる工事の種類
補助金の対象となる工事は、建物の性能向上や安全性確保など、社会的な意義が認められるものに限られます。
美観を整えるだけの工事や、専有部分のリフォームは対象外となるケースがほとんどです。
一般的に補助対象となる工事の種類は、以下の通りです。
| 工事 | 内容・目的 |
|---|---|
| 耐震改修工事 | 旧耐震基準で建てられたマンションの耐震診断や補強工事 |
| 省エネルギー改修工事 | 断熱材の追加、高断熱窓の設置、LED照明への交換などによる省エネ化 |
| 防水工事 | 屋上・外壁・バルコニーの防水性能を高め、雨漏りや劣化を防ぐ工事 |
| バリアフリー化工事 | エントランスのスロープ設置、手すりの取り付けなどによる住環境改善 |
| アスベスト除去工事 | 健康被害防止のための調査・除去作業 |
| 劣化診断 | 長期修繕計画見直しのための建物調査 |
これらの工事は、居住者の安全確保や建物の長寿命化に直結するため、国や自治体が積極的に支援しています。
自分のマンションでどの工事が必要か、そしてその工事が補助対象に該当するかを事前に確認しておくことが、スムーズな申請への第一歩となります。
補助金が適用されない工事・ケース
補助金制度には明確な対象要件があるため、すべての修繕工事が支援を受けられるわけではありません。
申請前に対象外となるケースを把握しておくことで、無駄な準備や期待外れを避けられます。
以下のような工事やケースは、補助金の対象外となることが一般的です。
| 適用外 | 内容・理由 |
|---|---|
| 美観目的のみの塗装やリフォーム | 性能向上を伴わず、見た目だけを変える改修は対象外 |
| 居住者専有部分の工事 | 各戸内部のリフォームや設備交換は対象外 (共用部分が対象になることが多い) |
| 過剰仕様や贅沢設備の導入 | 必要以上にグレードの高い仕様や設備への変更は対象外 |
| 工事契約後の申請 | 多くの補助金は工事着手前に申請が必須 |
| 過去に同じ補助金を利用した工事 | 制度によっては再申請に期間制限がある |
特に注意したいのが、工事契約のタイミングです。補助金の多くは、契約前に申請を完了させる必要があります。
契約後に補助金の存在を知っても、遡って適用することはできません。大規模修繕の計画段階から、補助金の活用を視野に入れて準備を進めましょう。
令和7年度の大規模修繕工事補助金一覧【国の制度】
令和7年度において、国土交通省・経済産業省・環境省が実施する主要な補助金制度は8つあります。特に省エネ改修に関する支援制度が充実しており、窓の断熱改修や高効率給湯器の導入などを含む大規模修繕では、複数の制度を組み合わせることで最大限の支援を受けられる可能性があります。
以下、各制度について詳しく解説していきます。
1.長期優良住宅化リフォーム推進事業
長期優良住宅化リフォーム推進事業は、既存住宅の性能を向上させ、長く安心して暮らせる住まいづくりを支援する制度です。
本事業では、以下のような性能向上工事が補助対象となります。
- 劣化対策工事:外壁塗装、屋根防水、鉄部塗装など、建物の劣化を防止する工事
- 耐震性向上工事:耐震診断に基づく耐震補強工事
- 省エネルギー性向上工事:断熱改修、高効率設備の導入など
- 維持管理・更新の容易性向上工事:配管の更新、点検口の設置など
- バリアフリー改修工事:スロープ設置、手すり設置、段差解消など
これらの工事を組み合わせて実施することで、マンション全体の性能を総合的に向上させることができます。
補助を受けるためには、工事前にインスペクション(建物状況調査)を実施し、工事後に一定の性能基準を満たす必要があります。
補助金額は、達成する性能レベルによって異なります。
| 性能レベル | 補助率 | 補助限度額 (1戸あたり) |
|---|---|---|
| 評価基準型 | 工事費用の1/3 | 100万円 |
| 認定長期優良住宅型 | 工事費用の1/3 | 200万円 |
| 高度省エネルギー型 | 工事費用の1/3 | 250万円 |
また、三世代同居対応改修工事(キッチン・浴室・トイレ・玄関のいずれかを複数化する工事)を実施する場合は、さらに50万円/戸を上限に加算されます。
令和7年度の申請期間は、下記になります。(郵送当日消印有効)
- Ⅰ期 ▶ 令和7年6月25日~令和7年9月30日
- Ⅱ期 ▶ 令和7年10月6日~令和8年2月20日
ただし、予算上限に達し次第、受付終了となりますので、早めの申請が推奨されます。
マンションの場合、管理組合が申請主体となり、共用部分の大規模修繕工事を対象とすることができ、また個々の区分所有者が専有部分の改修工事を申請することも可能です。
共用部分と専有部分を同時に改修する場合は、それぞれ別々に申請する必要があります。
詳細なスケジュールや最新情報は、国立研究開発法人建築研究所の公式サイトでご確認ください。
2.既存住宅の断熱リフォーム支援事業
既存住宅の断熱リフォーム支援事業は、高性能な断熱材や窓を使用した断熱改修を支援することで、住宅の省エネルギー性能を向上させる制度です。
以下の断熱改修工事が補助対象となります。
- 高性能な断熱材を用いた断熱改修:天井、壁、床の断熱性能を向上させる工事
- 高性能な窓への改修:ガラスやサッシを高断熱性能のものに交換する工事
- 高効率設備への改修:断熱改修と併せて実施する、空調設備や給湯設備の高効率化
特に、窓からの熱の出入りが大きいため、窓の断熱改修は省エネ効果が高いとされています。
補助金額は、住宅の種類によって異なります。
| 住宅種別 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 戸建住宅 | 工事費用の1/3以内 | 120万円/戸 |
| 集合住宅(マンション) | 工事費用の1/3以内 | 15万円/戸 |
集合住宅の場合、戸建住宅と比較して補助限度額が低く設定されている点に注意が必要です。
令和7年度の公募スケジュールは、例年6月頃から開始されます(令和7年6月時点では未発表)。
公募は複数回に分けて実施される予定で、予算上限に達し次第、受付終了となります。
マンションの場合、共用部分(廊下の窓、エントランスホールの窓など)の断熱改修が主な対象となります。専有部分の窓を各戸で改修する場合は、個別に申請することになります。
詳しい要件や申請方法は、公益財団法人北海道環境財団の公式サイトでご確認いただけます。
3.子育て支援型共同住宅推進事業
子育て支援型共同住宅推進事業は、子育てしやすい居住環境を整備するための改修工事を支援する制度です。
以下のような子育て支援に資する工事が対象となります。
- 子育て支援施設の整備:キッズルーム、プレイロット、託児スペースなどの設置
- 防音性能の向上:遮音床、遮音壁の設置による騒音対策
- セキュリティ性能の向上:防犯カメラ、オートロックシステムの導入
- バリアフリー性能の向上:エレベーターの設置、スロープの設置
- 省エネルギー性能の向上:断熱改修、高効率設備の導入
これらの工事により、子育て世帯にとって安心・快適な住環境が実現できます。
補助金額は工事の種類によって異なり、
| 工事の種類 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 新築工事 | 工事費用の1/3以内 | 500万円/戸 |
| 改修工事 | 工事費用の1/3以内 | 50万円/戸 |
既存マンションの大規模修繕の場合は「改修工事」に該当し、1戸あたり最大50万円の補助が受けられます。
管理組合が申請主体となり、共用部分に子育て支援機能を付加する工事を実施する場合に活用できます。
例えば、集会室をキッズルームとして整備したり、エントランス付近にベビーカー置き場を設けたりする工事が該当します。
令和7年度の公募スケジュールは未発表です。例年、春頃に公募が開始され、予算上限に達するまで受け付けられます。
最新情報は子育て支援型共同住宅サポートセンターの公式サイトでご確認ください。
4.アスベスト除去等事業補助金
アスベスト除去等事業補助金は、建築物に含まれるアスベスト(石綿)を除去・封じ込め・囲い込みする工事を支援する制度です。健康被害の防止と建物の安全性向上を目的としています。
以下のアスベスト対策工事が対象となります。
- 吹付けアスベストの除去工事:アスベストを完全に除去する工事(最も推奨される方法)
- 吹付けアスベストの封じ込め工事:アスベストを固化剤で固めて飛散を防止する工事
- 吹付けアスベストの囲い込み工事:アスベストを板材などで覆い、飛散を防止する工事
- アスベスト含有成形板等の除去工事:アスベストを含む建材の除去工事
特に、昭和50年代以前に建築されたマンションでは、機械室や駐車場の天井などにアスベストが使用されている可能性があります。
補助率と補助限度額は自治体によって異なります。
| 工事内容 | 補助率 | 補助限度額(例) |
|---|---|---|
| 吹付けアスベスト除去 | 工事費用の2/3 | 千代田区:400万円 横浜市:300万円 |
| アスベスト含有成形板除去 | 工事費用の1/3~2/3 | 自治体ごとに異なる |
国の補助制度を活用する場合、多くの自治体では国と自治体が費用を分担する形となっています。
申請期間は自治体によって異なりますが、多くの自治体では通年で受け付けています。ただし、予算上限に達し次第終了となるため、早めの申請が推奨されます。
マンションで活用する場合、まずアスベスト含有の有無を調査する必要があります(調査費用も補助対象となる自治体があります)。
アスベストが確認された場合、大規模修繕工事と併せて除去工事を実施することで、補助金を活用できます。
▶参考元:国土交通省「アスベスト対策Q&A」
5.先進的窓リノベ2025事業
先進的窓リノベ2025事業は、環境省が推進する「住宅省エネ2025キャンペーン」の一環として実施される、窓の断熱改修に特化した補助制度です。
高い断熱性能を持つ窓やドアへの改修工事が対象となります。
- 内窓設置:既存窓の内側に新たな窓を設置する工事(二重窓化)
- 外窓交換:カバー工法または窓枠を残して外窓を交換する工事
- ガラス交換:既存サッシはそのままに、ガラスのみを高断熱ガラスに交換する工事
- ドア交換:玄関ドアや勝手口ドアを高断熱ドアに交換する工事
これらの工事により、冷暖房費の削減と居住快適性の大幅な向上が期待できます。
| 補助対象 | 補助率・上限 | 補助額の例 |
|---|---|---|
| 窓改修(断熱性能向上) | ・工事費用の約1/2相当 ・1戸あたり最大200万円 | ・掃き出し窓(大):最大約10万円/箇所 ・小窓:最大約2万円/箇所 |
※窓のサイズや性能グレードによって細かく設定されています。
- 交付申請期間:令和7年3月下旬から遅くとも令和7年12月31日まで
- 工事着手期間:令和6年11月22日以降
- 工事完了期間:令和7年12月31日まで
予算の執行状況によっては早期に終了する可能性があるため、早めの申請が推奨されます。
分譲マンションの場合、管理組合が申請主体となり、共用部分の窓(廊下の窓など)や各戸の専有部分の窓を一括で改修する場合に活用できます。
賃貸マンションの場合は、オーナーが申請主体となります。
本事業は、他の住宅省エネ2025キャンペーン事業とワンストップで併用申請が可能です。
▶参考元:先進的窓リノベ 2025事業
6.子育てグリーン住宅支援事業
子育てグリーン住宅支援事業は、省エネ性能の高い住宅の新築・リフォームを支援する制度で、「住宅省エネ2025キャンペーン」の中核をなす補助事業です。
本事業では、「必須工事」と「任意工事」を組み合わせて実施する必要があります。
必須工事としては、以下のいずれか1つ以上を実施する必要があります。
- 開口部の断熱改修:窓・ドアの断熱性能向上
- 躯体の断熱改修:外壁、屋根・天井、床の断熱性能向上
- エコ住宅設備の設置:高効率給湯器、節水型トイレ、高断熱浴槽など
また、必須工事と併せて以下の任意工事を実施することも可能です。
- バリアフリー改修:手すり設置、段差解消、廊下幅拡張など
- 耐震改修工事
- 子育て対応改修:対面キッチン設置、防音性向上など
- 防災性向上改修:防災ガラス設置など
- リフォーム瑕疵保険または大規模修繕工事保証保険への加入
これらを組み合わせることで、総合的な性能向上が実現できます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 全世帯一律で 1戸あたり最大60万円 |
| 追加補助 | リフォーム瑕疵保険等に加入する場合、1契約あたり7,000円を加算 |
| 最低申請額 | 補助額の合計が5万円以上の工事が対象 |
| 対象世帯 | 子育て世帯・若者夫婦世帯に限らず、全世帯が対象 |
- 交付申請期間:令和7年3月31日から遅くとも令和7年12月31日まで
- 工事着手期間:令和6年11月22日以降
- 工事完了期間:遅くとも令和7年12月31日まで
予算の執行状況によっては早期に終了する可能性があるため、早めの申請が推奨されます。
既存マンションのリフォームが対象となります。
個々の区分所有者が専有部分の工事を申請する場合と、管理組合が共用部分の工事を一括で申請する場合(マンション大規模改修)の両方が可能です。
▶参考元:子育てグリーン住宅支援事業
7.次世代省エネ建材の実証支援事業
次世代省エネ建材の実証支援事業は、工期短縮が可能な高性能断熱材や、蓄熱・調湿機能を持つ次世代建材の効果を実証するための補助制度です。
本事業には3つの申請タイプがあり、それぞれ対象となる工事が異なります。
| 申請タイプ | 対象工事 |
|---|---|
| 外張り断熱(外断) | ・高性能断熱材または高性能断熱パネルによる外張り断熱改修 ・窓の断熱改修(併せて実施可) ・玄関ドアの断熱改修(併せて実施可) |
| 内張り断熱(内断) | ・高性能断熱材による内張り断熱改修 ・窓の断熱改修(併せて実施可) ・玄関ドアの断熱改修(併せて実施可) |
| 窓断熱 | ・窓の断熱改修(ガラス交換、内窓設置、外窓交換) ・玄関ドアの断熱改修(併せて実施可) |
| 申請タイプ | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 外張り断熱(外断) | 工事費用の1/2以内 | 戸建て:300〜400万円/戸 |
| 内張り断熱(内断) | 工事費用の1/2以内 | 戸建て:200万円/戸 戸集合住宅:150万円/戸 |
| 窓断熱 | 工事費用の1/2以内 | 戸建て・集合住宅:150万円/戸 |
集合住宅の場合、戸建住宅と比較して補助限度額が低く設定されています。
令和7年度の公募スケジュールは未発表です。例年、6月頃と9月頃の2回に分けて公募が実施されています(令和6年度は9月9日~11月29日に公募実施)。
集合住宅として申請可能で、特に内張り断熱や窓断熱は、マンションの専有部分や共用部分の改修に適しています。
なお、本事業は次世代建材の「実証」を目的としているため、工事前後の温度・湿度等の測定データ提出が必須となります。
▶参考元:次世代省エネ建材の実証支援事業
8.マンション総合対策モデル事業
マンション総合対策モデル事業は、令和7年度に新設された国土交通省の補助制度です。
老朽化マンションの長寿命化や、先導的な管理改善の取組を支援することを目的としています。
本事業には、複数のサブ事業が含まれています。
| 事業名 | 対象内容 |
|---|---|
| マンションストック長寿命化等モデル事業 | ・マンションの長寿命化に資する先導的な改修工事 ・管理組合の体制強化や合意形成支援などの計画策定支援 ・省エネ性能向上、耐震性能向上 ・バリアフリー性能向上を含む総合的な改修 |
| 老朽マンション対策モデル事業 | ・地方自治体が実施する老朽マンション対策の先導的な取組 ・管理不全マンションへの支援・建替え ・マンション敷地売却の円滑化支援 |
| 支援区分 | 補助内容 | 補助率・金額 |
|---|---|---|
| 計画支援 | 管理組合の合意形成や計画策定にかかる費用 | 定額補助 |
| 工事支援 | マンションの長寿命化に資する先導的な改修工事の費用 | 国が1/3を補助 |
※具体的な補助限度額は、事業の内容や規模によって異なります。
令和7年度の詳細な公募スケジュールは順次公表される予定です。事業の性質上、公募は年1~2回程度実施され、学識経験者による評価委員会で審査・採択されます。
管理組合が申請主体となり、特に築年数が古く大規模な改修が必要なマンション、または管理不全の兆候があるマンションで、先導的・モデル的な取組を行う場合に活用できます。
採択には、事業の先導性・波及効果・実現可能性などが評価されます。
本事業は令和7年度予算で27億円が計上されており、今後の老朽マンション対策の重要施策として位置づけられています。
▶参考元:マンション総合対策モデル事業
地方自治体が実施する大規模修繕工事の補助金制度
国の補助制度に加えて、都道府県や市区町村が独自に実施している補助金制度も数多く存在します。
自治体ごとに対象工事や補助額、申請条件が異なるため、マンションが所在する自治体の制度を詳しく調べる必要があります。
ここでは、代表的な補助制度の種類と、具体的な自治体の事例をご紹介します。
劣化診断補助事業(例: 東京都千代田区)
東京都千代田区では、「マンション劣化診断調査費助成制度」があります。
大規模修繕を実施する前や長期修繕計画を見直す際に行う、建物の劣化診断にかかる費用を補助する制度です。
対象は、現に住宅として使用されている築8年以上経過したマンションです。
調査の対象項目には、以下のようなものが含まれます。
- 防水の状況確認
- 壁面のひび割れや劣化状況
- 鉄部の腐食やサビの進行度
- 電気設備の老朽化
- 給排水設備の機能確認
| 区分 | 助成率 | 助成上限額 |
|---|---|---|
| 調査費用 | 調査に要する費用の 2/3 | 50万円 |
千代田区では、この他にも長期修繕計画作成費の助成(上限80万円)や、簡易耐震診断に係る費用の助成(上限20万円)など、マンション管理を支援する制度が充実しています。
詳しくは公益財団法人まちみらい千代田の公式サイトでご確認ください。
分譲マンション共用部分改修費用補助(例: 東京都中央区)
マンションの共用部の修繕工事に特化した補助制度です。
壁面改修、防水工事、防災対策、バリアフリー化などの設計・工事費用が対象となります。
東京都中央区では、区内にある築20年以上のマンションを対象に、修繕と防災対策にかかる設計・工事費用を助成しています。
対象となる工事内容は幅広く、大規模修繕の主要な工事項目をカバーしています。
具体的な対象工事は以下の通りです。
- 壁面改修工事
- 鉄部の塗装、取替え
- 屋上、バルコニー、外部共用廊下の防水工事
- 給排水管の更生、取替え
- 受水槽の耐震型への取替え
- エレベーターへの耐震改修工事
- 防災備蓄倉庫の設置
- 防火水槽の設置
- 電気設備への浸水対策工事
| 区分 | 助成率 | 助成上限額 |
|---|---|---|
| 設計費用 | 対象部分の設計費の 2/3 | 100万円 |
| 工事費用 | 対象工事費 × 10% の額の 2/3 | 1,000万円 |
中央区のような手厚い支援制度は、大規模修繕の費用負担を大きく軽減してくれます。
詳細は東京都中央区の公式サイトでご確認ください。
マンション耐震診断・耐震改修補助制度(例: 千葉県千葉市)
旧耐震基準で建設されたマンションの耐震診断や耐震改修工事にかかる費用を補助する制度です。
旧耐震基準とは、1981年5月31日以前に確認申請を受けた建物に適用されていた基準で、現在の新耐震基準と比べると地震への備えが不十分とされています。
千葉県千葉市には「分譲マンション耐震診断補助制度」があります。
この制度は耐震診断費用を助成するもので、耐震改修工事そのものは対象になりません。
補助額は、耐震診断費用の3分の2ですが、年度予算の範囲内で以下のように上限が設定されています。
| 診断の種類 | 補助上限額 |
|---|---|
| 予備診断 | 1棟あたり34,000円または1管理組合あたり17万円のいずれか低い額 |
| 本診断 | 1管理組合あたり400万円または補助対象面積に応じた上限額 |
令和6年度の受付は終了していますが、令和7年度も同様の補助制度が設けられる可能性があります。
旧耐震基準のマンションにお住まいの方は、自治体の最新情報をこまめにチェックしておきましょう。
詳細は、千葉県千葉市の公式サイトでご確認ください。
バリアフリー整備助成制度(例: 神奈川県横浜市)
マンションの敷地や共用部をバリアフリー化するための工事にかかる費用を助成する制度です。
高齢化が進む現代において、段差の解消や手すりの設置は、居住者の安全と快適性を大きく向上させます。
神奈川県横浜市では、「マンションの共用部等のバリアフリー化補助」の制度があります。
対象となるバリアフリー化工事の範囲は広く、以下のような箇所が含まれます。
- 敷地内の通路の段差解消
- 駐車場のスロープ設置
- 廊下の手すり取り付け
- 階段の滑り止め設置
- エレベーターの音声案内装置設置
| 工事内容 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| バリアフリー化等工事(一般) | 工事費の1/3 | 30万円/戸 |
| 手すり設置工事 | 工事費の1/3 | 30万円または8,000円/戸のうち低い方 |
横浜市マンション登録制度に登録することが補助要件となっています。
詳しい申請方法は、横浜市の公式サイトでご確認ください。
大規模修繕工事でお悩みの管理組合の方
「ファシリテーション」で談合をなくそう!
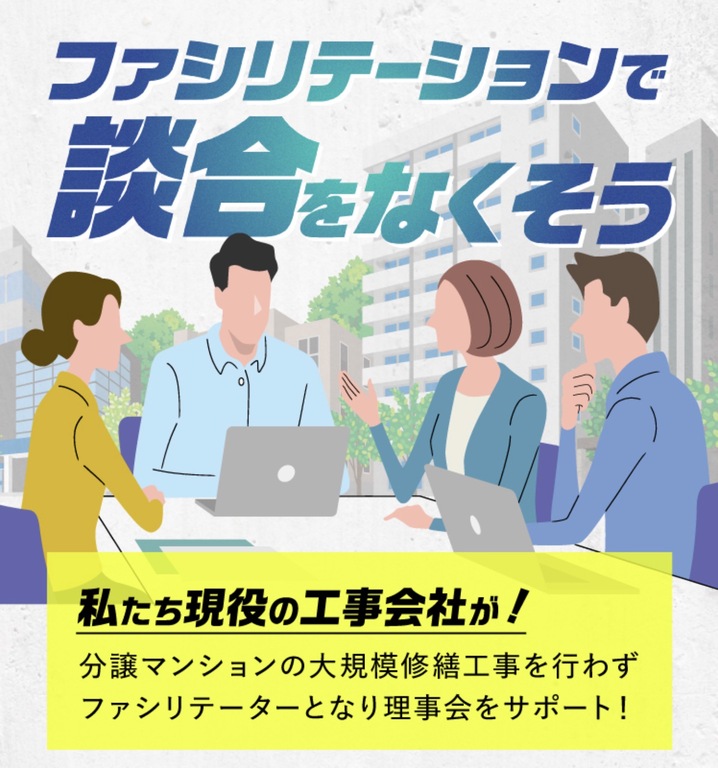
\お問い合わせや工事のお見積もり無料!/
豊富な実績と専門知識を持つスタッフが、
皆様の疑問や不安にお答えし、最適な解決策をご提案いたします。
大規模修繕工事の補助金申請の流れ【6ステップで解説】
補助金を活用するには、申請から採択、工事完了後の実績報告まで、一連の手続きを正しく進める必要があります。
ここでは、補助金申請の全体像を6つのステップに分けて、それぞれの段階で何をすべきか、どんな点に注意すべきかを詳しく解説します。
ステップ1:情報収集と制度確認
補助金申請の第一歩は、自分のマンションで利用できる制度を見つけることです。
国や自治体のウェブサイト、マンション管理センターなどの情報を活用して、対象となる補助金をリストアップしましょう。
情報収集の際は、以下のポイントを確認します。
- 補助金の対象となる工事内容
- 補助額や補助率
- 申請の受付期間
- 必要な書類や条件
- 過去の採択実績
特に重要なのが、申請の受付期間です。補助金の多くは年度ごとに予算が決まっており、予算に達すると募集が終了します。
早めに情報をキャッチし、計画的に準備を進めることが成功のカギとなります。
不明な点がある場合は、自治体の住宅課や、マンション管理センターの相談窓口に問い合わせると、丁寧に教えてもらえます。
ステップ2:事前相談・専門家への依頼
活用できそうな補助金が見つかったら、次は施工業者やマンション管理コンサルタントに相談します。
補助金の申請には専門的な知識が必要で、書類の不備があると不採択になる可能性が高まります。
専門家に相談することで、以下のようなサポートが受けられます。
- 補助金の対象となる工事内容の提案
- 申請書類の作成支援
- 必要な調査や診断の実施
- 工事スケジュールと申請スケジュールの調整
- 過去の申請実績に基づくアドバイス
補助金の申請実績が豊富な業者であれば、手続きの流れを熟知しているため、スムーズに進められます。
また、自治体によっては事前相談が必須となっている場合もあります。
申請前に窓口を訪問し、計画内容が補助対象になるかを確認しておくと、後のトラブルを避けられます。
ステップ3:管理組合での承認取得
補助金を申請するには、管理組合の総会で承認決議を得る必要があります。
大規模修繕工事そのものの承認と合わせて、補助金申請についても議題に含めましょう。
総会で説明すべき内容は、次の通りです。
- 申請する補助金の制度名と概要
- 補助対象となる工事内容
- 補助金の額と受け取り時期
- 申請に必要な書類や手続き
- 万が一不採択になった場合の対応
住民の中には、補助金制度をよく知らない方もいます。
「補助金を活用することで、修繕積立金の負担を軽減できる」というメリットを分かりやすく説明することで、賛同を得やすくなります。
また、補助金は審査制であるため、不採択のリスクも正直に伝えておくことが大切です。
「補助金が受けられなくても、修繕積立金で工事を実施する」という代替案も用意しておくと、住民の不安を和らげられます。
ステップ4:申請書類の作成・提出
管理組合の承認が得られたら、いよいよ申請書類の作成に取りかかります。
この段階は最も重要で、書類の不備があると審査すら受けられないこともあります。
一般的に必要となる書類は、以下の通りです。
- 補助金交付申請書(所定の様式)
- 工事の設計図書、仕様書
- 工事費用の見積書
- 管理組合の総会決議書
- 建物の登記事項証明書
- 劣化診断報告書(制度による)
- 長期修繕計画書(制度による)
書類の作成は、施工業者やコンサルタントに依頼するのが一般的です。専門家のサポートを受けることで、記載ミスや書類不足を防げます。
提出前には、複数人で書類をチェックしましょう。誤字脱字や数字の間違い、押印漏れなど、些細なミスが不採択につながることもあります。
申請期限ギリギリの提出は避け、余裕を持って準備を進めることが成功への近道です。
ステップ5:採択・交付決定の通知受領
申請書類を提出すると、自治体や事務局による審査が行われます。
審査には通常1〜2か月程度かかりますが、制度や時期によって異なります。
審査の結果は、書面で通知されます。採択された場合は「交付決定通知書」が届き、正式に補助金を受け取る権利が確定します。
この通知を受け取ってから、初めて工事契約を結ぶことができます。
もし不採択になった場合は、以下の対応を検討しましょう。
- 不採択の理由を確認し、改善点を把握する
- 再申請が可能かどうかを確認する
- 他の補助金制度への切り替えを検討する
- 補助金なしで工事を進めるか、延期するかを管理組合で協議する
不採択になっても、理由を確認して改善すれば、次の機会に採択される可能性があります。
諦めずに、次のステップを考えることが大切です。
ステップ6:工事実施・完了報告・補助金受領
交付決定通知を受け取ったら、工事契約を締結し、工事を開始します。
工事期間中は、施工業者と密に連絡を取り、計画通りに進んでいるかを確認しましょう。
工事が完了したら、実績報告書を提出します。報告書には、以下のような書類を添付します。
- 工事完了報告書
- 工事費用の支払いを証明する書類(領収書、振込明細など)
- 工事の写真(着工前、施工中、完成後)
- その他、制度で指定された書類
実績報告書が受理され、内容が確認されると、補助金が指定の口座に振り込まれます。補助金の入金までには、報告書提出から1〜2か月程度かかることが一般的です。
ここで重要なのが、補助金は工事完了後の受け取りであるという点です。
工事費用は一旦全額を支払う必要があるため、修繕積立金や借入金などで資金を確保しておく必要があります。
補助金ありきの資金計画は危険ですので、必ず全額を用意できる状態で工事を進めましょう。
大規模修繕工事の補助金を活用する際の注意点
補助金は大変魅力的な制度ですが、利用にあたってはいくつか注意すべきポイントがあります。
これらを見落とすと、せっかくの申請が無駄になってしまったり、資金計画に支障をきたしたりする恐れがあります。
工事契約前に申請が必須
補助金制度の多くは、工事契約を結ぶ前に申請を完了させることが絶対条件となっています。
契約後に補助金の存在を知っても、遡って適用することはできません。
工事のスケジュールは、以下の順序で進める必要があります。
- 補助金の情報収集と制度確認
- 申請書類の準備と提出
- 交付決定通知の受領
- 工事契約の締結
- 工事の着工
この順序を守らないと、補助金を受け取ることができません。
特に、施工業者との契約を急ぎたくなる気持ちは分かりますが、補助金を活用する場合は、必ず交付決定を待ってから契約を結びましょう。
また、事業者登録が必要な制度もあります。施工業者が補助金の事業者登録を済ませていない場合、その業者では補助金を利用できません。
業者選定の段階で、「この補助金制度に対応できるか」を必ず確認しておきましょう。
補助金は工事完了後の受け取り
補助金が口座に振り込まれるのは、工事が完了し、実績報告書を提出した後です。
工事費用は一旦、管理組合が全額を支払う必要があります。
資金計画を立てる際は、以下の点に注意しましょう。
- 修繕積立金だけで工事費用の全額を賄えるか確認する
- 不足する場合は、金融機関からの借入を検討する
- 補助金の入金時期を確認し、返済計画に組み込む
- 万が一、補助金が不採択になった場合の代替案を用意する
「補助金が受け取れるから、その分の積立金は不要」と考えるのは危険です。
補助金はあくまで「後から受け取れる支援金」であり、工事費用の支払いには使えません。必ず全額を用意できる状態で工事に臨みましょう。
予算上限に達すると募集終了
補助金は、国や自治体の予算の中から交付されます。
そのため、申請や受理の件数が予算額に達すると、募集期間中であっても受付が終了することがあります。
早めの申請が重要な理由は、次の通りです。
- 人気の高い制度は、募集開始から数か月で予算上限に達する
- 年度末に近づくほど、予算の残りが少なくなる
- 申請の集中する時期(年度初めや秋口)は競争率が高い
補助金の活用を検討している場合は、年度が始まったらすぐに情報収集を開始し、できるだけ早い時期に申請できるよう準備を進めましょう。
特に令和7年度の制度は、前年度の実績を参考に募集時期を予測することができます。
また、制度によっては複数回に分けて募集が行われることもあります。
第1回の募集で間に合わなくても、第2回に応募できる可能性があるため、最新情報を定期的にチェックすることが大切です。
不採択リスクを想定した資金計画を
補助金は審査制であり、申請すれば必ず受け取れるわけではありません。
書類の不備や予算の都合、他の申請との競争などにより、不採択になる可能性もあります。
不採択リスクに備えるためには、以下のような対策が有効です。
- 補助金なしでも工事を実施できる資金計画を立てる
- 複数の補助金制度を同時に調査し、選択肢を増やす
- 不採択になった場合の代替案を事前に管理組合で共有する
- 金融機関からの借入枠を事前に確保しておく
補助金を「確実にもらえるもの」として資金計画を立てるのではなく、「受け取れたらラッキー」という心構えで臨むことが、リスク管理の基本です。
不採択になっても工事を進められるよう、柔軟な計画を立てておきましょう。
補助金以外で大規模修繕工事の費用を削減する方法
補助金が活用できない場合や、不採択になった場合でも、大規模修繕工事の費用を削減する方法はいくつかあります。
ここでは、補助金以外で費用を抑えるための実践的な方法を3つご紹介します。
これらの方法は、補助金と併用することで、さらに大きな効果を生み出せます。
複数業者から相見積もりを取得する
大規模修繕工事の費用は、施工業者によって大きく異なります。同じ工事内容でも、業者によって数百万円の差が出ることも珍しくありません。
相見積もりを取ることで、以下のメリットがあります。
- 適正な価格相場を把握できる
- 業者間の競争により、価格が下がる可能性がある
- 各業者の提案内容や対応を比較できる
- 不透明な費用や過剰な工事内容を見抜ける
相見積もりを取る際は、最低でも3社以上に依頼しましょう。
見積書の内容を比較する際は、単に総額だけでなく、各工事項目の単価や数量、使用する材料のグレードなども細かくチェックすることが重要です。
また、極端に安い見積もりには注意が必要です。手抜き工事や追加費用の発生リスクがあるため、価格だけでなく、業者の実績や信頼性も総合的に判断しましょう。
過去の施工事例や、他のマンションでの評判を確認することをおすすめします。
工事内容・仕様の見直し
大規模修繕工事では、すべての工事を一度に実施する必要はありません。
緊急性の高いものと、先送りできるものを見極め、優先順位をつけることで、当面の費用を抑えられます。
工事内容を見直す際のポイントは、次の通りです。
- 緊急性の高い工事を優先 ▶ 放置すると大きな被害につながる工事
- 過剰仕様を避ける ▶ 必要以上に高級な材料や設備を選ばない
- 工事の分割実施を検討 ▶ 全体を数回に分けて実施することで、一度の負担を軽減
- 代替工法の検討 ▶ 同じ効果を得られる、より低コストな工法がないか検討
ただし、コスト削減を優先しすぎて、必要な工事を省いてしまうのは危険です。
建物の安全性や耐久性に関わる工事は、専門家の意見を尊重し、適切に実施することが大切です。
工事内容の見直しは、マンション管理士や建築士などの第三者専門家に相談することで、客観的な判断ができます。
工事時期の調整
大規模修繕工事の費用は、実施する時期によっても変動します。
建設業界には繁忙期と閑散期があり、閑散期に工事を発注することで、費用を抑えられる可能性があります。
工事時期を調整するメリットは、以下の通りです。
- 閑散期は人件費や材料費が割安になる傾向がある
- 業者のスケジュールに余裕があり、丁寧な施工が期待できる
- 天候の安定した時期を選べば、工期の遅延を防げる
一般的に、建設業界の閑散期は冬季(12月〜2月)とされています。
ただし、寒冷地では冬季の工事が難しい場合もあるため、マンションの所在地や工事内容に応じて判断しましょう。
また、計画的な修繕を実施することで、突発的な大規模工事を避けられます。
定期的な点検と小規模な補修を繰り返すことで、建物の劣化を緩やかにし、一度に必要となる修繕費用を抑えることができます。
長期修繕計画を5年ごとに見直し、実態に合った計画にアップデートすることも、費用の適正化につながります。
大規模修繕工事の補助金に関するよくある質問(FAQ)
ここまで補助金制度について詳しく解説してきましたが、管理組合の皆さまからよく寄せられる疑問や不安にお答えします。
実際に補助金を活用する際に役立つ情報ですので、ぜひ参考にしてください。
Q1. 補助金は管理組合でも申請できますか?
はい、分譲マンションの管理組合は補助金の申請主体となることができます。
ただし、申請には管理組合の総会決議が必要です。補助金を申請することについて、総会で承認を得てから手続きを進めましょう。
また、補助金によっては、管理組合の代表者(理事長など)が申請者となり、管理組合全体を代表して手続きを行います。
申請書類には、管理組合の総会議事録や、管理規約の写しなどを添付することが一般的です。
事前に必要書類を確認し、余裕を持って準備を進めることをおすすめします。
Q2. 複数の補助金を併用できますか?
補助金の併用については、制度ごとに異なるルールが設定されています。
国の補助金同士は原則として併用できないことが多いですが、国の補助金と地方自治体の補助金は併用できる場合もあります。
併用を検討する際は、以下の点を確認しましょう。
- 各補助金の募集要項に、他の補助金との併用に関する記載がないか
- 併用する場合、合計の補助額に上限が設定されていないか
- 申請窓口や事務局に、併用の可否を直接問い合わせる
複数の補助金を併用できれば、より大きな費用軽減効果が期待できます。
ただし、申請や報告の手続きが複雑になるため、専門家のサポートを受けることをおすすめします。
Q3. 過去に補助金を受けた場合、再度申請できますか?
過去に補助金を利用した場合の再申請については、制度によって条件が異なります。
同じ補助金を繰り返し利用できる制度もあれば、一定期間は再申請できない制度もあります。
再申請を検討する際は、次のポイントを確認しましょう。
- 前回の補助金利用から何年経過しているか
- 制度の募集要項に、再申請に関する制限が記載されていないか
- 前回と今回で、補助対象となる工事内容が異なるか
過去に補助金を利用したことがある場合は、修繕履歴を確認し、どの制度をいつ利用したかを把握しておくことが大切です。
自治体の窓口に問い合わせれば、再申請の可否について教えてもらえます。
Q4. 不採択になった場合はどうすればよいですか?
不採択になった場合でも、落ち着いて次の対応を検討しましょう。
不採択は決して珍しいことではなく、適切に対処すれば次の機会につなげられます。
不採択後に取るべき行動は、以下の通りです。
- 不採択の理由を自治体や事務局に確認する
- 指摘された点を改善し、再申請が可能かを問い合わせる
- 他の補助金制度への切り替えを検討する
- 補助金なしで工事を進めるか、延期するかを管理組合で協議する
- 費用削減の方法を見直し、資金計画を再構築する
不採択になった理由を把握することで、次回の申請で同じミスを繰り返さずに済みます。
書類の不備であれば修正して再提出できる場合もありますし、他の制度であれば採択される可能性もあります。諦めずに、次のステップを考えることが大切です。
Q5. 補助金を利用すると工事の自由度は制限されますか?
補助金を利用する場合、一定の条件や基準を満たす必要があるため、工事内容に制約が生じることがあります。
ただし、これは「自由度が制限される」というよりも、「適正な工事を実施するための基準が設けられている」と捉えるべきです。
補助金利用時の主な制約は、次の通りです。
- 使用する材料や設備が、一定の性能基準を満たす必要がある
- 工事の設計や施工方法が、補助金の趣旨に沿ったものである必要がある
- 工事完了後に、性能基準を満たしているかの検査が行われる
- 事業者登録を済ませた施工業者に依頼する必要がある(制度による)
これらの制約は、補助金を適切に活用し、質の高い工事を実施するために設けられています。
むしろ、基準を満たすことで、建物の性能が向上し、長期的な資産価値の維持につながります。工事の質を担保する仕組みと前向きに捉えましょう。
Q6. 補助金を受けると将来の修繕計画に影響しますか?
補助金を利用して大規模修繕工事を実施しても、将来の修繕計画に悪影響を及ぼすことは基本的にありません。
むしろ、費用負担が軽減されることで、修繕積立金に余裕が生まれ、次回以降の修繕計画をより柔軟に立てられるメリットがあります。
補助金利用が将来に与える影響として、以下の点が考えられます。
- 修繕積立金の残高が増え、次回の修繕に備えやすくなる
- 質の高い工事を実施できるため、建物の劣化が緩やかになる
- 長期修繕計画の見直し時に、より現実的な計画を立てられる
- 過去の補助金利用実績が、次回申請時の参考になる
ただし、同じ補助金を再度利用する場合には、一定期間の制限がある場合もあります。
長期修繕計画を作成・見直す際は、補助金の利用履歴も記録しておき、次回の修繕時に活用できるよう備えておくことをおすすめします。
まとめ
ここまで、大規模修繕工事における補助金制度について、令和7年度の最新情報をもとに詳しく解説してきました。
最後に、重要なポイントをチェックリスト形式で振り返りましょう。
- 補助金は国と地方自治体の両方の制度を確認する
- 工事契約前に必ず申請を完了させる
- 補助金は工事完了後の受け取りなので、全額の資金を事前に用意する
- 申請書類は専門家のサポートを受けて正確に作成する
- 管理組合の総会で承認決議を得る
- 予算上限があるため、早めに申請する
- 不採択リスクを想定し、代替案を用意しておく
- 補助金以外の費用削減方法も併せて検討する
補助金制度は、マンション管理組合にとって非常に心強い支援制度です。
数百万円単位で費用負担を軽減できる可能性があるため、大規模修繕を控えている管理組合の皆さまは、ぜひ積極的に活用を検討してください。
ただし、補助金はあくまで「費用負担を軽減するための手段の一つ」です。不採択になる可能性も考慮し、柔軟な資金計画を立てることが大切です。
相見積もりや工事内容の見直し、工事時期の調整など、他の費用削減方法も組み合わせることで、より確実にコストを抑えられます。
ご不明な点があれば、自治体の窓口やマンション管理の専門家に相談することをおすすめします。
皆さまのマンションの大規模修繕が、スムーズに進むことを心より願っております。








