
マンション大規模修繕の1回目と2回目の違いとは?時期・費用・工事内容を徹底比較
2025/07/24
マンション管理組合の理事として、または区分所有者として「2回目の大規模修繕って1回目とどう違うの?」「費用はどのくらい変わるの?」といった疑問をお持ちではありませんか。
これまで数多くの管理組合の皆様とお話しする中で、特に2回目の大規模修繕への不安や疑問を強く感じています。
確かに、1回目と2回目では工事の規模も内容も大きく異なり、適切な知識がないと思わぬトラブルや費用超過を招く可能性があります。
この記事では、1回目と2回目の大規模修繕の具体的な違いから実施時期、費用相場、そして成功のポイントまで、長年の実務経験をもとに分かりやすく解説いたします。
読み終える頃には、2回目の大規模修繕に向けた明確な準備方針が見えてくるはずです。
また、大規模修繕の目的や必要性・基本的な工事内容や流れ・費用などを理解しておくと、本記事の理解がより深まります。
こちらの記事では「大規模修繕とは」をテーマに、基本的な知識をわかりやすく解説していますので、あわせてご覧ください。
目次
1回目と2回目の大規模修繕の基本的な違い
マンションの大規模修繕は回数を重ねるごとに、その性格が根本的に変化します。
最も重要なのは建物の劣化進行度と修繕の目的そのものが異なるという点です。
劣化進行度と修繕目的の違い
1回目のマンション大規模修繕は新築から12~15年程度で実施されるため、基本的には「予防保全」としての性格が強くなります。
建物の基本性能を維持し、美観を回復することが主な目的となります。
対照的に2回目は築25~30年程度での実施となり、経年劣化がより深刻化した状態での「機能回復」が中心となります。
単なる補修では対応できず、根本的な改修や設備の交換が必要になる箇所が急激に増加するのが特徴です。
国土交通省の「令和3年度マンション大規模修繕工事に関する実態調査」によると、2回目では給水設備工事の実施率が1回目の約2倍、建具・金物等の工事実施率も大幅に上昇していることが確認されています。
工事の選択性と緊急性の違い
1回目では「今回は見送って次回に」という判断が可能だった工事も、2回目では必須工事となるケースが多数あります。
これは劣化の進行により、建物全体のバランスを保つために必要不可欠な修繕が増えるためです。
例えば屋上防水工事について、1回目では部分補修で対応できていた箇所も、2回目では雨漏りリスクの高まりにより全面改修が避けられなくなります。
また、設備関連では法定点検の結果や安全基準の観点から、交換時期の先送りが困難になる場合が多くなります。
1回目と2回目の大規模修繕の実施時期と周期の違い
マンションの大規模修繕の周期や実施時期は建物の劣化状況や管理組合の方針によって決まりますが、一般的な傾向を理解することで適切な計画策定が可能になります。
1回目の実施時期
国土交通省の調査データによると、1回目の大規模修繕は築15年以下で実施される割合が最も高く、具体的には築12~15年の間に実施するマンションが全体の約7割を占めています。
この時期設定の根拠となるのが外壁塗装の耐用年数です。
一般的なアクリルシリコン系塗料の耐用年数は8~12年とされており、新築時の塗装保護機能が低下し始める時期と重なります。
そのため1回目は「建物の基本性能維持」という予防的観点からの実施が基本となります。
また、1回目の時期は新築時の保証期間(通常10年)が終了する頃でもあり、施工不良があれば発見・対応する最後のチャンスという意味でも重要なタイミングです。
2回目の実施時期と周期
2回目の大規模修繕は築26~30年で実施される割合が最も多く、1回目からのマンションの修繕周期は平均13~14年となっています。
ただし、以下の要因により実施時期は前後する可能性があります。
- 1回目の工事品質▶︎ 施工の丁寧さにより劣化進行速度が変化
- 建物の立地環境▶︎ 海沿い、幹線道路沿いなどの厳しい環境では早期劣化
- 使用材料のグレード▶︎ 高耐久材料使用により周期延長の可能性
- 日常的なメンテナンス頻度▶︎ 定期的な小修繕により大規模修繕周期への影響
これらの要因を総合的に判断するため、築20年を過ぎた時点で建物診断を実施し、科学的根拠に基づいた実施時期の決定を行うことが推奨されます。
1回目と2回目の大規模修繕の工事内容と範囲の違い
1回目と2回目では対象となる工事範囲が大幅に拡大し、工事の性質そのものが変化します。
具体的な違いを工事分野別に詳しく見ていきましょう。
外壁関連工事の範囲拡大
1回目の外壁工事は主に塗装の塗り替えとシーリングの打ち替えが中心となります。
表面的な劣化への対応が主目的で、下地処理も軽微なケースがほとんどです。
2回目では外壁塗装に加えて、以下のような大規模な改修工事が必要になります。
| 工事内容 | 1回目 | 2回目 |
|---|---|---|
| 外壁塗装 | 塗り替えのみ | 下地補修+塗り替え |
| タイル工事 | 部分補修 | 張り替え・全面補修 |
| シーリング | 打ち替え | 打ち替え+構造補修 |
| バルコニー | 清掃・軽微補修 | 防水・構造補修 |
特にタイル外壁のマンションでは、2回目でタイルの浮きや剥落が深刻化し、大規模な張り替え工事が必要になる場合があります。
防水工事の全面化
屋上防水は1回目と2回目で最も違いが顕著に現れる工事分野です。
1回目では防水シートの部分的な補修や保護塗料の塗り替えで済んでいた箇所も、2回目では防水層の全面的な改修が必要となります。
この背景には防水材料の耐用年数(一般的に12~15年)があり、2回目の時期は防水性能の限界点と重なるためです。
雨漏りが発生してからでは建物への被害が深刻化するため、予防的な全面改修が不可欠となります。
設備関連の大幅な更新
2回目で最も費用に影響するのが設備関連の工事です。
多くの設備機器が耐用年数を迎え、修理ではなく交換が必要な時期となります。
代表的な更新対象設備は以下の通りです。
- エレベーター▶︎ 耐用年数20~25年、リニューアル費用500~1,500万円/基
- 給水設備▶︎ 受水槽・ポンプ類の交換、配管の部分更新
- 消防設備▶︎ 自動火災報知設備、消火栓の更新
- 電気設備▶︎ 分電盤、照明器具、インターホンシステム
- 機械式駐車場▶︎ 機械部品の大幅な交換・オーバーホール
これらの設備更新は安全性確保の観点から延期が困難で、2回目の大規模修繕費用を大幅に押し上げる要因となっています。
共用部分の機能向上工事
2回目では単なる修繕だけでなく、建物の付加価値向上を目的とした改良工事も重要な検討事項となります。
築25~30年が経過すると、竣工時と比較して住宅設備の標準的なレベルが大幅に向上しているためです。
主な機能向上工事としては、宅配ロッカーの設置、LED照明への全面交換、Wi-Fi環境の整備、バリアフリー対応などがあります。
これらの工事は入居者の満足度向上と資産価値の維持に直結するため、長期的な視点での投資判断が重要となります。
1回目と2回目の大規模修繕の費用の違い
2回目の大規模修繕では工事範囲の拡大により、費用面でも1回目との大きな差が生じます。
適切な資金計画のために具体的な費用構造を理解することが重要です。
総工事費用の比較と増加要因
国土交通省の「令和3年度マンション大規模修繕工事に関する実態調査」に基づく費用比較は以下の通りです。
| 費用指標 | 1回目 | 2回目 | 増加率 |
|---|---|---|---|
| 1戸あたり費用 | 75~100万円 | 100~125万円 | 約25%増 |
| 床面積あたり(1㎡) | 1.0~1.3万円 | 1.2~1.5万円 | 約15%増 |
| 総工事費(50戸想定) | 3,750~5,000万円 | 5,000~6,250万円 | 1,250万円増 |
この費用増加の主な要因は工事範囲の拡大です。
1回目では外壁・屋上・共用部分の表面的な修繕が中心でしたが、2回目では設備更新や構造的な改修工事が大幅に増加します。
特に影響が大きいのはエレベーターのリニューアル工事で、1基あたり500~1,500万円という高額な費用が発生します。
50戸程度のマンションでエレベーター1基の場合、この費用だけで1戸あたり10~30万円の負担増となります。
修繕積立金の不足リスクと対策
2回目の大規模修繕で最も深刻な問題となるのが修繕積立金の不足です。
多くのマンションで当初の長期修繕計画が楽観的すぎたため、実際の工事費用との間に大きな乖離が生じています。
修繕積立金不足の主な原因と対策は以下の通りです。
- 建設費・人件費の上昇▶︎ 計画策定時との物価差による費用増
- 設備更新費用の過小評価▶︎ エレベーター等の高額設備費用の見積もり不足
- 修繕積立金の段階増額不実施▶︎ 竣工時の低額設定のまま据え置き
- 想定外の劣化進行▶︎ 立地環境や施工品質による予想以上の劣化
これらのリスクに対応するため、築15年時点で長期修繕計画の全面的な見直しを行い、必要に応じて修繕積立金の増額や一時金の徴収を検討することが重要です。
工事費用の最適化手法
2回目の大規模修繕では費用が高額になる傾向がある一方で、適切な計画により費用を最適化することも可能です。
効果的な手法をご紹介します。
建物診断による優先順位の明確化が最も重要な費用最適化手法です。
専門業者による詳細な診断により、緊急性の高い工事と延期可能な工事を科学的に判別できます。
診断費用は20~100万円程度ですが、不要な工事の排除により数百万円の費用削減効果が期待できます。
また、工事の分割実施も有効な手法です。
全ての工事を一度に実施するのではなく、緊急性に応じて2~3回に分けることで、修繕積立金の計画的な活用が可能になります。
ただし、仮設費用の重複などにより総費用は若干増加する点に注意が必要です。
大規模修繕工事でお悩みの管理組合の方
「ファシリテーション」で談合をなくそう!
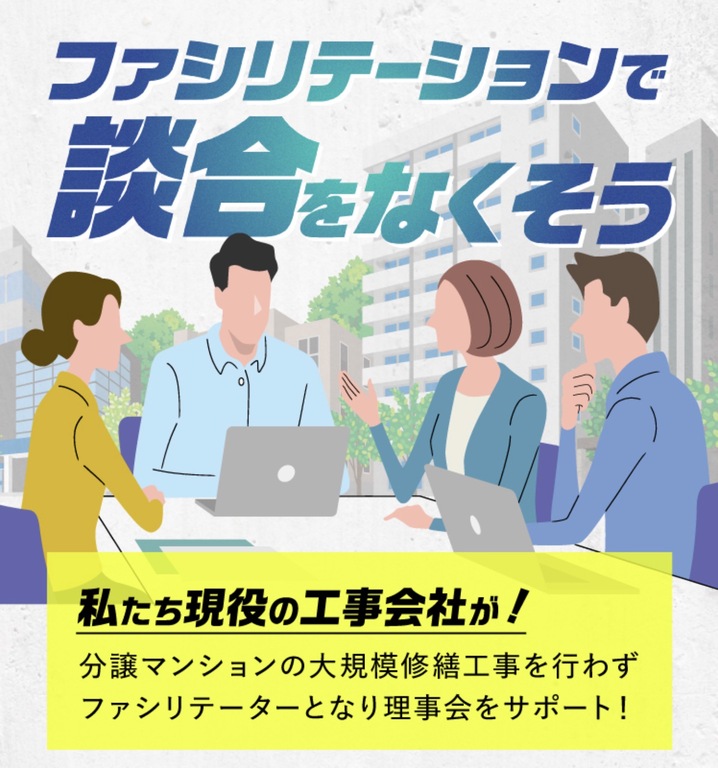
\お問い合わせや工事のお見積もり無料!/
豊富な実績と専門知識を持つスタッフが、
皆様の疑問や不安にお答えし、最適な解決策をご提案いたします。
1回目と2回目の大規模修繕で注意すべきポイントの違い
1回目と2回目では、工事を成功させるために注意すべきポイントが大きく異なります。
これらの違いを理解することで、トラブルの回避と満足度の高い修繕工事の実現が可能になります。
合意形成の複雑化への対応
2回目の大規模修繕では、1回目と比較して合意形成がより困難になる傾向があります。
この背景には複数の要因があります。
まず、費用負担の増大により、区分所有者間で工事内容や予算に対する意見の相違が生じやすくなります。
特に設備のグレードアップ工事については、必要性を感じる住民と費用負担を懸念する住民との間で対立が生じる場合があります。
また、築25~30年が経過すると住民の年齢構成も変化し、高齢化により工事への関心や参加意欲に差が生じることもあります。
さらに賃貸住戸の増加により、実際の居住者と区分所有者が異なるケースも多くなり、利害関係の調整がより複雑になります。
これらの課題に対処するため、工事計画の早期段階から住民アンケートを実施し、ニーズや意見を幅広く収集することが重要です。
また、工事の必要性と効果を分かりやすく説明する資料作成と、十分な説明会の開催により、合意形成をサポートすることが必要となります。
工事期間の長期化と生活への影響
2回目の大規模修繕は工事範囲の拡大により、1回目より工期が長期化する傾向があります。
一般的に1回目が3~6ヶ月程度であるのに対し、2回目は6~12ヶ月に及ぶ場合があります。
長期化の主な要因は以下の通りです。
- 設備工事の複雑性▶︎ エレベーター停止期間、断水・停電作業の増加
- 居住者への配慮▶︎ 騒音・振動を伴う作業の時間制限
- 安全対策の強化▶︎ 足場設置範囲の拡大、安全確保のための工程調整
- 天候の影響▶︎ 外壁・防水工事の天候依存度の高まり
長期化による生活への影響を最小限に抑えるため、工事スケジュールの詳細な説明と定期的な進捗報告が不可欠です。
また、エレベーター停止期間中の代替手段の確保や、騒音が特に激しい作業の事前告知など、きめ細かい住民サポートが求められます。
品質管理と業者選定の重要性増大
2回目の大規模修繕では工事の複雑性により、施工業者の技術力と管理能力がより重要となります。
1回目では表面的な工事が中心だったため、多くの業者が対応可能でしたが、2回目では設備更新や構造的な改修を含むため、高度な専門性と豊富な経験が必要となります。
特に注意すべきは、複数の専門工事が同時進行することによる工程管理の複雑化です。
外壁工事、防水工事、設備更新工事が相互に影響し合うため、全体を統括できる施工管理能力が施工品質を左右します。
業者選定では価格だけでなく、類似規模・内容の工事実績、現場代理人の経験年数、品質管理体制などを総合的に評価することが重要です。
また、工事中の定期的な第三者検査の実施により、品質確保を図ることも効果的な対策となります。
3回目のマンション大規模修繕に備えた視点
2回目の大規模修繕を計画・実施する際には、将来の3回目の大規模修繕(築40~45年頃)を見据えた長期的視点が重要になります。
この時期のマンションは建物の老朽化がさらに進行し、根本的な性能向上や建て替えとの比較検討が必要な段階を迎えます。
3回目の大規模修繕では、建物の長寿命化という新たな観点が加わります。
単なる修繕にとどまらず、耐震性能の向上、省エネルギー性能の大幅な改善、バリアフリー化の完全実施など、現代の住宅水準に合わせた根本的な改良工事が中心となります。
そのため2回目の修繕計画策定時には、3回目で実施予定の大規模改修工事との整合性を考慮することが重要です。
例えば、2回目で設備を更新する際には、3回目での全面的なシステム変更を想定した仕様選択を行うことで、長期的なコスト最適化が図れます。
また、3回目の時期は建て替えとの比較検討が本格化する時期でもあります。
修繕による建物延命と建て替えによる全面更新、どちらが経済的・機能的に優位かを判断するため、2回目修繕後の建物状況や住民意向の変化を継続的に把握することが重要となります。
修繕積立金の計画についても、3回目では1~2回目を大幅に上回る費用(1戸あたり200~300万円程度)が必要となる可能性があります。
2回目修繕完了後は速やかに長期修繕計画を見直し、段階的な積立金増額や特別徴収の検討を開始することが、将来的な資金不足を回避する鍵となります。
1回目と2回目の大規模修繕に関するよくある質問【FAQ】
大規模修繕の計画・実施過程でよく寄せられる質問について、実務経験に基づいてお答えします。
Q.1回目の大規模修繕を延期することは可能ですか?
A.建物の状況によっては延期も可能ですが、慎重な判断が必要です。
外壁塗装の劣化が軽微で、防水性能に問題がない場合は1~2年程度の延期は検討できます。
ただし、延期により生じるリスクも理解しておく必要があります。
劣化の進行により、本来であれば塗装の塗り替えで済んだ箇所が下地補修まで必要になり、結果的に費用が増加する可能性があります。
延期を検討する場合は、必ず建物診断を実施し、専門家の意見を参考に判断することをお勧めします。
Q.2回目の修繕積立金が不足している場合の対策は?
A.修繕積立金不足は多くのマンションで発生している深刻な問題です。
一時金の徴収が最も一般的な対策で、不足分を区分所有者から一括で集める方法です。
ただし、高額になる場合は住民の経済的負担が大きく、合意形成が困難になる可能性があります。
修繕積立金の増額により、数年間で不足分を補う方法もあります。月額3,000~5,000円程度の増額を2~3年継続することで、ある程度の不足は解消できます。
さらに、金融機関からの借入や工事の分割実施により、一時的な資金負担を軽減する方法もあります。
どの方法が最適かは、マンションの状況や住民の意向により異なるため、管理組合での十分な検討が必要です。
Q.工事中のエレベーター停止期間はどの程度ですか?
A.エレベーターのリニューアル工事における停止期間は、工事方式により大きく異なります。
制御部品型リニューアルの場合は1~2週間程度、準撤去型リニューアルでは3~4週間程度、全撤去型リニューアルでは1~1.5ヶ月程度の停止期間が必要となります。
停止期間中は階段での移動となるため、高齢者や身体の不自由な住民への配慮が重要です。
事前に代替手段の検討や、重い荷物の運搬支援体制の整備など、住民サポート体制を充実させることが求められます。
工事業者と事前に詳細なスケジュールを確認し、住民への十分な事前告知を行うことも重要なポイントです。
Q.大規模修繕の施工業者はどのように選定すべきですか?
A.2回目の大規模修繕では工事の複雑性が増すため、業者選定がより重要になります。選定時に重視すべきポイントをご説明します。
施工実績では、類似規模・内容の工事経験を重視してください。特にエレベーター更新を含む大規模修繕の実績があるかが重要な判断材料となります。
過去5年間の施工実績リストと、可能であれば施工物件の見学も有効です。
技術力については、1級建築施工管理技士等の有資格者の配置状況、品質管理体制、安全管理体制を確認してください。
また、工事中の定期報告体制や住民対応の方針についても事前に確認することが重要です。
Q.2回目の大規模修繕で実施すべき工事の優先順位は?
A.2回目では工事項目が多岐にわたるため、適切な優先順位付けが費用管理の鍵となります。
最優先事項は安全性に関わる工事です。
構造体の損傷、防水性能の著しい低下、設備の故障リスクが高い項目は延期できません。
具体的には屋上防水の全面改修、外壁の構造的補修、法定点検で指摘された設備の更新などが該当します。
次の優先順位は建物の基本性能維持に関わる工事です。
外壁塗装、共用部分の床・壁の改修、給排水設備の部分更新などが含まれます。
これらは緊急性は低いものの、放置すると次回修繕時の費用が大幅に増加する可能性があります。
最後の検討項目が機能向上・グレードアップ工事です。
宅配ロッカー設置、LED照明化、バリアフリー対応などは、予算に余裕がある場合に実施を検討します。
ただし、これらの工事は住民満足度や資産価値に大きく影響するため、長期的な投資効果も考慮して判断することが重要です。
まとめ|2回目の大規模修繕成功への確実なステップ
マンションの1回目と2回目の大規模修繕には、実施時期、工事内容、費用面において明確で重要な違いがあることをご理解いただけたでしょうか。
- 2回目は1回目より修繕範囲が大幅に拡大し、費用も25%程度増加する
- 築25~30年の時期に実施され、設備更新が大幅に増える
- エレベーター等の高額設備工事により一時的に大きな出費が発生する
- 建物診断による適切な優先順位付けが費用抑制の重要な鍵となる
- 居住者のライフスタイル変化を反映した改修計画が満足度向上につながる
- 工事期間の長期化と複雑化により、より高度な管理能力が求められる
- 3回目修繕を見据えた長期的視点での計画策定が必要である
- 修繕積立金の不足リスクに対する早期の対策が不可欠である
2回目の大規模修繕は確かに1回目より複雑で高額になりますが、適切な準備と計画により、建物の資産価値維持と居住者の快適性向上を同時に実現できる重要な機会でもあります。
工事の成功は事前準備の質に大きく左右されるため、築20年を過ぎたら具体的な検討を開始することをお勧めします。
まずは管理組合で2回目大規模修繕について具体的な話し合いの場を設け、建物診断の実施と長期修繕計画の全面的な見直しから始めてください。
適切な準備こそが、満足度の高い大規模修繕実現への確実な道筋となるのです。








