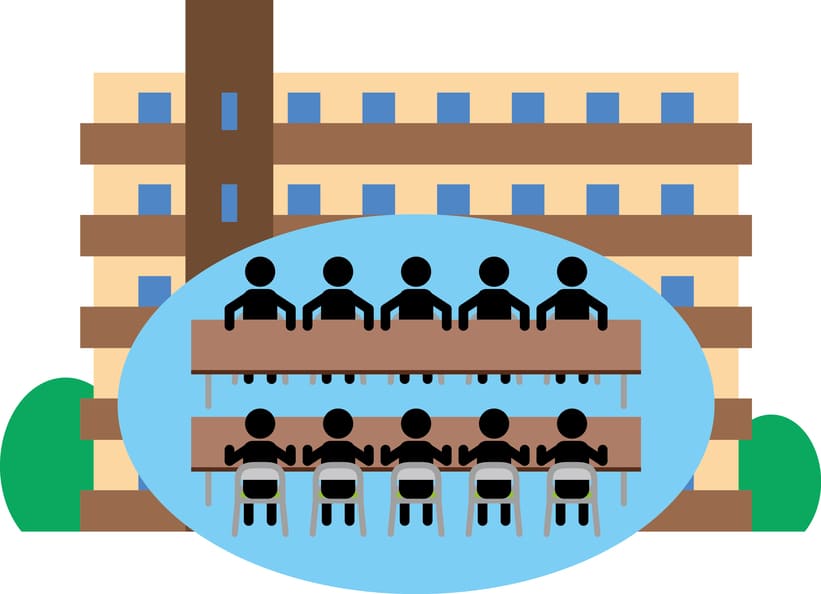
マンションの理事会は何をする?役割・仕事内容・流れを徹底解説
2025/10/29
マンションを購入すると、ある日突然「理事会の役員に選ばれました」という通知が届き、「え、理事会って何をするの?」「仕事が忙しいのに大丈夫だろうか」と不安に感じたことはありませんか。
分譲マンションでは、区分所有者全員で構成される管理組合があり、その代表者で組織されるのが理事会です。
理事会は、マンションの維持管理や住民の快適な生活を守るために重要な役割を担っていますが、初めて役員になる方にとっては「具体的に何をすればいいのか」「どのくらいの負担なのか」が見えにくく、戸惑うのも無理はありません。
この記事では、マンション管理組合と理事会の違いから、理事会の具体的な役割、役職別の仕事内容、そして役員になったときに意識すべきポイントまで、実務的な視点でわかりやすく解説します。
これから理事会役員になる方も、すでに活動中の方も、ぜひ参考にしてください。
この記事で分かること
- マンションの管理組合と理事会の違いと関係性
- 理事会が担う主な役割と具体的な仕事内容
- 理事長・副理事長・会計理事・監事など役職別の役割
- 理事会役員の選び方(輪番制・立候補制など)
- 理事会役員になったときに意識すべき重要なポイント
目次
マンションの理事会と管理組合の違いとは?
マンションの管理運営を理解するうえで、まず押さえておきたいのが「管理組合」と「理事会」の違いです。この2つは似ているようで、役割も権限も大きく異なります。
| 項目 | 管理組合 | 理事会 |
|---|---|---|
| 構成員 | 区分所有者全員 | 総会で選出された理事 |
| 役割 | 最高意思決定機関 | 執行機関(日常的な管理運営) |
| 決定できる事項 | ・規約変更 ・大規模修繕工事など | ・総会決定事項の執行 ・日常的な維持管理など |
| 活動頻度 | 年1回以上の総会 | 月1回または2か月に1回程度の定例会 |
管理組合は、分譲マンションの区分所有者全員で構成される組織です。マンションを購入した瞬間、自動的に管理組合の一員となります。
区分所有法に基づいて結成される法的な組織であり、脱退することはできません。管理組合の目的は、マンションの適正な維持管理を行い、区分所有者の共同利益を守ることにあります。
国土交通省が定める「マンション標準管理規約」によれば、以下のようなものが主な業務として挙げられています。
- 敷地や共用部分の保全・保守清掃
- 長期修繕計画の作成や変更
- 図面の保管
- 修繕履歴の管理
- 火災保険・地震保険などの契約
- 防火・防災対策など
しかし、区分所有者全員でこれらの業務を日常的に行うことは現実的ではありません。
そこで、管理組合の中から代表者を選出し、日常的な管理運営を行う執行機関として組織されるのが「理事会」です。
理事会は、管理組合の意思決定機関である「総会」で選任された理事で構成されます。会社組織に例えるなら、株主総会が管理組合総会、取締役会が理事会、社長が理事長に相当するイメージです。
理事会には独自の決定権がありますが、重要な事項(規約の変更、大規模修繕工事の実施、管理費の値上げなど)は必ず総会の承認を得なければなりません。
つまり、管理組合は区分所有者全員による意思決定機関であり、理事会はその決定事項を実行し、日常的な管理業務を遂行する執行機関という関係性にあります。
理事会は管理組合の一部であり、管理組合の代表者として活動しているのです。
この違いを理解しておくことで、理事会の役割と権限の範囲が明確になり、適切な活動ができるようになります。
マンションの理事会は何をするのか|主な役割
理事会の具体的な役割は多岐にわたりますが、大きく分けると4つの主要な業務があります。
ここでは、それぞれの業務内容について詳しく解説します。
管理組合の運営(会計・予算・議案作成)
理事会の最も基本的な役割は、管理組合の円滑な運営です。
年度ごとの収支予算案や事業計画案を作成し、総会に提出して承認を得る必要があります。
多くのマンションでは、管理会社が予算案や事業計画案の原案を作成してくれますが、理事会はそれを鵜呑みにするのではなく、内容を精査し、本当に必要な支出なのか、適正な金額なのかを検討することが重要です。
管理費や修繕積立金は区分所有者から預かっている大切な資金ですから、その使い道には責任を持たなければなりません。
また、管理費や修繕積立金の納入状況を確認し、滞納者がいる場合は督促を行うことも理事会の重要な業務です。
滞納が長期化すると、マンション全体の資金繰りに影響が出るため、早期の対応が求められます。
総会に向けての議案作成も理事会の仕事です。規約の変更や使用細則の制定・改正、大規模修繕工事の実施計画など、総会で決議すべき事項を整理し、わかりやすい議案書を作成します。
議案の内容によっては、事前に専門家の意見を聞いたり、複数の業者から見積もりを取ったりする必要もあります。
修繕積立金や修繕工事の計画・決定
マンションの資産価値を維持し、安全で快適な住環境を守るためには、計画的な修繕が不可欠です。
理事会は、長期修繕計画の見直しや修繕工事の実施について検討し、必要に応じて総会に提案します。
長期修繕計画は、一般的に25年から30年の期間を想定し、大規模修繕工事や設備の更新時期、必要な費用を見積もったものです。
建物の劣化状況や社会情勢の変化に応じて、5年程度で見直しを行うことが推奨されています。
大規模修繕工事の実施が近づくと、理事会は修繕委員会を組織したり、専門のコンサルタントを選定したりして、工事の準備を進めます。
工事業者の選定、工事内容の精査、工事期間中の住民への対応など、理事会が中心となって進める必要があります。
また、日常的な小規模修繕についても、理事会で判断することがあります。共用部分の設備が故障した場合や、安全上の問題が発生した場合など、緊急性が高いものは理事会の決議で対応します。
ただし、一定金額以上の支出については、総会の承認が必要になる場合が多いため、管理規約を確認しておくことが大切です。
管理会社・清掃業者・設備業者との契約や監督
多くのマンションでは、管理業務の大部分を管理会社に委託しています。しかし、委託しているからといって、すべてを任せきりにしてよいわけではありません。
理事会は、管理会社がきちんと業務を履行しているかを監督する責任があります。
管理会社からは、毎月または定期的に業務報告書が提出されます。
理事会では、この報告書を確認し、清掃が行き届いているか、設備点検が適切に行われているか、住民からの要望に対応できているかなどをチェックします。
もし管理会社の対応に問題がある場合は、改善を求めることも理事会の役割です。
担当者の対応が不適切であれば、管理会社の上席者に相談し、担当者の変更を要請することもできます。
ただし、過度な要求を続けると、管理会社から契約更新を断られるケースもあるため、管理会社とは適度な距離感を保ち、協力関係を築くことが長期的には重要です。
また、清掃業者や設備点検業者などの個別契約についても、理事会が内容を確認し、必要に応じて業者の見直しや契約条件の変更を検討します。
複数の業者から見積もりを取り、サービス内容と価格を比較検討することで、管理コストの適正化を図ることができます。
防災・防犯対策、住民トラブルの対応
マンション住民の安全と安心を守ることも、理事会の重要な役割です。防災対策としては、年に1回以上の防災訓練の実施、防災備蓄品の管理、防災マニュアルの作成や更新などがあります。
防災訓練は、住民同士の顔を合わせる貴重な機会であり、コミュニティ形成にも役立ちます。理事会が中心となって企画し、多くの住民に参加してもらえるよう工夫することが大切です。
防犯対策では、オートロックや防犯カメラなどの設備の点検・更新、不審者情報の共有、共用部分の照明の確認などを行います。
住民トラブルへの対応も、理事会が直面する難しい課題の一つです。
騒音問題、ペットの飼育マナー、ゴミ出しルール違反、駐車場・駐輪場の不正利用など、マンションでは様々なトラブルが発生します。
理事会は、まず事実関係を確認し、管理規約や使用細則に基づいて適切に対応する必要があります。当事者同士の話し合いで解決できる場合もあれば、理事会が間に入って調整することもあります。
悪質なケースでは、文書による注意喚起や、場合によっては法的措置も検討しなければなりません。
トラブル対応では、特定の住民の肩を持つことなく、公平な立場で判断することが求められます。感情的にならず、規約に基づいた冷静な対応を心がけましょう。
マンション理事会の仕事内容|役職別
理事会には、理事長、副理事長、会計理事、監事など、いくつかの役職があります。
それぞれの役職には明確な役割があり、協力しながら管理組合の運営を進めていきます。
ここでは、各役職の具体的な仕事内容を解説します。
理事長の役割(総括・代表権)
理事長は、管理組合を代表し、理事会の業務全体を統括する最も重要な役職です。区分所有法上の「管理者」にあたり、法的にも管理組合を代表する権限を持っています。
年に1回以上開催される通常総会では、理事長が議事を進行し、議案について区分所有者の意見をまとめます。理事会についても、定期的に開催日を設定し、議題を整理して会議を運営します。
次に、管理会社や各種業者との契約締結があります。管理委託契約の更新や、修繕工事の請負契約など、金額の大きな契約書には理事長の署名・押印が必要です。
契約内容を十分に理解し、管理組合に不利な条件がないかを確認する責任があります。
また、理事長は管理組合の対外的な窓口として、行政機関や近隣マンションとのやり取りも行います。
管理費の滞納者への督促や、ルール違反者への注意喚起など、住民に対して厳しい対応が必要な場面も、理事長が中心となって進めます。
理事長は責任が重い役職ですが、それだけにやりがいもあります。マンション全体のことを考え、住民の快適な生活を守るという重要な使命を担っています。
副理事長の役割(理事長補佐)
マンション標準管理規約第39条には、「副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う」と定められています。
日常的には、理事長の相談相手として、管理組合の運営に関する様々な事項について意見交換を行います。
理事長が仕事の都合や健康上の理由で総会や理事会に出席できない場合は、副理事長が代理として議長を務めます。
急な欠席にも対応できるよう、副理事長は日頃から管理組合の状況を把握しておく必要があります。
また、理事長が任期途中で辞任したり、転居したりした場合は、副理事長がその職務を引き継ぎます。次の理事長が選出されるまでの間、副理事長が理事長の役割を果たすことになるため、責任ある役職といえます。
副理事長の具体的な業務は、マンションによって異なります。
理事長と役割分担を明確にし、特定の業務(例えば、管理会社との日常的な連絡調整や、住民からの問い合わせ対応など)を担当することもあります。
会計理事・監事の役割(財務チェック・不正防止)
会計理事は、管理組合の会計業務を担当する役職です。収支予算案の作成、収支報告書の作成、管理費・修繕積立金の収支状況の確認などが主な業務です。
実際の会計処理は管理会社が行うことが多いため、会計理事の役割は、管理会社が作成した会計書類の内容を確認し、承認することが中心になります。
理事会に出席し、会計報告を行うことも会計理事の重要な仕事です。他の理事や監事が会計状況を理解できるよう、わかりやすく説明する必要があります。
一方、監事は、理事会の業務執行や会計処理が適正に行われているかを監査する独立した役職です。理事とは異なり、理事会の構成員ではありますが、業務執行には関与せず、監査に専念します。
監事の主な職務は以下の通りです。まず、会計帳簿や領収書などの関係書類を確認し、収支が適正に処理されているかを監査します。
また、理事会の議事録を確認し、決議事項が管理規約に違反していないか、適切な手続きで決定されているかをチェックします。
監事は、理事の業務執行に不正や規約違反がないかを監視する役割も担っています。もし問題を発見した場合は、理事会や総会に報告し、是正を求めることができます。
監事は、管理組合の財産を守り、不正を防止するための重要な役職です。
年に1回の通常総会では、監事が監査報告を行います。前年度の会計処理と理事会の業務執行について、問題がなかったことを報告し、総会での承認を得ることになります。
その他役職(広報・防災担当など)
マンションの規模や管理組合の方針によっては、理事長、副理事長、会計理事、監事以外にも、特定の業務を担当する役職が設けられることがあります。
広報担当理事は、管理組合の活動を住民に周知するための広報誌やお知らせを作成します。
理事会の議事録のダイジェスト版や、イベントの案内、マンション内のルールの再確認など、定期的に情報発信を行うことで、住民の管理組合への関心を高めることができます。
防災担当理事は、防災訓練の企画・実施、防災備蓄品の管理、防災マニュアルの更新などを担当します。
修繕担当理事は、大規模修繕工事の準備や、日常的な小規模修繕の対応を担当します。修繕委員会を組織する場合は、その委員長を務めることもあります。
すべてのマンションで必要というわけではありませんが、規模が大きいマンションや、特定の課題を抱えているマンションでは、専任の担当者を置くことで、より細やかな対応が可能になります。
マンション理事会役員の選び方
選出方法はマンションによって異なりますが、一般的には「輪番制」「立候補制」「推薦制」の3つの方法があります。
それぞれのメリット・デメリットを理解しておくことで、自分のマンションに適した選出方法を考えることができます。
- 輪番制 ▶ 各住戸・各号室が順番に役員を務める方式
- 立候補制 ▶ 役員候補者を募集し、立候補者から選出
- 推薦制 ▶ 理事会や有志が適任者を推薦し、承認を得る
| 方式 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 輪番制 | ・公平性が高い ・人選で揉めにくい ・役割が平等に分担される | ・意欲や適性のない人も就任 ・繁忙期と重なる住戸の負担感 |
| 立候補制 | ・モチベーションが高い人材が集まる ・専門性を活かしやすい | ・恒常的に応募が集まらない ・特定層に偏るリスク |
| 推薦制 | ・適性を見て配置しやすい ・急場の人選に強い | ・不透明 ・辞退が増えやすい |
最も一般的なのは輪番制で、住戸ごとに順番を決めて理事を務めるため公平性が高く、誰にでも経験の機会があるのが特徴です。
ただし意欲や適性に関係なく選ばれるため、引き継ぎ不足や活動の質にばらつきが出やすい点が課題です。
一方、立候補制は希望者が役員になる仕組みで、モチベーションが高い人材が集まりやすく、運営の質を高められる利点がありますが、応募が集まらないと役員が不足する恐れがあります。
推薦制は理事会や選考委員が適任者を選ぶ方法で、専門性のある人材を登用しやすい反面、不透明さや辞退のリスクがあります。
実務では輪番制を基本に、特定の役職を立候補や推薦で補うなど、複数の方式を組み合わせて運用するケースも多く見られます。
重要なのは、自分のマンションの状況に合った選出方法を採用し、できるだけ多くの区分所有者が管理組合の運営に関わる仕組みを作ることです。
どの方法にもメリット・デメリットがあるため、定期的に見直しを行い、より良い方法を模索していくことが大切です。
マンションの理事会役員になったら意識するべきポイント
理事会役員に選ばれた場合、何を意識して活動すればよいのでしょうか。初めて理事になる方にとっては、不安も大きいかもしれません。
ここでは、理事会役員として活動するうえで特に重要な3つのポイントを解説します。
自分のマンションをよく知ろう
多くの方は、自分の専有部分のことはよく知っていても、共用部分や管理組合の運営状況については詳しくないのではないでしょうか。
最も基本的な資料は「管理規約」と「使用細則」です。管理規約には、管理組合の目的、理事会の権限、総会の決議事項、管理費・修繕積立金の額、専有部分と共用部分の範囲など、マンション管理の基本ルールが定められています。
理事会で議論する際には、常に管理規約に基づいて判断する必要があるため、一度しっかりと読んでおくことが大切です。
使用細則には、ペットの飼育ルール、バルコニーの使用方法、駐車場・駐輪場の利用規定など、日常生活に関わる細かいルールが定められています。
住民トラブルが発生したときには、使用細則に基づいて対応することになるため、こちらも把握しておきましょう。
また、可能であれば、安全な範囲で共用部分を実際に見て回ることをおすすめします。実際に現場を見ることで、管理会社の点検報告書の内容がより理解しやすくなります。
共用部分を見て回る際には、危険な場所がないか、清掃が行き届いているか、設備の劣化が進んでいないかなど、改善すべき点がないかをチェックする視点も大切です。
管理会社と上手に付き合おう
管理会社は、マンション管理のプロフェッショナルとして、理事会の業務をサポートしてくれる存在です。上手に付き合うことで、管理組合の運営がスムーズに進みます。
まず理解しておきたいのは、管理会社は業務を委託されている外部の組織であり、最終的な決定権は管理組合(理事会)にあるということです。
管理会社の提案を鵜呑みにするのではなく、本当に必要な工事なのか、適正な価格なのかを理事会で十分に検討する必要があります。
一方で、管理会社に過度な要求をしたり、敵対的な態度を取ったりすることは避けるべきです。管理会社の担当者も人間ですから、理事会が協力的であれば、それに応えようと努力してくれます。
逆に、過度な要求を続けた結果、管理会社から契約更新を断られるケースも実際に発生しています。
管理組合運営が上手くいっているマンションほど、管理会社との距離感をうまく保ち、協力関係を築いています。
理事会の活動をみんなに知ってもらう
年に1回の総会だけでは、理事会の日常的な活動内容は伝わりにくいものです。そこで、定期的に理事会の活動報告を行うことをおすすめします。
方法としては、理事会議事録のダイジェスト版を作成して各戸に配布する、掲示板に掲示する、マンションの専用ホームページに掲載するなどがあります。
ただし、議事録には滞納者の個人名や、プライバシーに関わる情報が含まれることもあるため、そのまま公開するのは適切ではありません。
公開用のダイジェスト版を作成する際には、個人情報に配慮しながら、重要な決定事項や検討中の課題を共有するようにしましょう。
また、理事会だより(広報誌)のような形で、マンションの出来事やお知らせ、ルールの再確認などを定期的に発信することも効果的です。
さらに、総会以外にも、季節のイベント(お花見、夏祭り、クリスマス会など)や防災訓練を開催し、住民が気軽に参加できる機会を作ることも有効です。
多くの住民がマンション管理に関心を持てば、理事が交代しても組合の活動がスムーズに引き継がれていきます。良好なマンション管理には、理事会の活発な活動だけでなく、その継続性も重要です。
マンションの理事会・管理組合に関するよくある質問【FAQ】
マンションの理事会や管理組合について、多くの方が疑問に思うポイントをQ&A形式でまとめました。
理事会役員になる前に知っておきたい情報や、活動中の疑問解決にお役立てください。
Q. 理事会役員を断ることはできますか?
法律上、理事会役員の就任を強制する規定はないため、断ることは可能です。
しかし、輪番制で選出された場合は、管理組合全員で理事会役員を担当する仕組みとなっているため、正当な理由なく断ると他の住民とのトラブルに発展する可能性があります。
正当な理由としては、長期の海外出張や単身赴任、重い病気や介護などが挙げられます。こうした事情がある場合は、理事会や総会で説明し、理解を得ることが大切です。
ただし、単に「忙しい」「やりたくない」という理由だけでは、他の住民の理解を得にくいでしょう。
どうしても理事会役員を務めることが難しい場合は、代理人を立てる、一部の業務だけを担当する、役員報酬を辞退する代わりに別の協力をするなど、マンションごとに柔軟な対応を検討することも一つの方法です。
Q. 理事会は月にどのくらいの頻度で開催されますか?
理事会の開催頻度は、マンションの規模や管理組合の運営方針によって異なりますが、一般的には月に1回、または2か月に1回程度の定例会が開催されます。1回の理事会は、1時間から2時間程度です。
定例会以外にも、緊急の案件が発生した場合(例えば、共用部分の設備故障、住民トラブルの深刻化など)は、臨時の理事会が開催されることもあります。
また、大規模修繕工事の準備期間中などは、通常よりも頻繁に理事会を開く必要が生じることもあります。
最近では、オンライン会議システムを利用して理事会を開催するマンションも増えています。物理的に集まる負担が減り、参加しやすくなるというメリットがあります。
Q. 理事会役員に報酬はありますか?
国土交通省の調査によると、役員報酬を支給しているマンションの割合は約3割程度で、報酬を支給している場合の平均額は年額で約12,000円程度とされています。
理事長、副理事長、会計理事など役職によって報酬額を変えているマンションもあれば、役員全員一律の報酬を支給しているマンションもあります。
また、報酬を支給せず、理事会への出席ごとに数千円の出席手当を支払う形式のマンションもあります。
報酬の有無や金額は、管理規約で定められています。報酬を新設したり金額を変更したりする場合は、総会での決議が必要です。
Q. 賃貸に出している部屋の所有者も理事会役員になりますか?
管理組合の構成員は「区分所有者」であり、実際にその部屋に住んでいるかどうかは関係ありません。したがって、賃貸に出している部屋の所有者も、理事会役員の対象になります。
ただし、実際には遠方に住んでいたり、マンションの状況を把握しにくかったりするため、賃貸に出している区分所有者に対しては、理事会役員を免除したり、代わりに一定の金銭的負担を求めたりするなどの配慮をしているマンションもあります。
このような特例を設ける場合は、管理規約に明記し、総会で承認を得ておく必要があります。公平性を保ちながら、実情に合った運用を工夫することが大切です。
Q. 理事会の議事録は公開されますか?
理事会の議事録は、原則として管理組合員(区分所有者)であれば閲覧することができます。
マンション標準管理規約では、区分所有者は管理組合の会計帳簿や議事録などの書類を閲覧できると定められています。
ただし、議事録には個人情報や機密性の高い情報が含まれることもあるため、そのままの形で各戸に配布したり、掲示板に掲示したりすることは適切ではありません。
閲覧を希望する区分所有者に対しては、管理会社の事務所や管理人室などで閲覧できるようにするのが一般的です。
一方で、理事会の活動を広く知ってもらうために、個人情報を除いた議事録のダイジェスト版を作成し、広報誌として配布することは推奨されます。
透明性を保ちつつ、プライバシーにも配慮したバランスの取れた情報公開が求められます。
まとめ|理事会は住みやすいマンションづくりの要
マンションの理事会について、役割や仕事内容、役員になったときのポイントまで詳しく解説してきました。
最後に、この記事の重要なポイントを振り返りましょう。
- 管理組合は区分所有者全員による最高意思決定機関で、理事会はその執行機関
- 理事会は運営や修繕計画、管理会社の監督、防災・防犯、トラブル対応を担う
- 理事長は代表、副理事長は補佐、会計理事や監事は財務チェックを行う
- 役員の選び方には輪番制・立候補制・推薦制がある
- 理事会役員になったら、管理会社と協力し、活動を住民に周知することが大切
理事会役員は、確かに時間や労力を必要とする役割です。
しかし、自分が住むマンションの管理運営に携わることで、マンションへの理解が深まり、住環境の改善に直接貢献できるやりがいのある活動でもあります。
もし理事会役員に選ばれたら、前向きに取り組んでみてはいかがでしょうか。
また、役員でない方も、理事会の活動に関心を持ち、総会に出席したり意見を伝えたりすることで、マンション全体のコミュニティ形成に貢献できます。
住民一人ひとりの意識が、快適で資産価値の高いマンションを作っていくのです。








