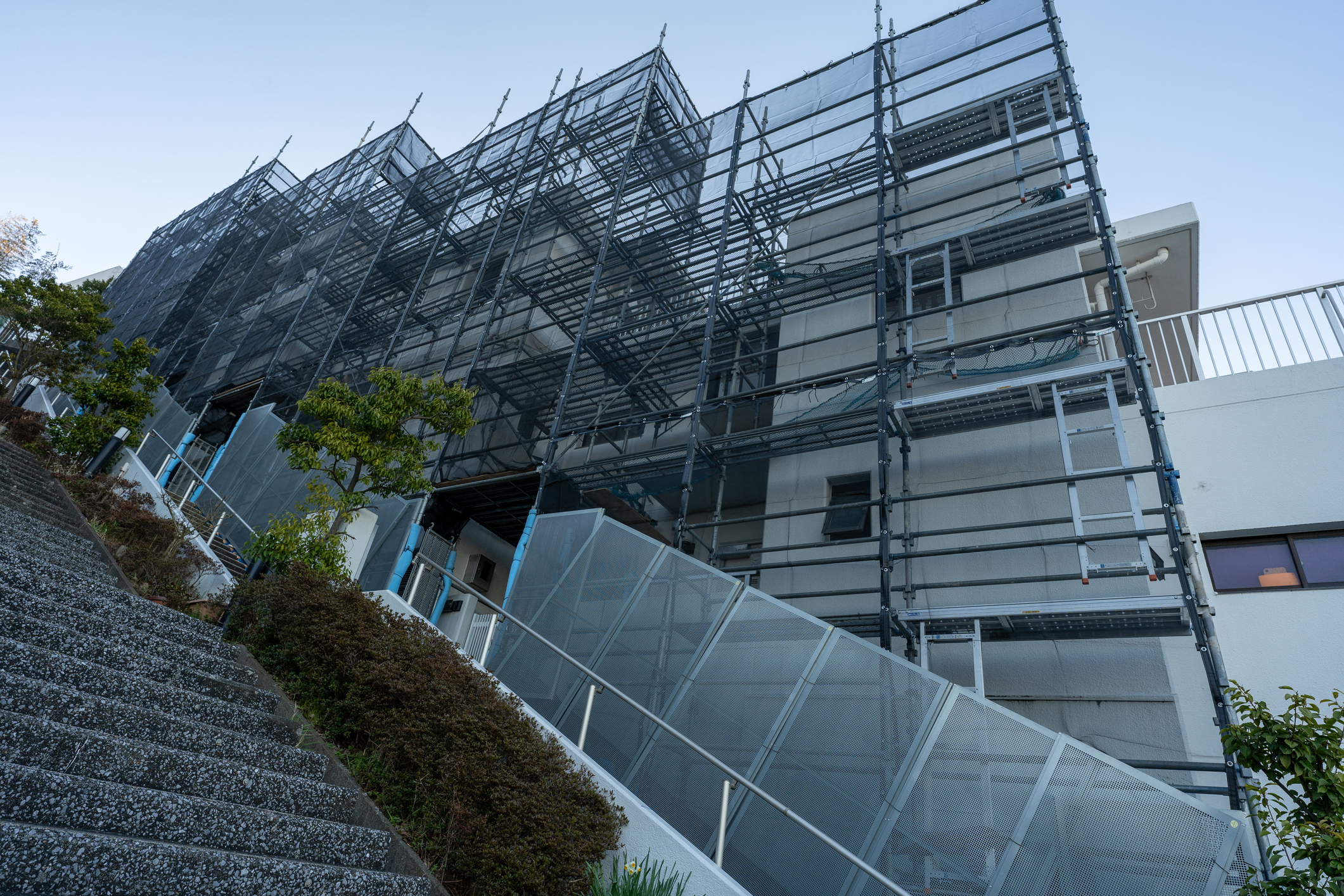
中古マンションの雨漏り工事はどうする?原因や注意点をわかりやすく解説
2025/07/24
中古マンションでは築年数の経過とともに、雨漏りが発生するリスクが高まります。放置するとカビや木部の腐食、構造躯体の劣化など、重大な問題に発展する恐れもあります。この記事では、中古マンションの雨漏りについて、原因や初期対応・工事の種類・注意すべきポイントなどをわかりやすく解説します。
目次
中古マンションで雨漏りが起こる主な原因とは?
中古マンションの雨漏りは、建物の経年劣化や施工不良、自然災害の影響など、さまざまな要因で発生します。以下では、代表的な原因を詳しく解説します。
屋上の防水層の劣化
屋上は日差しや風雨に常にさらされているため、防水層が劣化しやすい箇所です。とくに築15年〜20年を超えるマンションでは、ウレタン防水・塩ビシート防水などの劣化により、ひび割れ・膨れ・剥がれ・ドレン(排水口)の詰まりなどが生じやすくなります。
これらの異常を放置すると、防水層の下にあるコンクリートまで水が浸透し、鉄筋のサビや下階への雨漏り被害へとつながります。また、屋上の水たまりや、表面の細かいクラックも、劣化のサインとして見逃さないようにしましょう。
外壁やコーキングのひび割れ
外壁のクラックや、外壁パネル・タイルの目地に使われるコーキング材の劣化も雨漏りの原因になります。クラックには、構造に影響しない「ヘアークラック」と呼ばれる細いものもありますが、放置すると水が徐々に浸入し、内部の腐食や断熱材のカビを引き起こします。
また、コーキング材は紫外線や雨風で劣化しやすく、5~10年を目安に硬化・亀裂・剥離が生じます。とくに、サッシ周辺やALCパネル(軽量気泡コンクリート)の目地など、コーキングに依存する部分が多い建物は、定期的な打ち替えが不可欠です。
サッシまわりの隙間
サッシや窓枠は、建物の中でもとくに雨水が浸入しやすい場所です。施工時の取り付け精度の甘さや経年劣化による枠の変形・コーキング材の収縮や剥がれによって、外壁との間にわずかな隙間が生まれ、そこから雨水が染み込むことがあります。
さらに、強風を伴う豪雨や台風時などは、通常の水密性能では防ぎきれず、室内側の壁紙の浮き・窓枠からのポタポタ音・レール部分の腐食などが現れます。見逃されやすい部分だからこそ、違和感を感じたらすぐに確認しましょう。
給排水管の漏水との混同
雨漏りだと思っていたら、実は上階の給湯器や配管からの漏水だったというケースも多く見られます。とくに、浴室・キッチン・洗面所などの水まわりの下部に水が漏れていた場合は、雨漏りではなく給排水トラブルの可能性も少なくありません。
配管は壁や天井内に埋め込まれているため、発見が遅れると被害が拡大します。雨の日以外でも水が漏れる・シミが広がる・ニオイが気になる場合は、給排水トラブルを疑いましょう。専門業者に調査を依頼し、雨水と生活水の経路を見極める必要があります。
このように、雨漏りの原因は多岐にわたり、目視だけでは判断できないケースも多いため、専門業者による的確な診断と早期対策が重要です。
雨漏りを発見したときの適切な初動対応
雨漏りを発見した際には、焦らず落ち着いて次のように対応することが重要です。被害の拡大を防ぎつつ、原因の特定や修繕に向けた準備を進めましょう。
- 状況を記録する:雨漏りの発生場所や水の量・発生時間帯・天候の状況などを可能であれば撮影し、日付付きで記録を残しましょう。複数回発生している場合は、それぞれの記録を比較できるようにまとめておくと診断に役立ちます。
- 応急処置を行う:雨水の落下箇所にはバケツや洗面器を置いて受け止め、周囲の家具や床にはビニールシートやタオルを敷いて養生します。コンセントや電気機器が濡れている場合は感電の恐れがあるため、漏電ブレーカーを落とすなど安全対策を優先してください。
- 管理会社や管理組合へ連絡:マンションの場合、雨漏りの原因が共用部分(屋上・外壁など)にある場合は、管理組合の対応が必要です。修繕費用の負担区分(専有/共用)にも関わるため、早めに連絡し、状況報告と写真の提出を行いましょう。
- 専門業者に調査を依頼する:原因の特定には、雨漏り診断のプロによる現地調査が不可欠です。散水試験や赤外線カメラなどを用いて、目視ではわからない雨水の侵入経路を特定します。自分で補修を試みると、原因が分からなくなり再発リスクが高まるため、必ず専門業者に相談しましょう。
こうした初動対応を丁寧に行うことで、修繕までの流れがスムーズになり、トラブルや二次被害を防ぐことにつながります。
中古マンションにおける雨漏り工事の種類と内容
雨漏りの原因や被害の程度によって、実施される工事の内容も異なります。以下は代表的な工事の種類とその特徴です。
屋上防水工事
屋上からの雨漏りが確認された場合、防水層の再施工が行われます。主に以下の工法があります。
- ウレタン防水:液状の防水材を塗布し、継ぎ目のない防水層を形成。複雑な形状の屋上にも対応可能。
- シート防水:塩ビシートやゴムシートを貼る工法で、均一な厚みと耐候性に優れます。 いずれの工法も、下地処理や勾配調整が重要で、施工不良を避けるためには熟練の技術が求められます。
外壁補修工事
外壁に生じたクラックや、劣化したコーキングの補修を行います。
- ひび割れ補修:微細なものはシーラーや充填材で対応、大きなクラックはVカット工法やエポキシ樹脂注入で補修します。
- コーキング打ち替え:古くなったコーキング材を撤去し、新たに打ち直すことで防水性を回復。 外壁の種類によって適切な処置が異なります。
サッシまわりの補修
窓やサッシの周囲からの浸水を防ぐために、以下のような工事が行われます。
- コーキングの打ち替え:劣化した目地を新しい防水材で補修。
- 水切り金物の取り付け:雨水が壁内部に侵入しないよう、水の流れを制御する部材を設置。
- アルミ枠の調整・交換:枠の変形が激しい場合には交換も検討します。
内装復旧工事
雨漏りによって損傷した室内の仕上げ材を補修・交換する工事です。
- クロス張り替え:壁紙の浮きやシミ、カビなどのある部分を交換。
- 石膏ボード交換:天井や壁の下地が水を含んでいる場合、腐食やカビの原因となるため新しいものに交換。
- 断熱材の乾燥・交換:内部に浸水していた場合は断熱性能が損なわれるため、状態に応じて対応します。
雨漏り工事にかかる費用の目安
以下は主な工事項目ごとの費用相場です。被害の規模や建物の構造・使用する材料などによって価格は変動します。
| 工事項目 | 費用相場 |
| 屋上防水工事 | 約20〜200万円 |
| 外壁のひび割れ修理 | 約5〜10万円 |
| 窓のサッシまわり補修 | 約3〜10万円 |
| コーキングの補修 | 約2〜20万円 |
※現地調査費用として、別途費用がかかることがあります。
目安として把握しつつも、正確な費用は専門業者の見積もりを取得して比較検討することが大切です。
工事費用は誰が負担する?専有部分と共用部分の判断基準
マンションにおける雨漏りの修繕費用は、被害の発生箇所が「専有部分」か「共用部分」かによって負担者が異なります。
- 共用部分(屋上・外壁・共用廊下・共有配管など):原則として管理組合の負担になります。建物全体に関わる構造や外装部分、配管などが該当し、マンション全体の資産維持の観点から共通費用で修繕を行うケースが多いです。
- 専有部分(居住者の部屋内の天井・床・壁の仕上げ、クロスなど):基本的に居住者個人の負担となります。例えば、天井クロスの張替えやフローリングの張替えは専有部分の工事として扱われます。
ただし、被害が専有部分に現れていても、原因が共用部分にある場合は、管理組合が補修費を負担することになります。このように、見た目の被害箇所と原因箇所が異なるケースもあるため、費用負担の判断には注意が必要です。
判断に迷う場合は以下を徹底しましょう
- 管理規約の確認:管理規約には、専有部分・共用部分の定義や、修繕費の負担区分が明記されています。特に細則や特別規定がある場合もあるため、細かく確認することが大切です。
- 専門業者による調査・報告書:原因特定には専門家による調査が不可欠です。散水調査や赤外線カメラによる診断結果を報告書として残しておくと、後の説明・交渉にも役立ちます。
- 管理会社・管理組合との書面でのやりとり:口頭でのやりとりだけではトラブルに発展することがあります。やりとりの内容は必ず書面やメールなどで記録し、証拠を残しておくことが重要です。
管理組合との連携もカギ
共用部分の補修を管理組合が行う場合でも、住戸内の内装復旧費用は自己負担となることがほとんどです。どこまでが共用工事の対象か、内装復旧費用に対して補助が出るのかなど、管理組合と丁寧に話し合いを重ねることが望まれます。
このように、修繕費用の負担区分は単純ではありません。被害発見後は早めに管理会社・専門業者に相談し、トラブルを防ぎながら円滑に対応を進めましょう。
購入前に確認したい雨漏りのチェックポイント
中古マンションを購入予定の方は、内見時や契約前に以下のポイントを丁寧に確認することで、購入後のトラブルや修繕費の負担を避けることができます。
天井や壁のシミ・変色・カビの有無
室内の天井や壁に、茶色いシミ・クロスの浮き・カビ臭があれば、過去に雨漏りや漏水があった可能性があります。特に角部屋や最上階では、屋上・外壁からの浸水リスクが高いため注意が必要です。
窓まわりやサッシのコーキング状態
サッシ周辺のコーキングがひび割れていたり、剥がれていたりする場合は、そこから水が浸入するリスクがあります。内見時には窓枠まわりを目視で確認し、可能であれば外側もチェックしましょう。
管理組合による長期修繕計画の有無
マンション全体の維持管理に関わる長期修繕計画が整っているかを確認しましょう。屋上防水や外壁改修の周期が記載されていれば、将来的な修繕時期の目安にもなります。
直近の大規模修繕・防水工事の履歴
過去にどのような修繕工事が行われてきたかは、管理会社に確認できます。直近で屋上や外壁の防水工事が実施されていれば、雨漏りのリスクは比較的低いといえます。
インスペクション(住宅診断)の活用
第三者の専門家による住宅診断サービス(インスペクション)を活用すれば、見えない箇所の劣化や構造の不具合を把握できます。雨漏りリスクや修繕必要箇所の客観的な評価が得られ、購入判断に役立ちます。
瑕疵保険・売主保証の内容確認
中古住宅には「契約不適合責任」が適用されますが、売主によって保証範囲や期間が異なります。雨漏りが保証対象に含まれるかどうか、契約前に不動産会社を通じて確認しておきましょう。
このようなチェックを怠ると、購入後に多額の修繕費が発生するリスクも。特に築20年以上の物件では、雨漏りリスクを見逃さない慎重な確認が不可欠です。
信頼できる業者選びが重要な理由とチェックポイント
雨漏りはその発生原因が複雑で、外からは見えない部分で進行していることも多くあります。原因を正しく特定し、適切な工法で修繕しなければ、再発のリスクが非常に高くなります。だからこそ、信頼できる専門業者に依頼することが不可欠です。
適切な業者選びのポイントは以下の通りです。
専門的な資格や経験があるか
「雨漏り診断士」「防水施工技能士」など、専門性の高い資格を持った技術者が在籍しているかを確認しましょう。経験豊富な業者であれば、原因の特定や最適な補修方法の提案が的確です。
詳細な調査と根拠のある見積もりを提示できるか
現地調査を丁寧に行い、調査結果に基づいて具体的な見積書を提示してくれる業者は信頼できます。調査方法や施工手順も明確に説明してくれるか確認しましょう。
アフターフォローや保証体制が整っているか
工事後に雨漏りが再発した場合の対応について、保証内容を明確にしている業者を選びましょう。保証期間や範囲について事前に契約書に記載されているか確認することも重要です。
極端に安い見積もりや即決を迫る業者には注意
「今だけ」「すぐに契約すれば安くなる」といった営業手法で契約を迫る業者は避けましょう。極端に安価な見積もりは、手抜き工事や必要な工程を省略されるリスクがあります。
雨漏り工事は一度きりで終わるものではなく、長期的な建物の健康を守るための大切なメンテナンスです。信頼できるパートナーを選ぶことが、将来の安心にもつながります。
よくある質問(FAQ)
中古マンションの雨漏りに関して、よく寄せられる疑問や不安をまとめました。工事の内容や費用、原因の特定方法から業者選びまで、知っておきたいポイントをわかりやすく解説しています。ぜひ参考にして、雨漏り対策にお役立てください。
Q1. 雨漏りの原因はどうやって特定するの?
→ 散水調査・赤外線カメラ・目視調査などを組み合わせて判断します。
Q2. 雨漏りの修理費用は火災保険で補償される?
→ 経年劣化以外の自然災害が原因なら、補償対象となるケースがあります。契約内容を確認しましょう。
Q3. 雨漏りは放置しても問題ない?
→ 放置するとカビ・木部の腐食・電気設備のショートなど深刻な被害に発展します。
Q4. 自分で修理するのは危険?
→ 一時的に水が止まっても、根本的な解決にはならず再発の恐れが高いため、専門業者に依頼すべきです。
Q5. 中古マンション購入後すぐに雨漏りが見つかったら?
→ 契約内容次第では、売主に「契約不適合責任」が問える場合があります。すぐに不動産会社に相談しましょう。
まとめ
中古マンションの雨漏りは、放置すると建物の劣化を進行させ、カビや腐食を引き起こすだけでなく、住環境の悪化や資産価値の低下にもつながります。雨漏りを発見したら、まずは早期に正確な原因を特定することが重要です。そのうえで、状況に応じた適切な修繕工事を選び、費用負担の所在を明確にするために管理規約や専門業者の調査報告書を活用しましょう。
また、信頼できる業者を選ぶことも再発防止や安心した暮らしのために欠かせません。これらを徹底することで、長く安全で快適な住まいを維持できます。中古マンションの雨漏り対策は。早めの対応と適切な工事、そして信頼できるパートナー選びが成功のポイントです。








