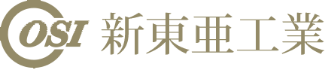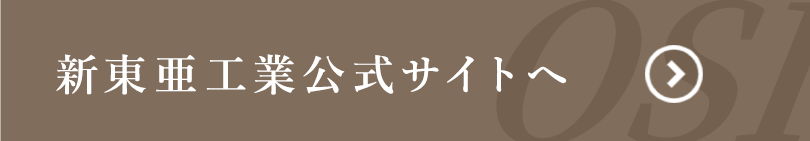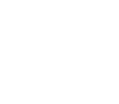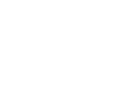マンションの防水工事は、建物の寿命や快適な居住環境、さらには資産価値にも大きな影響を与える非常に重要なメンテナンス作業です。
屋上やバルコニーなどの防水性能が低下すると、雨漏りや構造内部の腐食・カビの発生など、深刻なトラブルにつながりかねません。
そのため、定期的な点検と、劣化状況に応じた適切なタイミングでの防水工事が求められます。
また、施工にはさまざまな工法があり、建物の構造や劣化状態・立地条件などによって最適な方法を選定する必要があります。
防水材や施工方法の選び方によって、耐久年数やメンテナンスコストにも違いが出てくるため、専門的な知識が不可欠です。
本記事では、防水工事の基礎知識をはじめ、主な防水工法の種類やそれぞれの特徴、費用の目安、そして信頼できる業者を選ぶためのチェックポイントまでを丁寧に解説していきます。
マンション管理組合の方や、住民代表として防水工事を検討されている方は、ぜひ最後までご覧ください。
目次
防水工事とは?その目的と重要性
防水工事は、建物内部への水の浸入を防ぐための施工です。
特にマンションでは、屋上やバルコニーなどの防水層が劣化すると、雨漏りや構造体の腐食、カビの発生などの問題が生じます。
これらは居住者の快適性を損なうだけでなく、修繕費用の増加や資産価値の低下にもつながります。
防水工事の主な目的
雨水の侵入防止
防水工事の最も基本的な目的は、建物内部への雨水の浸入を防ぐことです。
屋上やバルコニー・外壁などは常に風雨や紫外線にさらされており、年月とともに防水性能は徐々に低下していきます。
そのまま放置し続けると、雨水がひび割れや隙間から浸入し、壁や天井にシミやカビを発生させるだけでなく、居住者の生活環境を悪化させる恐れもあります。
さらに水分が構造体にまで及ぶと、建物の根幹である鉄筋やコンクリートの劣化が進み、補修に多大な費用がかかることも考えられます。
こうしたリスクを未然に防ぐために、防水工事は定期的かつ適切なタイミングで実施することが重要です。
建物の耐久性向上
防水工事は、建物の耐久性を維持・向上させるうえでも極めて重要な役割を果たします。
特に鉄筋コンクリート造のマンションでは、コンクリートの中にある鉄筋が腐食すると、膨張して周囲のコンクリートを押し割り、ひび割れや剥離の原因になります。
このような現象は「中性化」と呼ばれ、雨水や湿気が浸入することで加速されます。
防水層がしっかりと機能していれば、外部からの水分の浸入を遮断し、建物内部の劣化を最小限に抑えることができます。
結果として、建物そのものの寿命を延ばし、大規模な修繕工事の頻度や費用を抑えることにもつながるのです。
資産価値の維持
マンションは居住空間であると同時に、大きな資産でもあります。
その資産価値を維持するためには、定期的なメンテナンスが欠かせません。
なかでも防水工事は、美観や機能性の維持に直結するため、重要な位置づけにあります。
たとえば、屋上や外壁に汚れやひび割れが見られたり、水漏れによる内装の損傷があったりすると、購入希望者や査定担当者にマイナスの印象を与え、評価額の低下を招く可能性があります。
逆に、しっかりと防水メンテナンスが行われている建物は、管理状態が良好である証としてプラス評価を受けやすくなります。
定期的な防水工事は、マンションの資産価値を守るための有効な投資といえるでしょう。
防水工事の種類と特徴
マンションの防水工事には、主に以下の4種類があります。
それぞれの工法には特徴があり、建物の構造や使用目的に応じて選択されます。
ウレタン防水
ウレタン樹脂を塗布して防水層を形成する工法です。
複雑な形状の部位にも対応でき、比較的安価で施工が可能です。
耐用年数は10〜15年程度です。
メリット
- 継ぎ目のないシームレスな仕上がり
- 複雑な形状にも対応可能
- 比較的安価で施工が可能
デメリット
- 耐候性が低く、定期的なトップコートの塗り替えが必要
シート防水
ゴムや塩ビ製のシートを貼り付けて防水層を形成する工法です。
工期が短く、広い面積にも対応できます。
耐用年数は10〜20年程度です。
メリット
- 耐久性が高い
- 軽量で建物への負担が少ない
- 工期が短い
デメリット
- 継ぎ目ができるため、施工技術によって防水性能が左右される
FRP防水
ガラス繊維と樹脂を組み合わせて防水層を形成する工法です。
耐久性・耐水性が高く、デザイン性にも優れています。
耐用年数は12〜20年程度です。
メリット
- 耐久性・耐水性が高い
- デザイン性が高く、さまざまな色や模様を選べる
デメリット
- 衝撃に弱く、ひび割れしやすい
- 紫外線による劣化が起こりやすい
アスファルト防水
アスファルトと合成繊維で作られたシートを貼り重ね、防水層を形成する工法です。
耐久性・耐火性・耐候性が高く、マンションの広い面積を持つ部分に適しています。
耐用年数は15〜25年程度です。
メリット
- 耐久性・耐火性・耐候性が高い
- 比較的安価
デメリット
- 重量があるため、建物への負担が大きい
- 工期が長い
防水工事の施工時期とメンテナンス
防水工事は、一度行えば永久に効果が持続するわけではありません。
防水層は、紫外線や雨風・温度変化などの影響で徐々に劣化していくため、定期的なメンテナンスが必要です。
新築時
新築時に適切な防水工事を行うことで、建物の初期性能を最大限に引き出し、将来的なメンテナンス費用を抑えることができます。
築10年を目安とした定期的な点検・補修
築10年が経過すると、防水層の劣化が目立ち始める時期です。
目に見える劣化がなくても、防水層の内部では劣化が進んでいる可能性があります。
定期的な点検では、専門業者に依頼し、防水層の亀裂や破損・浮きや膨れ・シーリング材の劣化・雨漏りの兆候などを確認してもらいましょう。
大規模修繕時
マンションなどの集合住宅では、12年に一度、大規模修繕を行うことが一般的です。
大規模修繕は、足場を組んで外壁の補修や塗装を行うため、防水工事を行う最適なタイミングと言えます。
防水工事の費用相場
防水工事の費用は、工法や施工面積・建物の状態によって異なります。
以下は一般的な費用相場です。
| 工法 | 費用相場(㎡あたり) | 耐用年数 |
| ウレタン防水 | 4,000~7,000円 | 10~15年 |
| シート防水 | 5,000~8,000円 | 10~20年 |
| FRP防水 | 6,000~9,000円 | 12~20年 |
| アスファルト防水 | 5,000~10,000円 | 15~25年 |
防水工事を行うタイミングの目安
防水層の寿命は10年から20年程度とされていますが、実際の劣化スピードは環境条件や使用状況によって異なります。
以下のような症状が見られたら、防水工事の検討時期です。
劣化のサイン
- 雨漏りが発生している
- 防水層のひび割れや膨れ、剥がれがある
- 屋上やバルコニーに水たまりができやすい
- コンクリートの表面に白華現象(白い粉)が見られる
- シーリング材(コーキング)が割れている・縮んでいる
こうした劣化の兆候を放置しておくと、最終的には構造体の腐食や内部のカビ発生につながり、修繕費用が大幅に膨らむ可能性があります。
防水工事の施工手順
防水工事は専門的な作業のため、経験豊富な業者に依頼することが基本です。
ここでは、一般的なウレタン防水工事の流れを紹介します。
- STEP
現地調査と診断
防水工事を成功させるためには、まず現地調査と診断が欠かせません。
専門の技術者が屋上やバルコニーなどの施工箇所に赴き、ひび割れ・膨れ・漏水跡といった劣化の状態を詳細に確認します。
また、建物の構造や素材・勾配・水はけの状況などもチェックし、それに応じた最適な防水工法や使用する材料を選定します。
この工程を正確に行うことで、無駄のない施工計画が立てられ、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。 - STEP
高圧洗浄
防水施工前には、施工面の高圧洗浄を徹底的に行います。
これは、防水材がしっかり密着するよう、屋上や床面に付着した泥・カビ・苔・ホコリ・油分などの汚れを除去する作業です。
高圧洗浄機を使って水の圧力で汚れを吹き飛ばすことで、下地がクリーンな状態になります。
洗浄が不十分だと防水層の剥がれや密着不良の原因になるため、この工程は非常に重要です。
適切な洗浄によって、防水性能の持続性も高まります。 - STEP
下地処理
洗浄後の下地には、ひび割れや欠け・段差といった劣化箇所が存在する場合が多く、そのままでは防水材がしっかりと密着しません。
下地処理では、これらの劣化部分を丁寧に補修・補強し、防水層が安定して施工できる状態に整えます。
たとえば、クラック(ひび割れ)にはシーリング材を充填し、欠損部には樹脂モルタルを使って平滑に仕上げます。
丁寧な下地処理は、防水層の耐久性と仕上がりの美しさに直結する重要な工程です。 - STEP
プライマー塗布
下地処理が完了したら、次にプライマーを塗布します。
プライマーは下地と防水材をしっかり密着させるための接着剤のような役割を果たすもので、これを省略すると防水層が剥がれやすくなります。
施工面全体に均一に塗布し、乾燥時間をしっかり確保することが重要です。
使用する防水材に応じた専用のプライマーを選ぶことで、密着性や耐久性が大きく向上し、防水効果を長期的に維持できる下地を整えることができます。 - STEP
防水層の施工
防水工事の中心となる工程が、防水層の施工です。
調査結果や建物の条件に応じて、ウレタン塗膜防水やシート防水・FRP防水など最適な工法が選ばれます。
たとえば、ウレタン塗膜防水は液状のウレタンを複数回塗り重ねて防水層を形成する工法で、複雑な形状にも対応できるのが特徴です。
防水層は厚みや均一性が重要で、施工技術の高さが耐久性に直結します。
丁寧に施工された防水層が、雨水の浸入をしっかりと防いでくれます。 - STEP
トップコート塗布
防水層の上からトップコートを塗布することで、防水材を紫外線や風雨・摩耗などの外的ダメージから保護します。
ウレタン防水の場合、このトップコートは防水材自体の劣化を遅らせる役割があり、長期的な防水性能の維持には欠かせません。
トップコートには防滑性や遮熱性を付加した製品もあり、用途や環境に応じて選択されます。
施工は均一にムラなく塗る必要があり、見た目の仕上がりにも大きく影響する重要な工程です。 - STEP
最終検査・引き渡し
すべての施工工程が終了した後、施工業者と管理組合または施主が立ち会い、最終検査を行います。
施工箇所の仕上がりや不具合の有無を丁寧に確認し、必要であれば是正工事を行います。
問題がなければ、工事完了報告書や写真付きの記録資料・保証書などを受け取り、正式に引き渡しとなります。
これにより、防水工事の内容がしっかり記録として残り、将来的なメンテナンスやトラブル時の対応にも活用できます。
マンションの防水工事で失敗しないための業者選びのポイント
防水工事は専門性が高く、業者の技術力や信頼性によって仕上がりが大きく左右されます。
業者選びの際には、以下のポイントを押さえておきましょう。
実績が豊富かどうか
マンションや大規模物件での防水工事は、戸建て住宅に比べて規模も複雑さも格段に高くなります。
そのため、過去に同様の物件での施工実績がある業者を選ぶことが非常に重要です。
実績が豊富な業者は、現場ごとの課題やトラブルに柔軟に対応するノウハウを持っており、工期や品質面でも安心して任せられます。
業者選定の際は、ホームページやパンフレットに掲載されている施工事例を確認し、自分たちのマンションと似た条件での実績があるかどうかをチェックしましょう。
また実績件数だけでなく、施工後の評判や口コミも確認すると、業者選びの精度が高まります。
見積もりが明確で詳細
防水工事の見積もりは、工事内容の透明性と信頼性を確認するための重要な資料です。
見積書に「一式」とだけ記載されているような曖昧な表現が多い場合、実際の作業内容が不明瞭で、後から追加費用を請求されるリスクがあります。
信頼できる業者は、材料費・人件費・足場代・高圧洗浄費・下地処理費・廃材処分費などを項目ごとに細かく記載し、それぞれの単価や数量も明示してくれます。
見積もりの段階でしっかりと説明を受け、わからない点はその場で質問しましょう。
複数社から見積もりを取り、比較検討することも、納得のいく工事を実現するために欠かせないプロセスです。
アフターフォローの有無
防水工事は施工完了後の状態がすぐに目に見えにくく、数年後に不具合が発覚するケースもあります。
そのため、施工後のアフターフォローがあるかどうかは非常に重要です。
定期点検の実施や、保証期間内の無償修理対応など、長期的な安心を支える体制が整っている業者を選ぶべきです。
保証内容や期間について、契約書に明記されているか必ず確認し、不明点があれば事前に質問しておきましょう。
信頼できる業者は、アフターフォローの説明も丁寧で、実際のトラブル発生時にも迅速に対応してくれるため、施工後の安心感が違います。
工事品質だけでなく、その後のサポート体制にも注目することが、賢い業者選びのポイントです。
4. 自社施工か下請けか
防水工事業者の中には、営業活動は自社で行いながら、実際の施工はすべて外部の下請け業者に任せているケースもあります。
このような体制の場合、現場での対応力や品質管理にばらつきが出ることがあり、トラブルに発展することもあります。
一方で自社施工の業者は、最初の打ち合わせから施工・アフターケアまで一貫して責任を持って対応してくれるため、トラブルが少なく安心感があります。
契約前には、担当者に「実際の工事は誰が行うのか」「自社スタッフが現場を管理するのか」などを明確に確認しましょう。
信頼できる業者は、このような情報も丁寧に説明してくれるはずです。
管理組合が知っておきたい防水工事の進め方
分譲マンションの場合、防水工事は管理組合が主導して行うケースがほとんどです。
以下は、一般的な進行スケジュールです。
- STEP
劣化調査・診断の実施
防水工事を行う前に、まず必要なのが建物の劣化状況を正確に把握するための調査・診断です。
専門業者が屋上やバルコニー・外壁などの状態を目視・打診・機器によって調べ、ひび割れや浮き・漏水跡などの有無を確認します。
この調査結果にもとづき、どの範囲に防水工事が必要か、どの工法が適しているかを判断します。
マンションの維持管理計画において、最初のステップであり非常に重要な工程です。 - STEP
工法・業者の選定
調査結果を踏まえて、最適な防水工法と施工業者を選定します。
ウレタン防水やシート防水・アスファルト防水など、それぞれの特徴と費用を比較検討し、建物の状況や管理組合の希望に合った工法を決定します。
同時に、過去の実績や保証内容・施工体制などをチェックし、信頼できる業者を選ぶことが肝心です。
複数社から見積もりを取り、透明性の高い選定プロセスを心がけましょう。 - STEP
予算案の作成と合意形成
選定した工法と業者をもとに、詳細な工事費用を見積もり、予算案を作成します。
この予算には、施工費だけでなく足場設置費・廃材処理費・共用部分の清掃費用なども含める必要があります。
また、修繕積立金の残高や必要に応じた一時金の有無など、資金計画も併せて整理します。
住民への説明資料を用意し、分かりやすく内容を共有することで、合意形成をスムーズに進められるでしょう。 - STEP
総会での承認
防水工事は共用部の大規模修繕にあたるため、管理組合の総会で正式な承認を得る必要があります。
理事会が準備した調査報告書や見積書・予算案をもとに、居住者へ説明を行い、質疑応答や意見交換を経て、最終的な議決に至ります。
住民の理解と協力を得るためには、丁寧な情報提供と、将来的なコスト削減や建物の寿命延長といったメリットを明確に伝えることが重要です。 - STEP
工事開始~完了
承認を得たら、いよいよ工事開始となります。
着工前には施工業者と打ち合わせを行い、工程表や安全管理体制、住民への告知方法などを確認します。
施工中は騒音やにおい、通行制限などが発生するため、影響を最小限に抑える工夫が必要です。
また、進捗や問題点を随時報告してもらいながら、理事会や管理会社が連携して管理を行い、予定通りに工事が完了するよう監督します。 - STEP
引き渡しと報告書の受領
工事が完了した後は、施工内容の最終確認と引き渡しが行われます。
施工箇所の仕上がりや性能試験の結果をチェックし、不備があれば補修対応を依頼します。
問題がなければ、業者から工事報告書や保証書を受け取り、管理組合で保管します。
報告書には施工写真や使用材料の情報、今後のメンテナンス方法などが記載されており、将来の修繕時にも参考となる重要な資料です。
特に「総会での承認」では、居住者全体の理解と協力が不可欠です。
丁寧な説明資料や工事の必要性・効果を伝えるための写真・動画を用意すると、合意形成がスムーズになります。
まとめ
マンションの防水工事は、単なる雨漏り対策にとどまらず、建物そのものの寿命を延ばし、長期的な資産価値を守るためにも極めて重要なメンテナンスです。
外観の美観や内部構造の健全性を維持するうえでも、防水層の劣化を見逃すことはできません。
特にマンションのような集合住宅では、ひとつの漏水トラブルが複数の居住者に影響を及ぼすため、早期発見と計画的な対応が求められます。
信頼できる業者に適切なタイミングで工事を依頼することで、安心・安全な住環境を実現できます。
また定期的な点検や、工法・材料に関する正しい知識を管理組合が持つことも重要です。
住民の理解と協力を得ながら、一丸となって防水工事に取り組むことで、無用なトラブルを防ぎ、快適なマンションライフを長く維持することができるでしょう。
おすすめサイト
大進双建:神奈川の防水工事と雨漏り修理

神奈川を中心に、千葉・埼玉・東京で雨漏り・防水工事・シーリング工事、屋根外壁の事なら大進双建まで。
株式会社修工舎
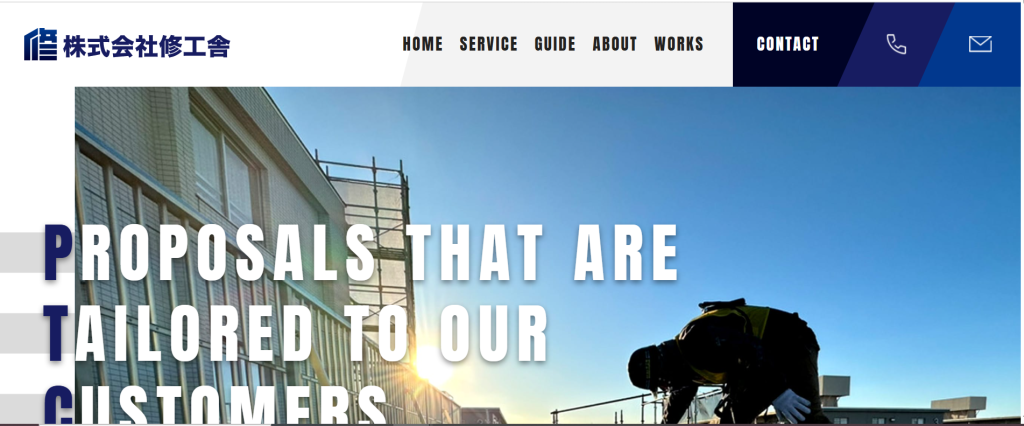
株式会社修工舎は、戸建やマンションといった建物の修繕にかかるさまざまな工事を請け負っております。修繕工事をメインとしているため、可能な限りご対応いたします。
大規模修繕コストカットナビ
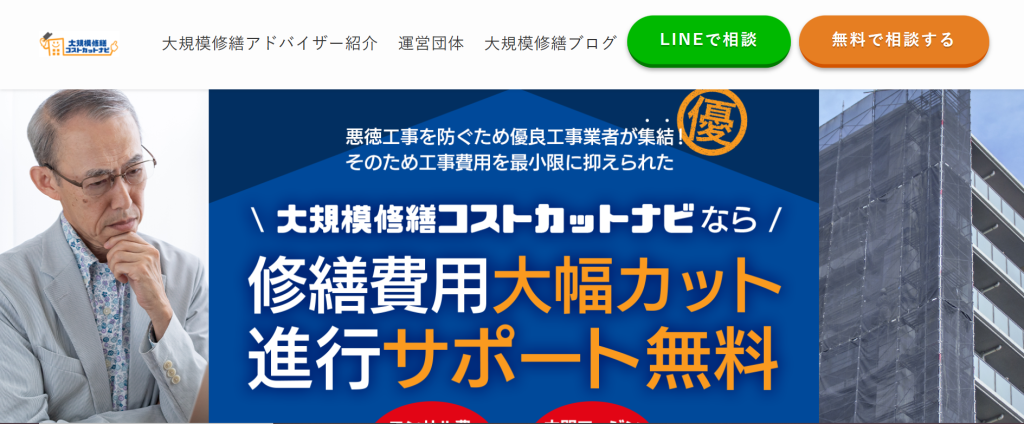
「大規模コストカットナビ」は、マンションや大型建物の大規模修繕における 「コスト削減」 と 「業者の選定」 の悩みを解消するための無料サポートサービスです。
防水工事見積もりcom
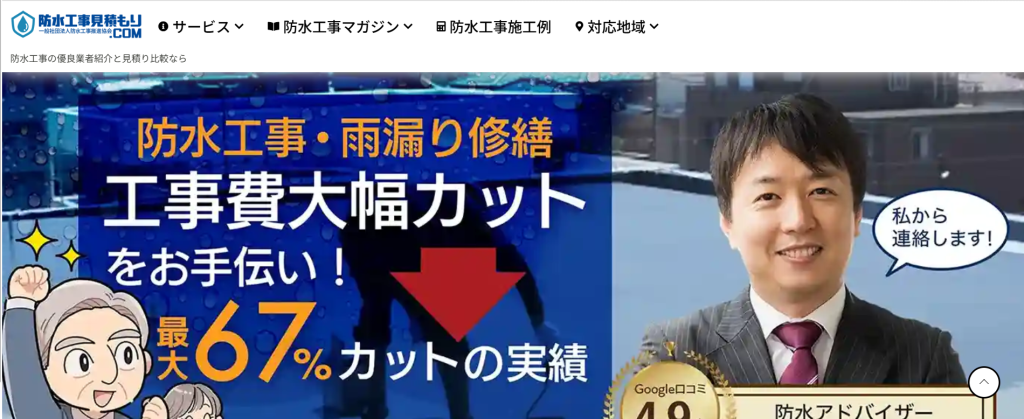
防水工事見積もり.comは加盟業者からの加盟金で成り立っています。お客様に対する手厚いサービスを心がけ、多くの方にご利用いただくことで、加盟業者が継続して登録をしていただくことができます。